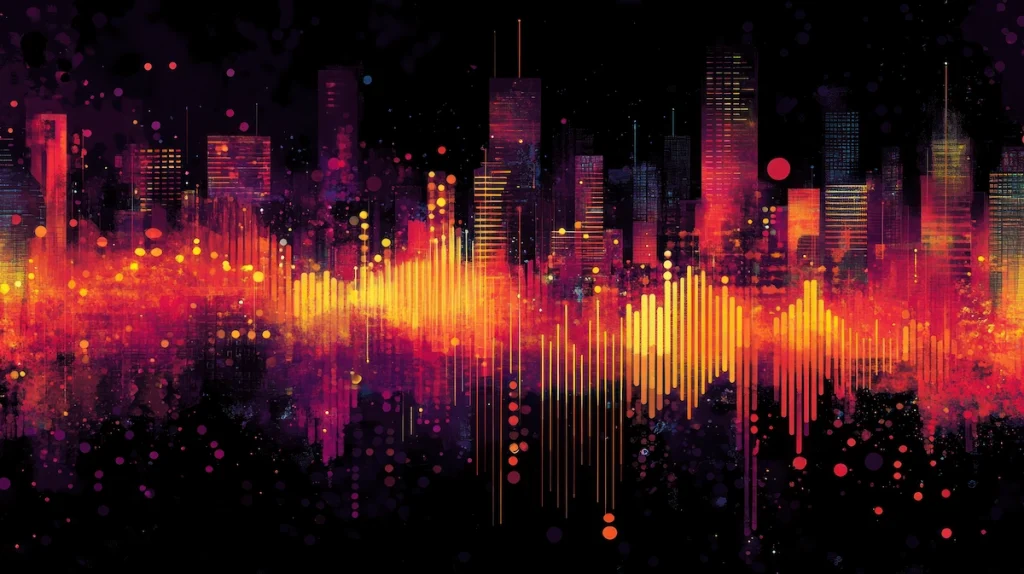【ハイブリッドワーク】出勤か、リモートか。最適化へ向けた現在地

戦略的ニーズに焦点を当てた、英国のリサーチ企業Leesmanの新しいレポートによると、従業員個人から都市・社会全体に至るまで、ハイブリッドワークの“ゴール”は揺れ動いている。
Culture, Style
多くの企業はハイブリッドワークの運用ルールを細かく変更している。そうした中、Leesmanが新たに公開した調査レポート「The Hybrid Future: Redefining Possibilities」(ハイブリッドな未来:可能性の再定義)は、企業が検討すべき課題や機会、戦略の進化にスポットを当てている。
2023年7月から2024年10月まで8回にわたって実施したこの調査は、従業員、企業、社会がハイブリッドワークの複雑さにどう対応しているかの知見を提供するものだ。調査には計3,988人の従業員が参加している。
ハイブリッドワークは、従業員にとって依然として仕事に対する満足度を左右する主要な要素であり続けている。圧倒的大多数(91%)がハイブリッドワークを好み、74%が勤務の継続または就職の意思に影響すると回答。ワークライフバランスが仕事の満足度に直結する最重要要素である今、さまざまな場所で働ける柔軟性は、従業員が仕事に抱く常識に変化をもたらしている。ただ、従業員が実際にどう感じるかは、職務内容、職位、企業方針などによって大きく異なる。
ハイブリッドワークは生産性にプラスと回答した従業員は83%に上る一方、課題も残る。対面の共同作業とリモートの効率性との最適なバランスの答えはまだ出ておらず、企業は苦戦し続けている。

リモートワークは「つながり」を弱める
ハイブリッドワークモデルで最も大きく変わったのは、ミーティングや共同作業の性質だろう。オフィスは今でもチームワークの拠点と見なされ、59%が出勤は主にミーティングや共同作業のためと回答している。だが、ハイブリッド会議にはこんな課題もある。
・ オフィス参加者の40%が、リモート参加者との関わりに難しさを感じている
・ リモート参加者の41%が、オフィス側の話し合いから取り残されていると感じている
・ 30%がビデオ会議疲れを経験している
・ ブレインストーミングが効果的なのは、オンライン(39%)より対面(58%)と考える人の方が多い。この傾向は特に幹部層で顕著
また、リモートワークは柔軟な働き方ができる一方、従業員同士のつながりを弱める。4人に1人がリモート勤務では同僚から切り離されているように感じると回答する。上級幹部の間ではこの懸念はさらに高まり、58%がつながりを保つことが難しいと回答している。

通勤がネック
オフィスの役割が変わるにつれ、通勤の捉え方にも変化が見られる。半数近くの人が通勤のせいでオフィスに行く気がそがれると回答し、38%が通勤を時間の無駄だと考える。だが、通勤している人たちの中には、じっくり考え事をする時間として活用(31%)、リラックスする機会(18%)など、通勤に価値を見いだしている人もいる。
出勤促進を目指す企業にとっては、オフィスの立地改善、柔軟な勤務時間、通勤費補助など、通勤改善は極めて重要だ。

幹部層はリモートワークにややネガティブ
Leesmanのレポートで最も際立っていた点の1つが、幹部層が従業員以上にハイブリッドワークを困難に感じていることだった。従業員がおおむね新しい働き方に適応する一方、幹部層は企業文化の維持、エンゲージメント醸成、ハイブリッドなチーム間での均等な参画という点で課題が大きいと回答している。
・ 主要な意思決定に参加できていないと感じるのは、リモートワーク従業員の場合4人に1人だが、上級幹部層では3人に1人
・ 従業員のうち、62%がハイブリッドワークが企業文化にプラスの影響をもたらすと考える一方、13%はマイナスだと考えている
・ 企業は信頼に基づいたリーダーシップのモデルに向かいつつあり、目の前にいることより成果を重視するようになっている
変化への適応を進める中で、多くの企業がハイブリッドワークに対する方針に磨きをかけ、企業文化の維持、インクルージョンの確保、より良いリーダーシップツールの提供に関して新しい方法を試している。

バランス・適応・継続的な改善が重要
ハイブリッドワークは職場に変化をもたらすだけでなく、街全体にも影響を及ぼす。都市圏では、中心部でオフィス需要が低下する一方で郊外の地元経済が活性化するという経済シフトが見られている。
ハイブリッドワークはサステナビリティにも影響する。通勤減少は排ガス削減につながるからだ。ただし、そのトレードオフとして、個々の世帯で使用されるエネルギー量は増えている。また、ハイブリッドなモデルでは障がいがある人、介護者、リモートワーカーが働きやすくなるため、職場のインクルージョン向上も見られる。
このような変化は、政治と企業が協力し、サステナブルでインクルーシブなハイブリッドワーク環境を整備していく必要性を強く感じさせる。
Leesmanのレポートは、ハイブリッドワークが今後も定着していくものの、その将来的な姿がまだ形成中であることを明確に示している。一部には、生産性、イノベーション、企業文化の向上につながると信じてフルタイム出勤を求めている企業もある。だが、データが示すのは、従業員が圧倒的にハイブリッド勤務を好み、この変化に対応できない企業は最高の人材を失うリスクがあるということだ。
ハイブリッドワークの未来は、リモートか出勤かという選択の問題ではない。問題とすべきはバランス、適応、継続的な改善だ。従業員の声に耳を傾け、ハイブリッド戦略に磨きをかけ、柔軟な働き方を支える職場を生み出せる企業が、成功に最も近づくことになるだろう。
Leesmanのレポート「The Hybrid Future: Redefining Possibilities」の完全版はこちら。
※本記事は、Worker’s Resortが提携しているWORKTECH Academyの記事「The hybrid future: balancing flexibility, productivity and connection」(公開日:2025/2/26)を翻訳したものです。