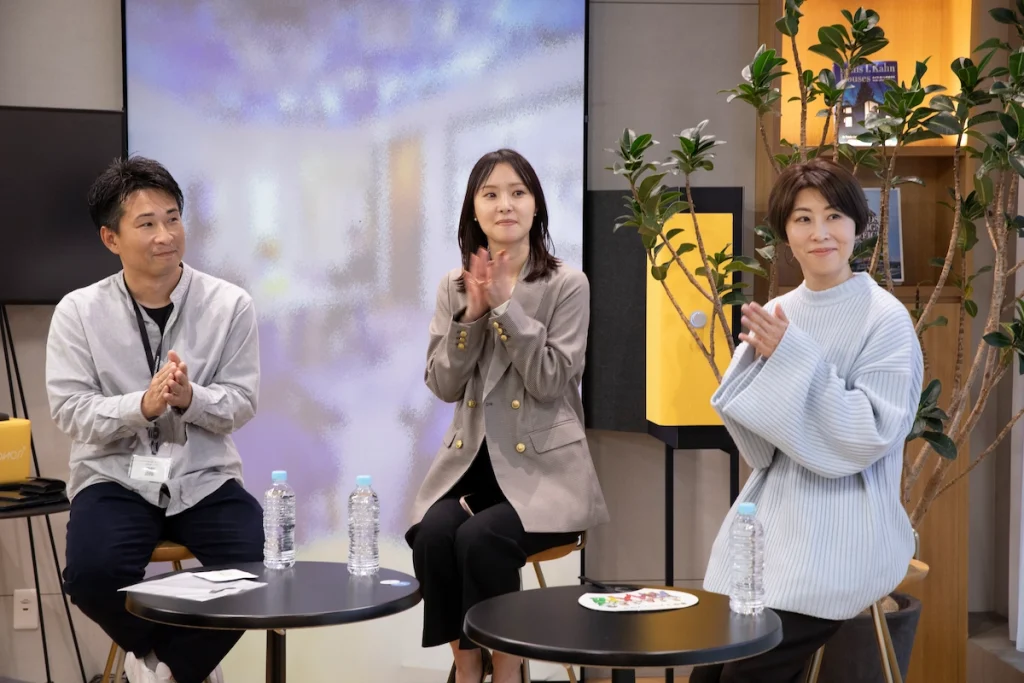【オフィス再定義】オフィス回帰の真意を探り、グローバル視点で考える2030年の働く場

コロナ禍の混乱は、「出社して働く」という日本人の価値観に、リモートワークという選択肢をもたらしました。そんな変化から5年強、今やリモートワークの環境が整った企業であっても原則出社を掲げるなど、日本ではオフィス回帰の動きが見られます。同時に、イノベーションの創出、人材獲得競争力の向上、ワーカーのエンゲージメント向上といった観点から、働き方やオフィスの再定義に取り組む企業も珍しくありません。
そこで今回は、オーストラリア、香港を中心に海外のワークプレイス構築に携わり、日本でのオフィスコンサルティングの経験も豊富な、カルダー・コンサルタンツ・ジャパンCEOの奥錬太郎さんにインタビュー。オフィスを巡る海外の動向や最近の傾向を踏まえ、これからのオフィスづくりに問われる視点を語っていただきました。
Facility, Culture, Style
-
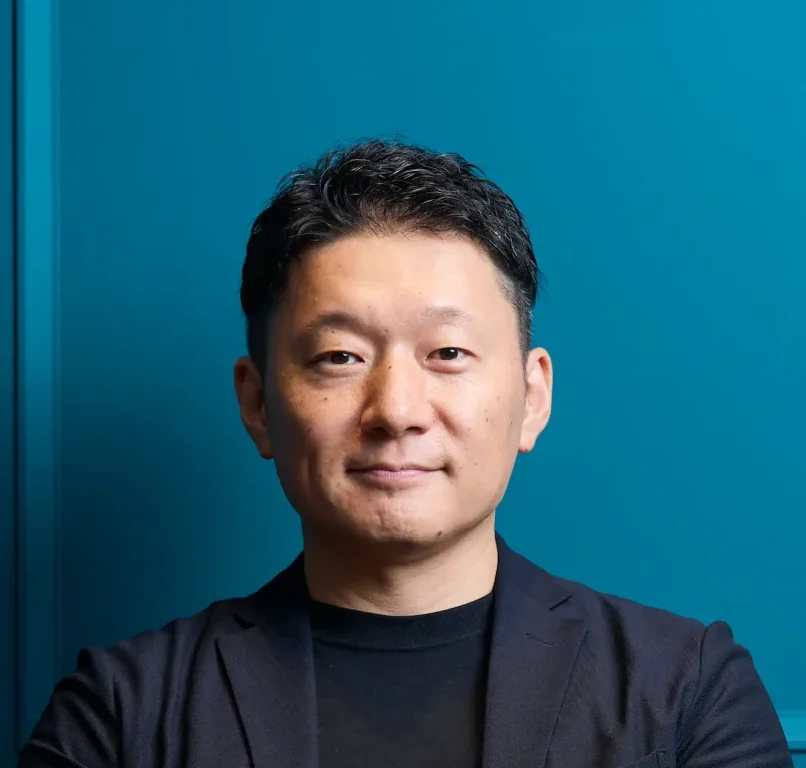
奥 錬太郎/おく れんたろう
カルダー・コンサルタンツ・ジャパン株式会社 ファウンダー/CEO。2005年よりオーストラリアや香港にてオフィスデザイン・コンサルティング、CRE(Corporate Real Estate)戦略、ワークプレイス・チェンジマネジメント業務に従事。大規模オフィス建築プロジェクトなど数々のプロジェクトに参画し、高い評価を獲得する。DEGW(シドニー)、マッコーリーグループ(シドニー/香港)、ウッズ・バゴット(香港)、CBRE(東京)を経て、2018年にジェームス・カルダー氏と共にカルダー・コンサルタンツ・ジャパンを設立する。美しい日本文化に根差した、働く人々が幸せになれるワークスペースの実現に邁進中。
オフィス回帰はなぜ進む? 日本型組織文化とコミュニケーション
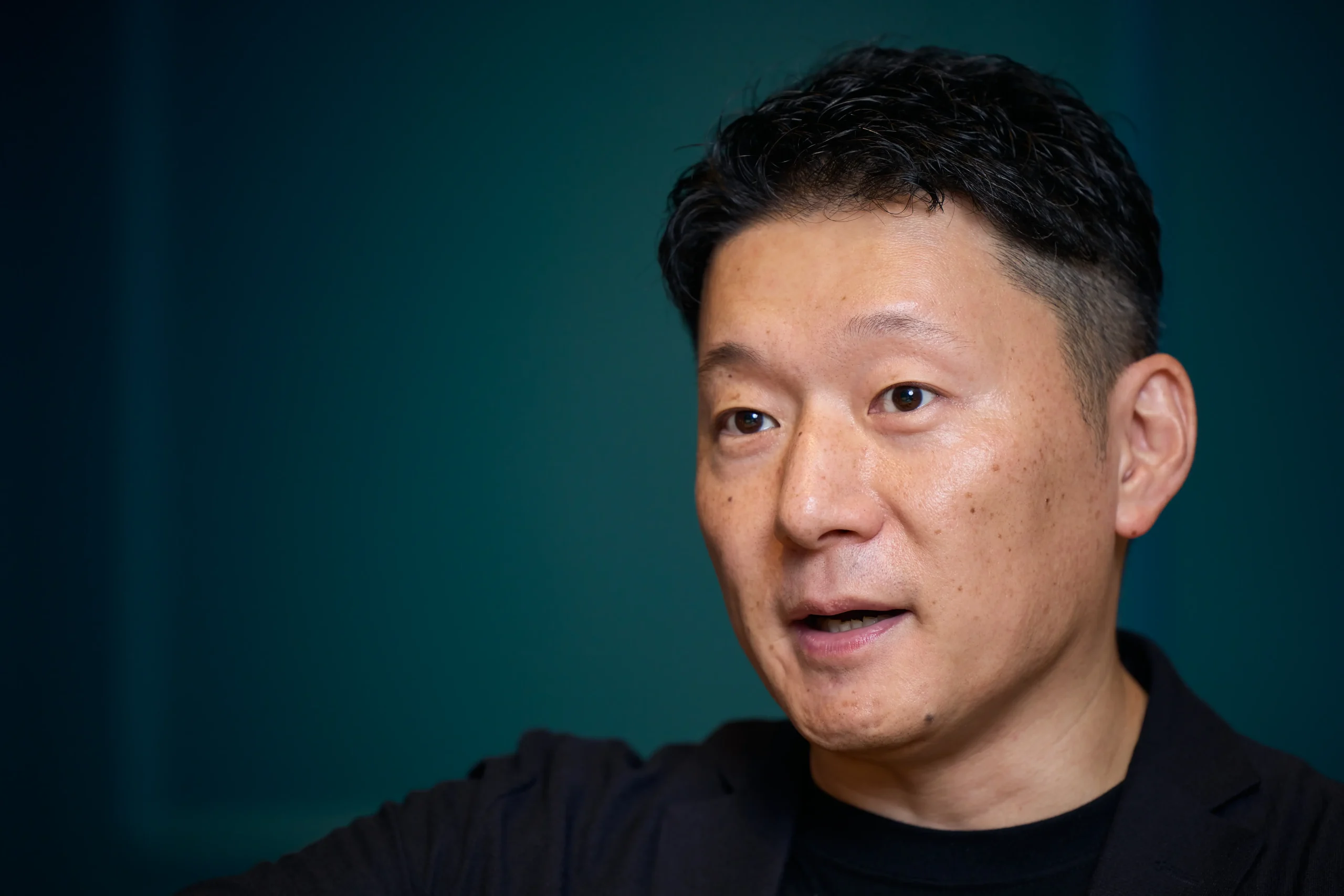
──奥さんは海外のオフィス事情にも精通していらっしゃいます。私たちの働き方に大きな影響を与えたコロナ禍から5年あまり、現在の傾向などについて教えてください。
奥 2020年から始まったコロナ禍により、オフィスへの出社が強制的に制限されました。そこで一気に普及したのがリモートワークです。当時は、エッセンシャルワーカーのような出社や対面が求められる職種を除き、自宅などオフィス以外の場所で仕事を進め、会議や打ち合わせはオンラインで行う、リモートワークを基本とした働き方が主流となりました。この辺りの変化は皆さんが知るところだと思います。
2025年現在、そんな働き方はどうなっているのでしょうか? 海外では、週2~3日出社、そのほかはリモートワークといった働き方に落ち着いている企業が多い印象です。米国では、アマゾンやテスラのようなテック企業が週5日のオフィス勤務を義務づけたとしてニュースになりましたが、それはごく一部の動きです。欧米豪の多くの企業は、リモートワーク主軸のハイブリッド型が主流で、デスクの平均利用率が最も高いとされる英国ですら、約50%しかないというデータもあります。一方、日本では、オフィス回帰の傾向が強まり、オフィス勤務主軸のハイブリッド型を選択する企業が目立ちます。

──背景には、コミュニケーション面の課題があるといわれます。
奥 一般論として、リモートワークはコミュニケーションがとりにくいといわれています。ただ、オーストラリアをはじめ、個々の業務範囲が明確でプロセス以上に成果を重視する働き方が主流の海外では、コロナ禍以前から一定程度リモートワークも浸透していました。ですから、リモートワークがコミュニケーションにもたらすインパクトは日本ほどではなかったはずです。とはいえ、偶発的な接触から生まれる創造性やチームワーク、意思決定のスピードなどに負の影響があったことは否めないでしょう。
日本の場合は、ハイコンテクスト(非言語的情報によるコミュニケーション)面の課題に加えて、日本型の就労慣行や人事制度が、オフィス回帰を加速させた要因だと見ています。「役割の線引きが明確でない」「周りに相談しながらプロジェクトなどを進めるケースが多い」「結果ではなくプロセスをより評価される」といった日本型組織文化のなかでは、上長も部下も同僚同士も、互いに目の行き届く場にいたほうが働きやすい、ということでしょう。つまり、コロナ禍という外圧によって、リモートワークを導入せざるを得なかった実情と組織文化の間で生じた歪みを修正しようしているのが、今の状況ではないしょうか。
──日本の場合、オフィス回帰の大きな理由は日本型組織文化にあると。
奥 そうですね。ただし、その組織文化を「自社の持続的発展のために理にかなったもの」だと捉えてあえて意図的に選択しているのなら、正しい戦略といえるかもしれません。そうではなく、そうした組織文化で発生しがちな「フォーマルに偏り過ぎた、無駄な忖度が蔓延したコミュニケーション」という、本来であればはるか昔に改善すべきだったやり方が残っているがためにオフィス回帰がなされているのだとしたら、どうでしょうか?
わかりやすい例だと、案件の起案前に遠い関係者にまであらかじめお伺いを立てておいたり、上長からの批判を回避するために提案用資料をつくり込み過ぎたり……。特に経営層が絡む段階になると、周りが事を大きくし、いろいろな立場の人が口出ししてくるので、その対応にも追われてしまう。本質的でない作業が仕事を増やし、意思決定を遅らせ、結果として生産性とエンゲージメントの低下を招いていますよね。
──そんな経験があるビジネスパーソンは多いと思います。
奥 ですから、何のためのオフィス回帰なのか、本当にコミュニケーションに課題があるのか、自社の組織文化にこそ変えるべき点があるのか、現状をあらためて見直す必要があります。その上で、働き方やオフィス戦略を再定義する必要があるでしょうね。
ちなみに、諸外国のコミュニケーションはもっとカジュアルです。たとえば、小さな提案であれば、アイデアが浮かんだ段階で、メモ書きなどを上司に共有しながら相談し、早々にジャッジが下されます。役職による裁量の違いはもちろん存在しますが、日本に比べ、過剰な根回しが要求されず、ストレートでインタラクティブな議論がなされる場面が多く見られます。肌感覚ですが、日本では3カ月かかるボリュームのものは、海外では1~2週間で何かしらの結論を出さないと、時間がかかり過ぎていると評価される印象です。
オフィスは唯一の答えではない。再定義のヒント

──働き方やオフィスの再定義というお話がありました。オフィス構築について、もう少し詳しくお聞かせください。
奥 オフィスとは本来、企業理念や経営戦略とひもづくように、柔軟に計画・設計されるものです。企業の経営戦略が100あれば、オフィスも100通りの解が存在します。企業の在り方が多様化し、経営を取り巻く環境が急速に変化し続けている現代においては、「これからのオフィスはこうすべき」と定めること自体、時代に合わなくなっていますよね。
日本企業のオフィスは長らく、蛍光灯が灯る天井にスチール製のパーティションで囲われた窓のない会議室、管理職がひな壇席に座り、それ以外が対向島型に座らされるレイアウトが一般的でした。実は、この環境は先に述べたような日本型組織文化との相性は悪くなかったといえます。極論ですが、今後もそんな従来型の日本的組織文化を貫くというのであれば、そのようなオフィスの在り方を変える必要はないかもしれません。
とはいえ、無機質で窮屈な空間や自由度が低いオフィスは、運用の柔軟さに欠け、人にストレスを与えます。また、創造性の発揮や共創といった、多くの企業が求める価値を生み出せる環境とは言い難いですよね。

──海外ではホテルのラウンジさながらのオフィス、大学のキャンパスのような解放感にあふれたオフィスなどもよく目にします。
奥 そうですね。たとえばオーストラリアでは、主な産業を鉱産資源に頼る時期が長く続きました。しかし80年代中頃から経済構造改革に取り組み、特に90年代以降、金融やIT分野が強化されてきました。そこで生じたのが人材の獲得競争です。優秀で自律した人材を世界各国からいかに呼び寄せるかという命題に、報酬だけでなく、オフィスなどの環境面に資金を投じた動きが今につながっています。この傾向はオーストラリアのみならず、アメリカや欧州も同様でしょう。
一方、日本は「失われた30年」といわれるように経済成長はほぼ横ばいでしたから、オフィスへの投資も諸外国の後塵を拝することになってしまいました。この10年ほどでやっと、日本企業のオフィスに対する認識の変化を感じます。
──確かに、コワーキングを誘発するオープンエリアやカフェテリアの充実など、いろいろな工夫が見られるようになりました。
奥 はい。洗練された家具を配置したりオープンエリアやブレイクアウトエリアを設けたりする企業が増え、働く人のパフォーマンス向上やコミュニケーション促進といった「いかに快適に働けるか(=エクスペリエンスを高めるか)」を追求する傾向が見られます。
ただ残念なことに、狙い通りのオフィス活用がなされていないケースがあるのも事実です。たとえば、「社内外との共創を図るはずの場が、シェアオフィスのような単なる個人作業をするスペースになってしまった」ということはないでしょうか。
──経営層やオフィスマネージャーが抱える課題のひとつだと思います。
奥 原因は大きく2つ考えられます。ひとつはコンセプトの段階でニーズを見誤っていた、すなわち必要のない「場」をつくってしまった。そこで働く人の行動に対する調査・分析が浅く、潜在的なニーズを引き出せなかったことに問題があります。
加えて、近年の「場づくり」には完成形がないということも忘れてはいけません。ガバナンスの強化が問われているのか、カルチャー変革を必要としているのか。そのときどきの企業が抱える課題によっても理想とする働き方は変化するだろうし、当然望ましい空間も変わってくるはずですから。
もうひとつは、変化を成功に導くチェンジマネジメントの不足です。新しいオフィスや働き方を導入する際には、その目的や理由、そのオフィスを使う人それぞれにとってのメリット(とデメリット)を明確に理解してもらう必要があります。個々の社員が仕事への向き合い方を自問できるよう、会社側からの意図的な働きかけが不可欠でしょう。
海外企業の場合、インナーコミュニケーションの総量が、日本企業に比べて圧倒的に多いと感じます。どんな組織でありたいかという総論から、カフェテリアのメニューまで、ありとあらゆる情報をコンスタントに発信しています。経営層が公の場で語ることはもちろん、メールマガジンやサイネージ、タウンホールミーティングなど駆使するツールもさまざまです。
中長期的なスパンで働く場を育てる視点

──オフィスマネージャーの役割は近い将来、たとえば2030年を見据えるとどうなっていくと考えますか?
奥 まずは、オフィス構築への投資効果はもちろん、コワーキングスペースやインキュベーション施設のような外部拠点をどんなバランスで取り入れるのか、誰を利用対象とすれば経営上の効果を期待できるのかなど、ワークスペースに対してこれまで以上に戦略的視点を持つことが求められると思います。そこでは、自社が所有する不動産全体のポートフォリオや5年後10年後の組織とワークスペースとの整合性を取るための戦略など、一度つくったオフィスを「使い切る」中長期的な視点も重要になるでしょう。
また、繰り返しになりますが、オフィスは自社の経営戦略や組織文化を体現し、いかにより快適に働けるのかを追求する場でもあります。たとえば、従業員の自律を促したいというのであれば、働き方の自在度を高めた自律性を育む環境を提供すると同時に、人事制度や評価手法といった枠組みの再構築が必要になるかもしれません。共創の機会を高めたいならば、人と人とが交わる場を提供するだけでなく、彼らを共創に導く仕掛けも必要となってくるでしょう。
これからのオフィスマネージャーには、さまざまな分野の専門知識を統合して、総体的な働く環境をつくる役割が求められます。つまり、データに基づいた根拠を提示することによって、経営陣が、オフィスを単なる作業場ではなく投資効果も含めた経営資源として捉え、自信をもってオフィスに関する意思決定を可能にするための参謀役のような存在になっていくのだと思います。