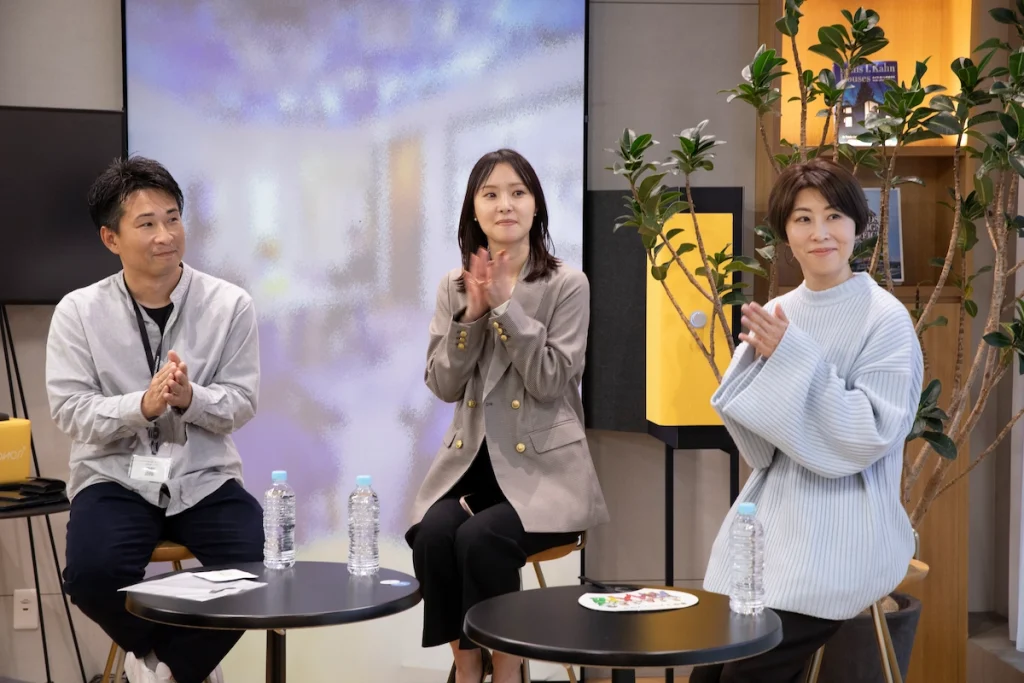オフィスの価値を高め、未知の価値を生み出す。ロフトワーク・加藤翼さんに聞くコミュニティ・マネジメント

働く人と人がオープンに交わり、新しい価値が生み出される。そんな活気にあふれたオフィスは、場を整えるだけではつくり上げることができません。では、何が必要なのでしょうか?
Worker’s Resort編集部が尋ねたのは、株式会社ロフトワークでLayout シニアディレクターを務める加藤翼さん。加藤さんは、新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点「100BANCH」や、会員制の共創施設「SHIBUYA QWS」などのコミュニティマネージャーとしてコミュニテイ・マネジメントを手がけるほか、企業のコミュニティづくりの支援やコミュニティマネージャーを養成する学校「BUFF」の運営に携わっています。
コミュニティ・マネジメントの第一人者である加藤さんに、コミュニティとオフィスについてお話を伺いました。
Design, Culture, Research Community
-

加藤 翼/かとう つばさ
株式会社qutori CEO
株式会社ロフトワーク シニアディレクター
BUFFコミュニティマネージャーの学校、創設代表
1990年千葉県柏市出身。「共創」をテーマにしたコミュニティマネージャーとして、他分野のコミュニティを横断する事業を多数手がける。早稲田大学で哲学を専攻後に、外資系コンサルティング企業に勤務。デザインスクールを経て、株式会社ロフトワークに入社。100BANCH、SHIBUYA QWSの立ち上げに携わる。2017年 株式会社qutoriを創業。コミュニティマネジメントに特化したプロフェッショナルファーム「BUFF コミュニティマネージャーの学校」、ブランドを応援するポップアップメディア&コミュニティ「POPAP」、南麻布に位置するCafe&Gallery「muun」を運営する。
コミュニティという生き物の最適解を探り続ける

――コミュニティマネージャーとは、どのような役割なのでしょうか?
加藤 まずは、コミュニティとは何かを簡単に定義してみます。共通の利害関係やテーマを持っている人々の集団のことで、基本的に内発的な動機で自発的に参加するものです。そして、このコミュニティが機能するには、「なぜ集まるのか」という動機づけがとても大事になります。
たとえば、私が関わる場「SHIBUYA QWS(以下、渋谷キューズ)」であれば、「問いから未知の価値を生みだしたい」という共通の価値観があります。どんなものでも構いませんが、共通する動機や価値がなければコミュニティは成り立ちません。ただ一方で、共通の価値さえあればうまくいくかというと、そうとも限りません。何かしらの刺激がないと化学反応は起きにくいんですね。また、多様な人が集まると、利害関係が異なるケースも生じます。
そうしたなかで、普段なら交わりにくい人同士を引き合わせたり、健全な緊張状態をつくりだしたりして、人のつながりに介入し、組み替え、時に切断しながら場の価値を高めていくのがコミュニティマネージャーの役割だと考えます。とはいえ、決して新しい仕事ではありません。学校や地域の活動、スナックのママさんまで、多くの先人たちが同じような役割を果たしてきはずです。
――時代背景や場所などによって、コミュニティマネージャーにもいろいろありそうですね。
加藤 コミュニティマネージャーは、企画フェーズや運用フェーズなど、いろいろなレイヤーに存在します。たとえば、私は渋谷キューズで今、主に運用フェーズにおけるディレクターという役割を担っています。
会員数の変動やコミュニケーションの密度などを見ながら、空間内のレイアウトを変えたり、ワークショップなどの機会を増やしたり、スタッフの育成に携わったりしています。集まる人たちのコミュニケーションの質を高めるため、UXにテコ入れするようなイメージですね。
そのほかのプロジェクトでは、企画や場のデザインのフェーズに参画することも多く、建築家や家具メーカーの方々と、どういう空間にすればコミュニティの目指すところに近づけるのかを一緒に検討するなどしています。
さらに、コミュニティは「生きもの」ですから、最適解は常に変わっていきます。建築物と違って一度として完成することはありません。フェーズに応じて、こうしたらいいのか? ああしたらどうだろう? と試行錯誤を繰り返すことにも意義があります。「コミュニティをつくったら終わり」とはならないんです。そこが面白いところでもあり、飽きないところでもありますよね。
受け手が「場」をどう捉えるのか? 意味のデザインこそ真髄

――オフィスの価値を高めるオフィスマネージャーの役割と、場の価値を高めるコミュニティマネージャーの役割には、多くの共通点がありそうです。
加藤 確かに多くの共通項はありますよね。なぜならコミュニティとは、いわば「世界の見方」のようなもので、コミュニティという視座で見ることができると、一つひとつの言葉に意味を込められるようになり、行動変容も促せるからです。
ですから、「それは、ブランディングと何が違うのでしょうか?」と質問をいただくことがあります。もしそれが総務であれば、「オフィスの価値を高めるプロパティマネジメントと何が違うのか?」となるのでしょう。たとえば、リモートワークが浸透したことで生じた「なぜオフィスで働くのか?」という疑問に対する、「モチベーションが上がる」「コミュニケーションが取りやすい」などの解。その仕掛けをつくっていくという点で、コミュニティマネージャーの考え方が生きてくるはずです。
ひとつ興味深い話があります。特定のコーヒーショップで勉強や仕事をする人を揶揄(やゆ)するような「どうしてコーヒーショップで勉強なんかしているんだ?」というSNSのポストに対し、地方の高校生が「そのショップには、今の自分の生活のなかではなかなか出会わないようなキラキラした人がいる。その景色のなかにいることが勉強のモチベーションになる」と反応したんです。
それこそが、コミュニティの思考ですよね。環境を整えることではなく、受け手がどう捉えるかを考えることに本質がある。そこでは、この環境がどう受け取られるのか、何がモチベーションになるのかといった「意味のデザイン」が求められます。それが結果として、生産性や創造性、エンゲージメントに寄与します。
また、立場が違えば重要なところや大切にしたいところも当然違ってきて、バランスの重要性やせめぎ合いも生じます。コミュニティ要素に振り切るとカオス化するだろうし、逆にオフィス・マネジメントに振り切ると機能や効率化が重視されて同質化してしまうでしょう。「せめぎ合いによるバランス」が、よい場を築いていくのだと思います。
――KPIマネジメントなどによって管理・評価することが難しいですね。
加藤 そうかもしれません。さまざまな要素が合わさって定義すらできない「まだ見ぬもの」を内発的に生み出すのが、コミュニティだからです。指標で割り切れないところがあります。
ですから私は、「自社でマネジメントしきれる集団を求めるのであれば、コミュニティはやめたほうがいいですよ」とアドバイスしています。目指すアウトプットが明確で時間に限りがあるのなら、もっと効率的なやり方があるはずです。つまり、すべての業務をコミュニティ思考で進める必要はありません。
だからといって、効果の再現性を問わないわけではありません。私たちの場合、会員数とか滞在時間とか、いろいろなところにセンサーを仕込んでおいて、目的にかなう行動変容を起こすのは何かをつぶさにウォッチしています。そのデータや経験から未来を予測する、たとえるなら天気予報に近いですね。予測の確率を上げていくと、再現性にもつながっていくはずです。
心の機微に気づけるかどうか

――次に、加藤さんが運営されている、コミュニティマネージャーの学校「BUFF」について教えてください。
加藤 BUFFは、「コミュニティ・マネジメントをすべての組織の当たり前に」をビジョンとして、コミュニティ・マネジメントのプロとして活躍できる人材を育成しています。コミュニティ・マネジメントに関係するナレッジは、Web上にあふれていますが、コミュニティの洞察やアプローチの仮説検証には実践が不可欠です。また、同じ志を持つ仲間を通じ、コミュニティの多様さに気づくことも重要な学びです。
たとえば、必ず課しているのは、「コミュニティに対する自分なりの定義」を定めることです。大切なのは「あなたにとって」なので、「正解を探そうとしないでほしい」「自身の信念を表現にしてほしい」とアドバイスしています。
また、コミュニティの価値を向上させるためには、メタ認知や内省がとても大事になります。渋谷キューズの場合、「他者に問うことができたか?」「問いに対して思考できているか?」などですね。それがないと、ただの「場」で終わってしまいます。システム的にその機会や問いを増やすにはどうすればいいのかなどを議論しています。ただし、肌感覚や身体知で内省できる人もいるため、言語化にはこだわっていません。
――コミュニティマネージャーには、内なる情熱が問われるということでしょうか。
加藤 そうです。そして、それこそが日本の、特に大企業におけるコミュニティの問題だと思います。総論では「仕事につながるコミュニティをアクティベーションさせることが大事」と賛成するのだけれど、「じゃあ誰がやるの?」となってしまうんです。社員の大半は、コミュニティづくりがしたくてその会社に入ったわけではないですから。
とはいえ会社には、あの人とあの人をつなげようとか、コミュニケーションが活発になるようにこんなことをやってみたいとか、実際に何かを仕掛けてニヤニヤしているとか、そんな人たちっていると思います。目の前の人の表情や仕草から心の機微に気づけるとも言え、そうした感覚自体が、コミュニティマネージャーにとって大事な要素です。
一方で、その気づきができるか否かは、はっきり分かれると思います。気づけない人は、「みんな忙しそうっすね!」で終わってしまう。「いやいや、あの人何か言いたげだったじゃん、話しかけて何があったか聞いてごらんよ」と気づける人なら、その先の場のデザインなどに展開できます。コミュニケーションが得意な人なら直接的に対話すればいいし、「これを仕掛けたら、みんなの動きが変わったぞ! ははは!」みたいな自己完結的なアプローチでも、コミュニティがうまく機能するなら正解です。
所属を超えて、社会全体に作用をもたらす存在になる
――加藤さんの考える、コミュニティマネージャーのやりがいや未来像を教えてください。

加藤 ビジネスの分岐点や成功の瞬間に立ち会えたり、人から直接感謝されたりすることが醍醐味でしょうか。特に大きな組織にいると、エンドユーザーからかけ離れたところで働いている人も多いですよね。コミュニティ・マネジメントは、現場で生身のリアクションに触れられます。その経験はほかの業務でも活きるはずです。
BUFFを始めた当初は、コワーキングスペースの運営に携わる方の受講が多かったのですが、働き方改革やコロナ禍を経て、企業のマネージャークラスやフリーランスの方など、いろいろな属性の人に参加していただいています。高校からの講義依頼もありました。今や、コミュニティ・マネジメントは属性や年齢に関係なく、スキルのひとつとして注目されつつあると思います。
たとえば、労働人口が減少している日本の状況を踏まえると、やるべき仕事に対して、その場その場でチームを組んで取り組む必要性が増していくでしょう。また、テクノロジーの進化などに伴い、働く場や時間の制約から解放されていきつつあります。その潮流のなかで、これまでと同じチームややり方でないと仕事ができないのでは困ります。
そんなシチュエーションでも、多くの人がコミュニティの考え方や振る舞いを理解していれば、より柔軟にいろんな課題に対応できるはずです。法整備や社会通念の転換などの要因も絡みますが、私は、コミュニテマネージャーは所属組織を超えて社会全体に作用をもたらす存在になると確信しています。見えないリーダーとかヒーローとか、そんなイメージですね。
- 連載「オフィスマネージャーの本音」のその他の記事はこちら
本記事はリサーチコミュニティ会員限定記事です。
リサーチコミュニティとは、総務などオフィス運用やマネジメントに携わる人のみの会員制サービスです。
限定記事の閲覧のほか、各種特典もご用意しております。