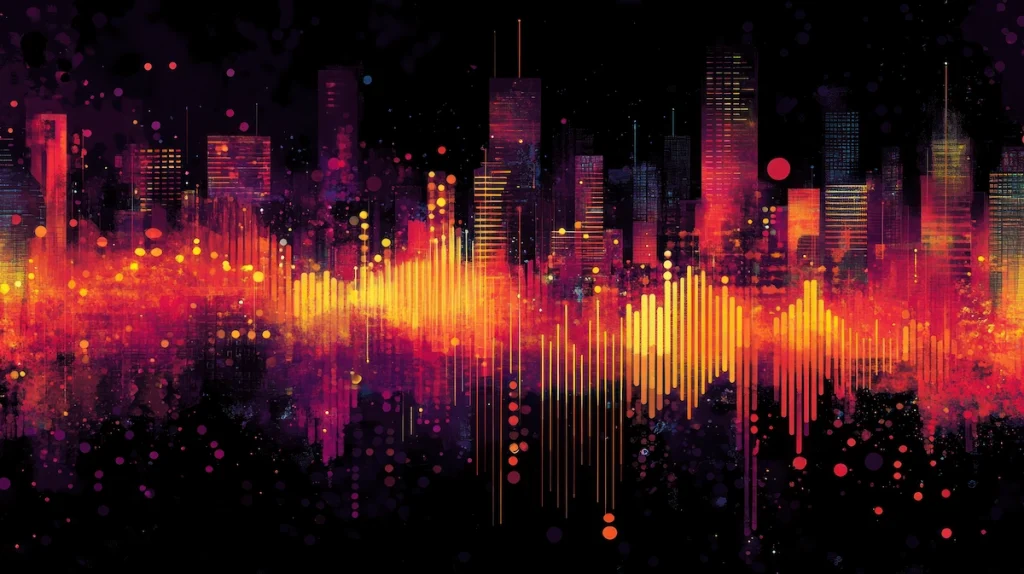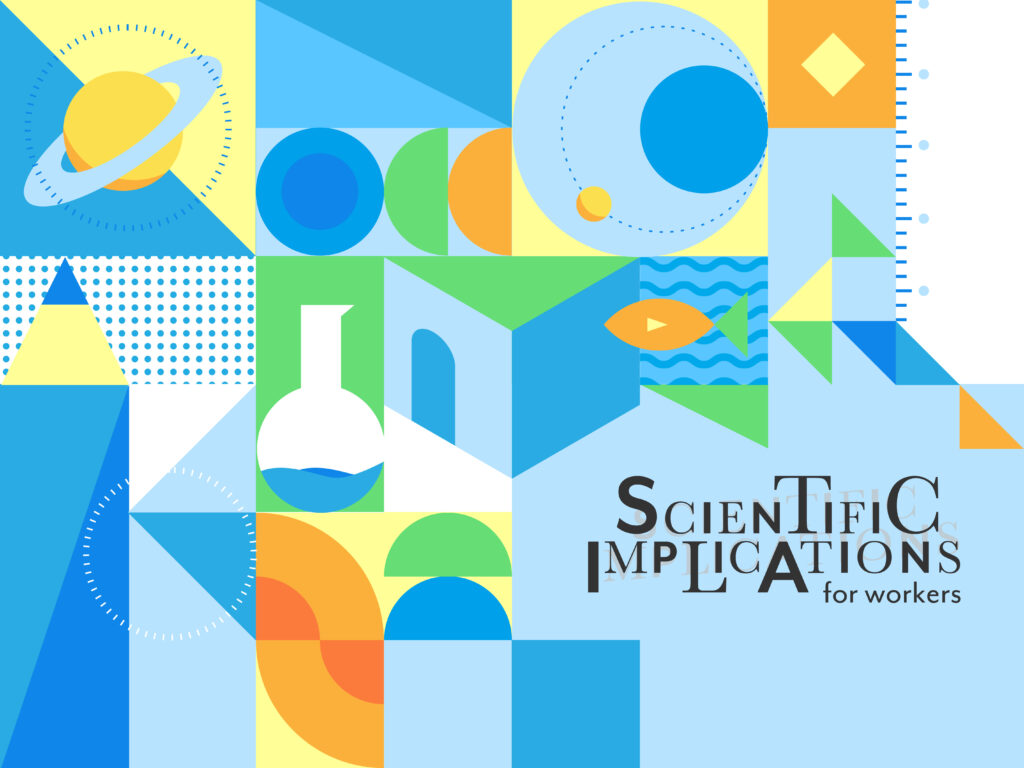リアルタイムのデータ活用! 職場の実態やニーズに最適化したオフィスの築き方

多くの企業が今、オフィスに求められる新たな要件を満たすべく、人々の働き方に合わせたオフィス設計のあり方を模索している。本記事では、そんなオフィス利用に関する最新の調査結果を紹介する。
Design, Technology, Style
ハイブリッドワークの試験的な段階を経て、それぞれの企業でオフィス設計の成果と課題が見えてきている。オフィス利用率の計測や分析を専門とするVergeSenseは今年5月、「2025 Workplace Occupancy and Utilisation Index(2025年オフィス稼働率・利用率指数)」を公表。世界50カ国の企業が利用する1億5,600万平方フィート(約1,449万2,874平方メートル)のワークスペースに関するデータを調査対象とし、多くの組織がコロナ禍以前と同じオフィス設計の方針を維持する背景について分析した。
企業が働き方の刷新に尽力しているにもかかわらず、物理的環境の整備はまだ遅れをとっている。また、会社のデスク利用率は徐々に上がっているものの、オフィススペースの大部分はまだ十分に活用されていないか、効果的に使われていない。
そんななか、VergeSenseのレポートは、各社に共通するミスマッチがあると指摘。働く人々が求めているのは、オフィスにおけるプライバシーの確保やフレキシブルな利用環境、小規模な会議スペースなどだが、そのニーズはいまだ満たされていない。それどころか、現実に提供されているのは、広々とした会議室や空いた状態で並ぶデスク、ハイブリッド派の働き方に合わないコラボレーションエリアといった設備がほとんどで、結果として業務が円滑に進みにくく、軋轢が生まれやすい環境になってしまっている。

「見せかけの会議室不足」はなぜ起きる?
ビジネスにおけるコラボレーションの重要性が叫ばれるなか、会議室の大半は本来の目的通りに利用されていない。たとえば、オフィス会議の4分の3以上(77%)が出席者2名以下なのに対し、会議室の半数近くが5名以上を収容できる広さになっている。これでは会議スペースの利用効率が悪く、「会議室が足りない」という誤った印象を与えてしまう。つまり、柔軟な使い方ができる小さめの会議室が満室になる一方で、大きい会議室には空きが多いというミスマッチが起こっているのだ。
この問題をさらに深刻化させているのが、いわゆる「ゴースト会議」、予約した会議室が使われていないという現象だ。2024年のデータでは、2~11名用の会議室の空予約率が12~17.6%に上り、従業員が「見かけの会議室不足」に対する不満を抱く一因となっている。ハイブリッドワークが定着して以来、会議は時間が短縮され、自発的に開催されるようになり、1対1やオンラインで行われる場合が多くなった。しかし、会議に使われているインフラの大半は、いまだに柔軟性に欠ける旧来のモデルに縛られている。
解決策は、規模の最適化とバランスの調整にある。つまり、広い会議室を分割したり、電話ブースの数を増やしたり、さまざまなフォーマットに対応できるオフィス家具を導入したりといった取り組みだ。適切なデータがあれば、企業はより効果的なレイアウトを考案し、習慣ではなく実際のニーズを満たすオフィスを実現できるだろう。

地域・業界で異なるオフィスの利用実態
オフィス利用の習慣に関して、注目すべき点は“地域差”にもある。VergeSenseのデータによれば、出社の頻度だけでなく、規則性や行動も地域により大きく異なる。オフィス利用率がもっとも安定しているのはアジア太平洋地域で、1年の大半を通じて平均10.8~11.6%で推移している一方、北米では平均利用率が7.6%にとどまり、数値は週ごとに大きく変動している。
このデータは、オフィスにおける人々の行動が、社会背景や状況によって左右されることを示す。アジア太平洋地域では週5日出社が主流だが、それとは対照的に、北米および欧州・中東・アフリカの一部では、ハイブリッドな働き方を採用する企業が多く、出社率は週の半ばでピークを迎え、週末前後の月曜と金曜に大きく落ち込む。たとえば、北米のオフィス利用率は金曜が3.1%と低い。それに対して、アジア太平洋地域では月曜でも8%にとどまっている。
同様に、業界によってオフィスの利用法にも違いがあるようだ。金融サービスが、平均利用率トップの11.7%を記録しているが、これは週4日出社体制によるところが大きい。対照的なのが官公庁や教育機関で、オフィス利用率は平均4.9%と低く、リモート優先であることがうかがえる。このデータのばらつきを見ると、オフィス設計を成功に導くには、機能だけでなくさまざまな条件も考慮する必要があることを教えてくれる。

データ主導で“出社しがいのある”オフィスに
今やオフィス戦略は、単なる推測ではなく、リアルタイムのデータをもとに策定されるようになった。VergeSenseの指数が示すように、ハイブリッドワークでは、その勤務モデルの複雑さから、出勤状況の把握や直感的なデザイン以上の対応が求められる。必要なのは、人々の実際の行動ややり取り、働き方の情報を常に収集しながら、継続的なフィードバックのループ(行動や結果から得られた情報をもとに、次の行動を調整・改善するプロセスを繰り返すサイクル)を回すことだ。
最近では、オキュパンシー・インテリジェンス・プラットフォーム(Occupancy Intelligence Platform)という新しいサービスが、このプロセスの中心的な役割を担っている。組織の意思決定を支援するこのシステムは、さまざまな場所の施設の利用状況(活発なものからそうでないものまで)を把握して、特定のパターンや非効率性を検出し、俊敏に対応することを可能にした。そのため、オフィスの運用担当チームは、数年ごとに設計を一からやり直すのではなく、リアルタイムで人々の行動を観察しながら、少しずつ戦略的に環境整備を進めることができる。たとえば、大会議室の分割や十分に使われていないスペースの見直し、季節ごとのニーズに合わせた設備・アメニティの調整などだ。
重要なのは、スペースの節約ではなく体験価値の向上。AIツールの成熟によって、オフィスはより予測やそれへの対応がしやすいものとなり、これからは稼働率やニーズに応じて調整されるようになるだろう。その場合、データはインフラの一部に組み込まれ、オフィス利用者と同様に、適応力の高いオフィスの基盤として機能する。
今、企業の幹部たちが直面している問題は、もはや従業員がオフィスに戻ってくるかどうかではなく、オフィスが従業員のニーズにしっかり応えられるかどうか。“インテリジェント・インフラ”を導入することで、企業は新たな働き方を支援しながら、変化に柔軟に対応できる“出社しがいのある”環境を構築できるようになるだろう。
ガブリエラ・ビアルコウスカ氏は、WORKTECH Academy所属の研究者/ライター。前職ではThe Future LaboratoryのアナリストおよびAIの専門家として、Creative Foresight(創造的な未来洞察)分野の経験を積んだ。
※本記事は、Worker’s Resortが提携しているWORKTECH Academyの記事「From occupancy to opportunity: bridging the gap between space and behaviour at work」を翻訳したものです。