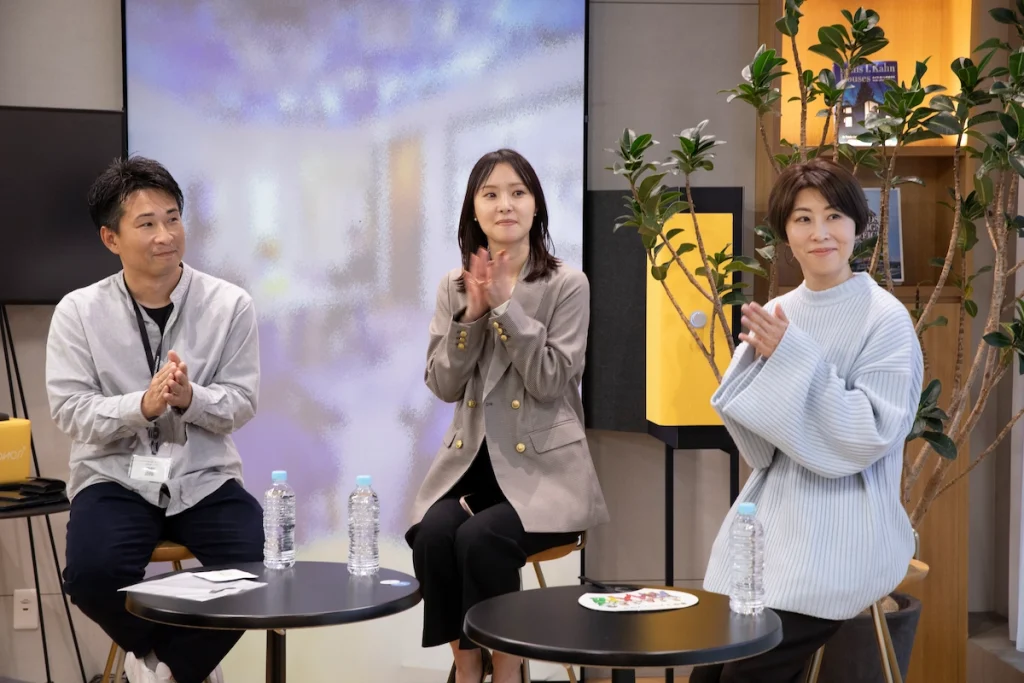イルカとの対話を目指して半世紀。海洋生物学者・村山司先生に聞く、コミュニケーションの本質

海や川に生息する哺乳類、イルカ。コミュニケーション能力や身体機能に優れた彼らは、クリックスやホイッスルと呼ばれる音を出して周囲を探ったり、仲間と高度なコミュニケーションを図り、連携して狩りをしたりするなど、社会性を持つことでも知られています。
そんなイルカと「話す」ことを夢見て50年。今も水族館のイルカを相棒に研究を続ける、東海大学海洋学部教授の村山司先生に、イルカが持つ知性や賢さについて伺いました。「怒ったり開き直ったり、人と似ているところが多い」というイルカの生態には、企業で働く私たちが、人とのコミュニケーションやチームワークを考える上でのヒントが隠されているようです。
Culture, Style
-

村山 司/むらやま つかさ
東海大学 海洋学部 教授
東海大学 海洋科学博物館 館長
1960年生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科修了、博士(農学)。水族館や動物園で飼育されている海獣類(鯨類、鰭脚類、海牛類、ラッコ、ホッキョクグマ)やコツメカワウソ、ペンギンなどを対象に行動実験によって感覚や知能などについて研究している。日本で最初のイルカの認知研究者。海の動物を研究しているが、船に弱い。主な著書は『海に還った哺乳類 イルカのふしぎ』(講談社)、『イルカ』(中央公論新社)、『イルカと心は通じるか』(新潮社)、『シャチ学』(東海教育研究所)ほか。
イルカと話をしたい。その思いで50年

──イルカとの「対話」を目指して長年研究を続けてこられている村山先生に、イルカについて教えていただきます。まず初めにお伺いしたいのですが、イルカというのは俗称だそうですね?
村山 その通りです。「イルカ」は便宜的な名称に過ぎません。海や川にいる哺乳類で、一般的にイルカやクジラと呼ばれるものは「鯨偶蹄目(くじらぐうていもく)」に分類されます。鯨偶蹄目は、口の中に髭板(ひげいた)と呼ばれるものが生えている「ヒゲクジラ亜目(類)」と、歯が生えている「ハクジラ亜目(類)」の大きく2つに分かれます。ハクジラ類のなかで体長4〜5メートル程度の小さなものを一般に「イルカ」と呼んでいます。
──そんなイルカの研究を先生が始められたきっかけは、高校時代に観た映画だったとか。
村山 はい、1974年に日本公開された『イルカの日』という映画ですね。言葉を覚えたイルカが大統領の暗殺に利用されてしまうというSF的な作品で、研究者がイルカと会話を交わすというシーンに衝撃を受けました。「そうか! 研究すればイルカと話せるんだ」って。私は当時16歳で、それからほぼ半世紀、「イルカと話したい」という思いを持ち続けていることになります。
──研究はどこまで進んでいるのですか?
村山 名詞を覚えさせるところまでは到達しました。今は動詞を覚えさせているのですが、ここで時間がかかっています。基本的に名詞はモノについている名称なので、イルカにも理解しやすいのです。たとえば、物体を見せて、それが「フィン」と呼ばれるものだということは示せますよね。一方、動詞の場合、自分自身がしている行動や動作を言葉や記号で表すことになるので、ピンとこないようです。
それに、イルカが人の言葉を理解したら何かにタッチ(選んで)して正解・不正解を判別、というだけでは面白くありませんよね? モノ(名詞)や行動(動詞)を覚え、たとえば「餌/ほしい」「ボール/遊ぶ」とか、文章表現でイルカの方から何らかの意思を伝えてこられるようになるのが目標です。
また、イルカは人と似ているところがあって、実験をし過ぎると飽きたり、ときには開き直ったりすることもあります。たとえば、どちらの記号を選んでも餌をあげないというような実験もあるのですが、その記号が出ると餌をもらえないと知っているイルカは、「どうせもらえないんでしょ!」とばかりに、わざとこちらに水がかかるような行動をしながら答えを選ぶのです。

──それは「感情のやりとりができている」ということでしょうか?
村山 そうだと思います。ちなみに、私のことを嫌っているイルカもいます(笑)。30年前から実験を行っている鴨川シーワールドで飼育されているナックという名前のシロイルカは、ほかのトレーナーが「おいで」と言うと来るのに、私が言っても全然来ません。しつこく言っていると、口を開けたままズブズブと水に沈んで、口に溜めた水を思いっきりかけてくることもあります。
ナックの実験では動物に接するのはトレーナーで、私は横で見ているだけ。ですから私を、「餌もくれないし、遊んでもくれない。何もしてくれないのに、この人が居ると面倒なことをやらされる」と認識しているのかもしれません。ただ、「その他大勢」ではなく「嫌いな人」と認識してくれているわけだから、私はむしろ嬉しいですね(笑)。
イルカのコミュニケーション能力と社会性

──イルカのコミュニケーションに関して、もう少し詳しく教えてください。
村山 私たちの実験では、イルカのコミュニケーションの一端を実証しました。目隠しをしていないナックと目隠しをしたデュークという名のイルカの2頭による実験です。ナックに「回転しなさい」と指示を出すと、目が見えていないはずのデュークも回転するのか? というものでした。結果としてデュークも回転しました。
この実験から判明したのは、ナックがこちらからの指示をデュークに音で伝えていたということ。さらに、違う指示の場合、たとえば「逆立ちをしなさい」であれば、「回転しなさい」とは異なる音をナックがデュークに出していたことも明らかとなりました。
これは訓練をしたわけではなく、2頭が自らやったことです。さらに興味深いのは、生存とは関係のないコミュニケーションであるということ。野生下であれば、「餌がある」「敵が来た」など、生きていくのに必要なコミュニケーションをしているはずですが、回転も逆立ちも生存とは関係ありませんよね。
──生存に関わらないコミュニケーションに賢さを感じますね。
村山 群れをつくっているうちに、そうした賢さや行動が培われてきたのだと考えられます。1頭だけではできないことが2頭だとできる。それが5頭、10頭ともなれば、できることがさらに増えます。社会性が先か、脳が先かという議論はありますが、社会性を持つイルカには脳の発達が見てとれます。群れをつくる種でも、サンマやイワシが「遊んでいる」ところを見たことがありませんから。
社会性と脳の大きさは密接に関係しているはずです。“余裕”を持てる脳があるからこそ「遊び」が生まれるのでしょう。ですからイルカは、実験にも遊びの要素を感じているのかもしれません。少し複雑なことを考えなくてはいけないので、一時的にはストレスになるかもしれませんが、成功すればリターンがあるというエンターテインメント性や達成感のようなものが彼らの学習意欲を高めている可能性があります。
成長の源泉は、“心の余裕”と“好奇心”
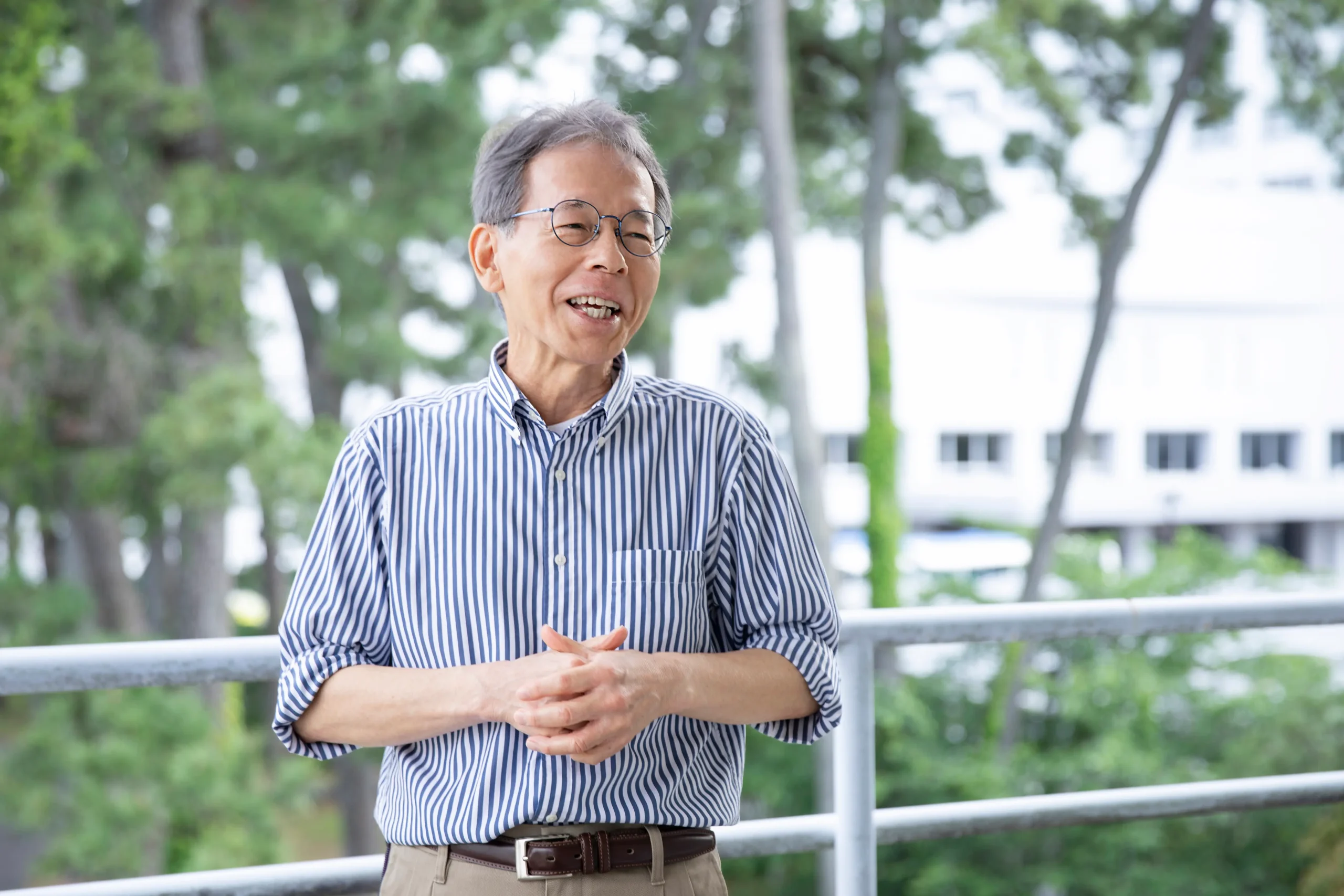
──そのようなイルカから人が学ぶべきものがあるとすれば、どのようなことでしょうか?
村山 イルカには、人と同じように内面の個体差があります。コミュニケーションが苦手な個体もいれば、イルカ同士だけではなく、人ともコミュニケーションをとる個体もいます。ナックがその好例ですね。ナックの場合、さらに勉強好きで好奇心旺盛でもあります。好奇心があるイルカは、「次は何?」「次は何?」とどんどん学習します。
そこから私が考えるのは、好奇心がないと何も進まないということ。ヒトやそのほかの動物が進化に適応してきた過程でも、好奇心は重要な要素だったのではないでしょうか。私自身、長らく研究を続けてきましたが、好奇心を持って挑戦すれば結果的に良い方向に転がることが少なくありませんでした。仮に最初は失敗したとしても、次の手に移りやすくなります。
──私たちは、好奇心を持って働ける環境をつくるためにどのようことを意識すべきでしょうか?
村山 「心に余裕を持てる」環境をつくりだすことだと思います。イルカの実験や訓練でも、余裕を与えないと何もやらなくなります。途中の息抜きや気分転換などがとても大事ですね。エサを与えれば動くのかというと、実は、そうではありません。余裕の持てる環境をつくりだしてこそ、覚えたことも忘れないし、やる気も見せてくれます。そのため、たとえば水族館では、イルカの水槽に遊び道具を入れたり、エサを取る際に一工夫必要な仕組みにしたりと、メンタルヘルスにつながる取り組みを積極的に取り入れています。
私たちヒトも、どこかに余裕を持った働き方をしないと、心が壊れていくし、やる気もなくなっていきますよね。たとえば企業において、従業員の積極性や生産性、そして長期的なエンゲージメントを維持するためには、この“心の余裕”をいかに創造するかが極めて重要になると思います。そのために求められているものは何か? 物理的な環境なのか、柔軟な制度なのか、企業カルチャーなのか……一人ひとりが自らの好奇心を追求しながら健全な状態で働き続けられるような、余裕を見つけ出せる環境を整えていくことが大事ではないでしょうか。動物を通した研究は、そんなことを私たちに教えてくれる気がします。
- 連載「生き物たちのワークとライフ」のその他の記事はこちら