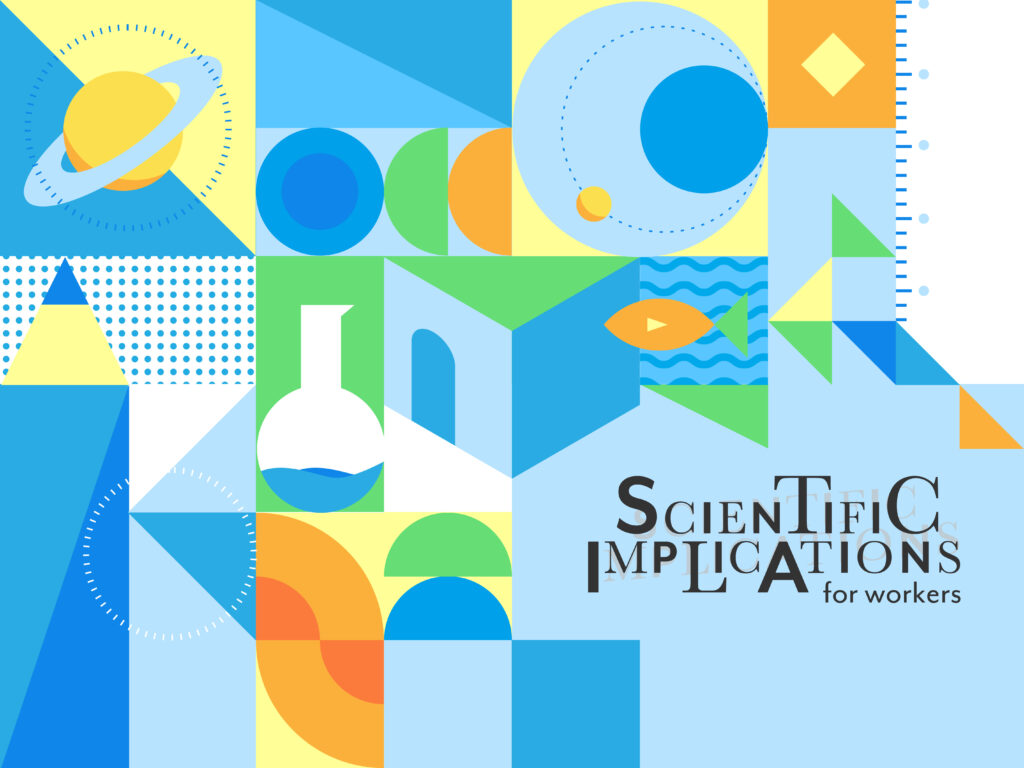本質からズレている? ABWとは、働き方を自由に“選ぶ力”を育てること

ABW(Activity Based Working)とは何か──。コロナ禍でリモートワークが加速度的に普及するなどし、ABWという言葉を耳にする機会が増えた。実際に導入に踏み切った企業も少なくない。ただ、ABWでワーカーの働き方はアップデートされたのか。あるいは、企業の生産性は上がったのか。そもそも、ABWの理念や本質はしっかり理解されているのか。
本連載では、ABWの創始者である、オランダ発のグローバルな働き方コンサルティングファーム・Veldhoen + Company社の岸田祥子氏、生駒一将氏に、ABWの理念から実践、展望まで、国内外で最もホットな話題を全6回にわたって提供してもらう。第1回のテーマは「ABWの本質」。
Facility, Design, Culture
-

岸田 祥子/きしだ しょうこ
株式会社ヴェルデホーエンカンパニー カントリーマネージャー/シニアコンサルタント
奈良県出身。京都工芸繊維大学大学院にてオフィス環境と知識創造に関する研究に取り組む。卒業後、オフィス家具メーカーに勤務。2019年にVeldhoen+Companyへ入社し、日本初のABWプロジェクトに参画。以降、製造業を中心にABW導入を支援するプロジェクトに多数関与。ABWという新しい働き方を、組織の働き方や文化を尊重したうえで定着させるための導入プロセス設計やチェンジマネジメントが専門。 -

生駒 一将/いこま かずまさ
株式会社ヴェルデホーエンカンパニー コンテンツマネージャー
サンフランシスコでのオフィスマネージャー経験を経て、日本国内でオフィス・働き方領域のコンサルティングに従事。現在は、欧州の先進企業への視察や最新トレンドを取り上げたセミナー・イベントの企画も行いながら、国内外の知見をもとに実践的なアプローチを発信している。同時にABWやハイブリッドワークの導入支援、チェンジマネジメントに関するトレーニングなどのサポートも担う。企業の働き方変革において「空間」「制度」「文化」をつなぐ視点を大切にし、理想論にとどまらない実行可能な変革を支援している。
ABWの理念に立ち返る
コロナ禍によって私たちの働き方は大きな転換点を迎えた。「毎日出社」という前提が崩れ、リモートワークの拡大によって「今日はどこで働くか」という問いが日常的な選択のひとつとなった。オフィスという存在の意味や役割もまた、あらためて見直されるようになっている。
一方で、「いつ働くか」という時間の柔軟性については、企業文化や制度面の制約もあり、思うようには浸透していないのが現状だ。こうした背景から、働き方の柔軟性は時間よりも空間、すなわち「働く場所」において先行して広がってきたと言える。リモートワークやサテライトオフィスの活用といった施策が浸透し、場所を選べる自由度は着実に整いつつある。
ただし、「何を目的にこの場所があるのか」「タスクに最適な環境とはどこか」といったオフィス空間の意図が、組織の中で十分に共有されているとは言いがたい。選べる環境は整ってきたものの、それをどう活用するかという働き方を“選ぶ力”については、まだ発展途上にあると言えるだろう。
私たちVeldhoen + Companyが35年にわたって提唱してきたActivity Based Working(以下、ABW)は、単なるオフィスのレイアウトや制度設計ではない。「どのように働くか」「なぜその場所を選ぶのか」といった問いを通じて、働く人の仕事に対する意識や行動そのものを変えていくことがその本質にある。環境や選択肢が整いつつある今だからこそ、このABWの理念にあらためて立ち返る必要があるのではないだろうか。
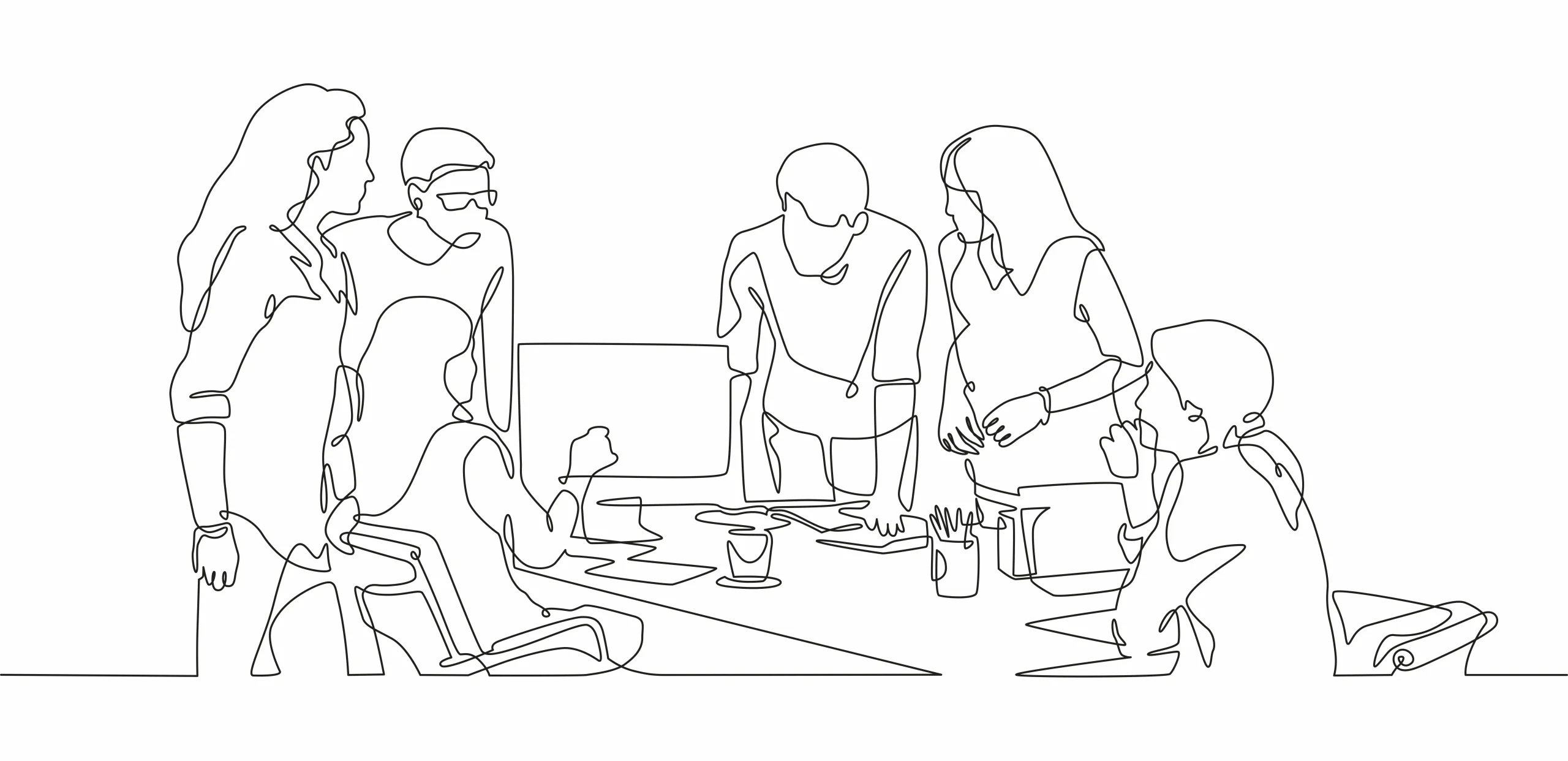
空間だけ変えても働き方は変わらない
ABWとは、業務(=Activity)に応じて働く場所や時間を自律的に選び、パフォーマンスを最大化する働き方である。単なる場所の選択肢を提供するという空間デザインのトレンドではなく、①働く空間、②IT環境、そして③働く人の意識と行動──の3つの側面から変化を促す統合的な企業戦略であり、組織文化の醸成にもつながる変革のアプローチと言える。
中でも特に重要なのが「行動の変化」である。従業員一人ひとりが自身の業務と向き合い、最もパフォーマンスを発揮できる環境を自ら選択できるようになることが、ABWの核心だ。つまり、ABWの中心にはあるのは「自由に働ける環境を整えること」ではなく、「働き方を自由に選ぶ力を育てること」である。
その点において、「私たちは何を実現するために行動を変えるのか」という問いに対して、明確な答えを持つことが欠かせない。組織が目指す理想の状態や働き方のゴールによっては、ABWがその手段として必ずしも最適であるとは限らない。導入ありきではなく、「私たちは何のためにABWを採用するのか」という問いから出発することが重要である。
しかしながら、2020年代の日本におけるABW導入の多くは、Activity Based “Workplace(≠Working)”、すなわちオフィスの物理的な側面に偏って語られてきたのが実情だ。「バラエティのあるオフィス家具のレイアウト」「集中ブースの設置」「電話ブースの拡充」といった空間施策ばかりが取り上げられ、「ABW=おしゃれなオフィス」や「ABW=フリーアドレス」といった誤解を招いたことは否めない。
忘れてはならないのは、ABWが本来目指すのはオフィスレイアウトの刷新ではなく、「働き方そのものの見直し」であるという点だ。たとえば、自由に席を選べる環境が整っていても結局いつも同じ席に座り続けてしまう──これはフリーアドレス導入時にも見られた典型的な課題であり、ハイブリッドワーク時代の在宅勤務も含む「最適な場所を選ぶ」ことへの意識変容が伴わなければ、いかに物理的環境を整備してもABWとは言えない。

フリーアドレスでは実現できない、ABWの本質
ABWが持つ「業務の目的に基づく選択」という視点は、空間を画一的に整えるだけのフリーアドレスとは本質的に異なる。フリーアドレスは面積削減や部署間の交流といった企業側の利点が強調されやすい一方で、従業員にとっての意義やメリットが曖昧になることも少なくない。
ABWの本質は、「従業員が自身の業務に最も適した時間・場所を理解し、自ら選び、その選択を日々の行動に反映させていく」というサイクルにある。その選択と実行の積み重ねが組織の柔軟性や生産性を高め、最終的には人的資本経営の推進にもつながっていく。だからこそ、ABWを通じて何を実現したいのかというゴールを、経営と現場であらかじめ共有し、働き方に対する共通の目的意識を持つことが不可欠である。
ABW実践の重要ポイント
ではここまでで記載してきたような本質的なABWの実践にむけて、重要なポイントはどこなのか、この記事では立場ごとに初めに持つべき視点やアクションを挙げておきたい。
オフィスマネージャー・働き方改革担当者向け:ワーカーの行動変容につながっているか
プロジェクトを推進する立場にあるオフィスマネージャーや働き方改革の担当者は、「ABW=オフィスの運用スタイル」と捉えてしまわないように注意が必要だ。
ABWの実践においてまず重要なのは、「オフィス空間の整備」と「行動変容」を同時に捉える視点だ。単に場所を用意するだけでは十分とは言えず、「その空間が意図する行動を促す設計になっているか」「期待する行動が組織に根付いているか」を問い直す必要がある。仮に、まだ定着していない行動を促したいのであれば、それを自ら選べるようになるための行動変容を支える仕組みや働きかけが求められる。
そうした意味で、プロジェクト初期において担当者が陥りがちなのは、空間の完成イメージには関心が集まる一方で、実際の運用フェーズに対する想像が置き去りになりやすいという点である。オフィスレイアウトの図面やパースなどのビジュアルは理解・共有しやすいが、「その空間が本当に意図通りに使われるのか」という行動面の問いに目を向けることは簡単ではない。
「リフレッシュスペースが使われない」や「集中スペースが電話の音でかえってストレス源になってしまう」といったケースは珍しくない。それぞれの活動が自社の企業文化の中で選べる状態にあるのか、またその活動を選ぶ力を育てていけるか、という問いに向き合う姿勢がプロジェクトの初期から求められる。
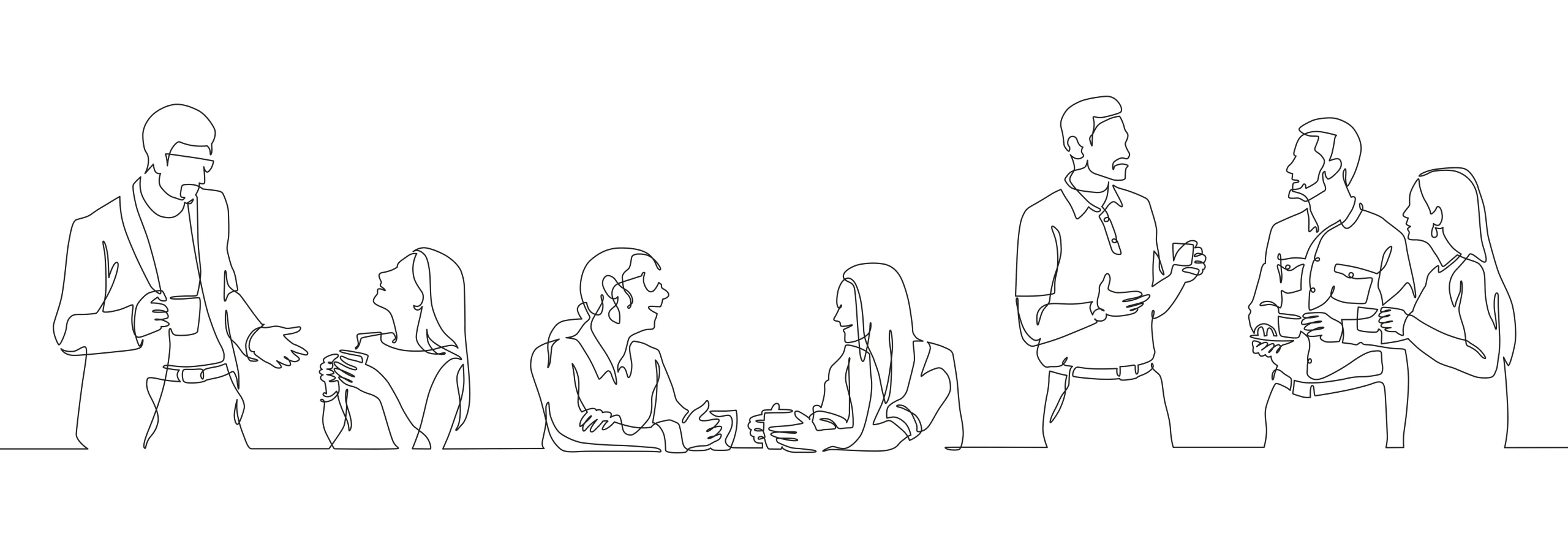
経営層向け:ABWは競争力強化につながる経営戦略
経営層においても同様に、ABWを単なるオフィスのアップデートと認識することからの脱却が重要である。ABWは、従業員の自律的な行動を引き出すことで、業務効率やエンゲージメントを高め、最終的には企業の競争力強化につながる経営戦略である。その実現に向けては、まず経営層自身がプロジェクトに主体的に関与し、変革の意思を示すことが出発点となる。
また“選ぶ力”の育成には、空間だけでなく制度やITといった複数の視点からのアプローチが必要であり、情報システム部門や人事部門などを巻き込んだ広い視点を持った組織体制づくりを経営層が後押しすることが欠かせない。そして、ABWを通じて何を実現したいのかという目的を明確にし、そのメッセージを従業員と共有していくこともまた、共通認識を築くうえでの重要な第一のステップとなる。
ABWとは一部門の取り組みでは完結しない。全社的な視点で、「空間・行動・制度・テクノロジー」のすべてを連動させる必要があるのだ。

“深い理解”と“定着”が次なる課題
ABWが真に目指すのは、「自由に働ける環境」の整備ではなく、「自由に選ぶ力」を育てることにある。自分の仕事を理解し、最適な時間と場所を選び、それを行動に移す──このサイクルが組織全体に根付いてこそ、ABWは本来の力を発揮する。
日本でもABWという言葉が広まりつつある今、その思想をどれだけ深く理解し、現場に定着させていけるかが次なる課題である。そして、その理解をより確かなものにするためには、ABWが生まれた欧州をはじめとする海外の実践や文化的背景から学ぶ姿勢も欠かせない。ABWはどのような価値観や制度のもとで発展してきたのか。空間や制度だけでなく、人々の意識や行動がどのように変化してきたのか。こうした視点を持つことは、ABWを形式的な導入だけで終わらせないためのヒントになるだろう。
日本は今、ABWの次のフェーズをどのように設計していくかを考えるべきタイミングに差しかかっている。Veldhoen + Companyでは、こうしたグローバルでの知見や経験をもとに、常にABWの最新動向を追いながら、日本の文化や組織特性に即した形での導入支援を行っている。
世界では今、働くという行為がどう再定義されているのか。そして私たちは、どのようにそれを自分たちの文脈に取り込んでいくべきなのか──本連載を通じ、そんな問いを一緒に考えていきたい。次回は、そうした国際的な視点から見えてきたABWのトレンドや、その実践から得られるヒントを掘り下げていく予定だ。

- 連載「ABW再考」のその他の記事はこちら