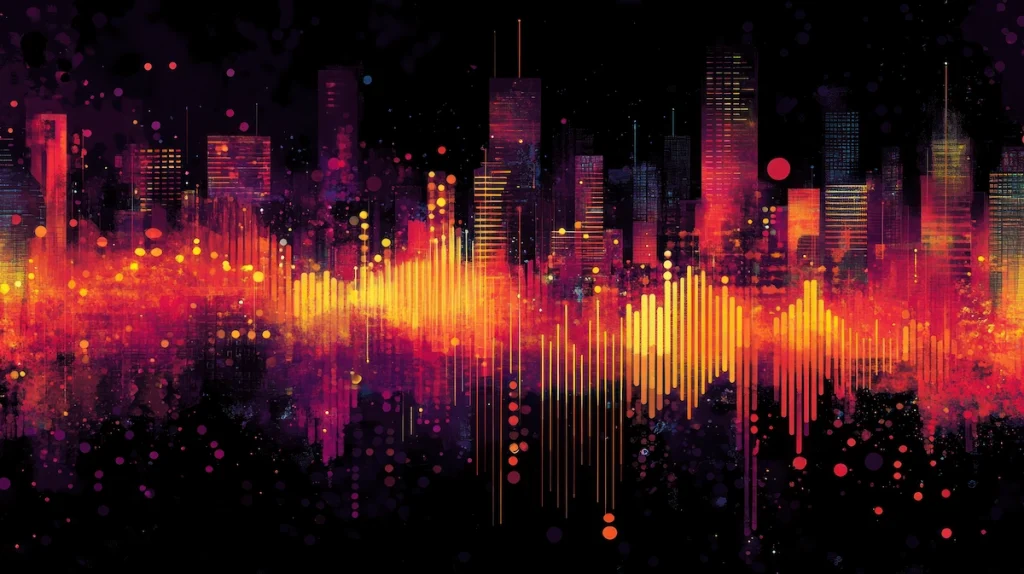ABW発祥の地・オランダに学ぶ、ハイブリッドワーク時代の働き方

ABW(Activity Based Working)とは何か──。コロナ禍でリモートワークが加速度的に普及するなどし、ABWという言葉を耳にする機会が増えた。実際に導入に踏み切った企業も少なくない。ただ、ABWでワーカーの働き方はアップデートされたのか。あるいは、企業の生産性は上がったのか。そもそも、ABWの理念や本質はしっかり理解されているのか。
本連載では、ABWの創始者である、オランダ発のグローバルな働き方コンサルティングファーム・Veldhoen + Company社の岸田祥子氏、生駒一将氏に、ABWの理念から実践、展望まで、国内外で最もホットな話題を全6回にわたって提供してもらう。第2回のテーマは「発祥の地・オランダに学ぶABW」。
Facility, Design, Culture, Style
-

岸田 祥子/きしだ しょうこ
株式会社ヴェルデホーエンカンパニー カントリーマネージャー/シニアコンサルタント
奈良県出身。京都工芸繊維大学大学院にてオフィス環境と知識創造に関する研究に取り組む。卒業後、オフィス家具メーカーに勤務。2019年にVeldhoen+Companyへ入社し、日本初のABWプロジェクトに参画。以降、製造業を中心にABW導入を支援するプロジェクトに多数関与。ABWという新しい働き方を、組織の働き方や文化を尊重したうえで定着させるための導入プロセス設計やチェンジマネジメントが専門。 -

生駒 一将/いこま かずまさ
株式会社ヴェルデホーエンカンパニー コンテンツマネージャー
サンフランシスコでのオフィスマネージャー経験を経て、日本国内でオフィス・働き方領域のコンサルティングに従事。現在は、欧州の先進企業への視察や最新トレンドを取り上げたセミナー・イベントの企画も行いながら、国内外の知見をもとに実践的なアプローチを発信している。同時にABWやハイブリッドワークの導入支援、チェンジマネジメントに関するトレーニングなどのサポートも担う。企業の働き方変革において「空間」「制度」「文化」をつなぐ視点を大切にし、理想論にとどまらない実行可能な変革を支援している。
ABW発祥の地、オランダ・アムステルダムで現地企業の取り組みを体感して見えてきたのは、本質的なABWの考え方が社会に根付き、経営層から現場まで共通の理解が形成され、ハイブリッドワークの価値を最大化しているという事実だった。では、日本との違いはどこにあるのか。出社の価値があらためて問われる今、ハイブリッドワーク時代のABWはどうあるべきかという問いに向き合いたい。
個人を尊重する文化
まずは、ABWという働き方が生まれた背景を整理する。
オランダは1990年代に労使・政府が協調し、賃金抑制と雇用創出の両立による「オランダの奇跡(Dutch Miracle)」と呼ばれる経済的成功を経験した。パートタイム雇用を含む柔軟な働き方を拡大させ、女性や高齢者の労働参加が進み、社会全体で働き方の多様性を受け入れる文化が醸成された。こうした社会背景の中、ABWという働き方はInterpolis社への導入を契機に、信頼を基盤とした場所と時間を選ばない働き方として成立した。
働き方には文化的な特徴が大きく影響する。オランダはもともと自立性が尊重されるフラットな社会構造を持ち、率直でダイレクトなコミュニケーションの文化に根差す。ABWの根底には、日本とは対照的に、役割とタスクを明確化して業務や意図を言語化しながら個人の“活動(Activity)”を尊重する文化が流れている。

ハイブリッドワークは当たり前
コロナ禍を経た2025年のオランダでは、ハイブリッドワークは国の社会基盤となっている。2016年にはWet flexibel werken(フレキシブルワーク法)が成立し、労働者は雇用主に対して柔軟な働き方を要求できる制度がコロナ以前から整っていた。しかし、柔軟に働く権利が認められるにとどまり、やはり出社を前提とした働き方であったことは否めない。
これがコロナ禍を契機に大きく変わり、現在は週2~3日程度の出社が一般的になっている。これは従業員だけでなく経営層も例外ではない。ここに日本との違いがある。日本やアメリカの場合は、「出社してほしい会社(経営側)と在宅勤務をしたい従業員」という対立構造で語られることが多い。
一方で、欧州、特にオランダでは、経営層も含めてハイブリッドワークのメリットが社会全体で認知されている印象がある。それゆえに持続可能な社会基盤として機能し、会社として働く場所・時間の選択に関するルールやポリシーも現実的で無理がない。オフィスも「毎日来ないことが前提」の設計やデザインになっていることが印象的だった。

出社・在宅での活動を区分する
ABWはハイブリッドワークで働くうえで強力な基盤となる。なぜなら、ハイブリッドワークで効率的に働くためには、オフィスと在宅を行き来する生活の中で、「いつ・どこで・どんな活動を・どう行うか」を意識的に選ぶことが求められるからだ。これこそが“活動”を軸に働き方を計画するというABW(Activity Based Working)の根幹だ。
具体的には、出社日と在宅日のそれぞれに最適な活動を考え、計画することが重要になる。在宅の日は集中作業や資料作成を効率的に行い、出社日にはコミュニケーションやコラボレーションといった活動を優先する──といった具合に、タスクと最適な場所を合わせて自分の業務を計画することがポイントとなる。
私たちは家でもオフィスでも同じように働けることを求めてはいないだろうか。「出社時の活動」と「在宅時の活動」を区分して考えることができれば、それぞれの場所のメリットを享受できるというわけだ。

コミュニケーションを促す仕掛け
では、出社した際にはどのような活動(Activity)が期待されているのだろうか。やはり対面でのコミュニケーションが期待されているのは、オランダも日本も変わらない。しかしオランダでは以下のような、コミュニケーションという活動を増やす、あるいは円滑にするための具体的なサポートが充実している。
- 【飲食を共にする機会の創出】
いずれの企業にも充実したカフェテリアがあり、安価な食事が提供されている。昼食や定時後のアルコールを共にすることで、雑談やチーム間のつながりが生まれる。視察の際も意図的にチーム全員で集まって食事をしている光景を見かけることができた。 - 【明確なポリシー】
たとえば、オンラインオークションプラットフォームを手掛けるオランダのCatawiki社では、Ritual(慣例)と呼ばれる明確な働き方のポリシーがいくつか定められている。その1つが「オフィスではコミュニケーションが最優先」。個人の集中作業中であっても話しかけられたらそれを優先するようにというポリシーがあり、それが文化となっている。
コミュニケーションをはじめ、オフィスで期待した活動を促すには、オフィスの整備だけでなく、こうした具体的で明確な制度や仕組みが欠かせない。なぜなら、在宅で実施するよりもより効率的に、あるいはクリエイティブに意図した活動を実現できたという日々の経験が、ABWや出社に対する“信頼性”につながるからだ。

出社の体験価値を最大化する
視察をした多くの企業では「週2日の出社推奨+曜日の固定」というガイドラインが設定されていた。その理由は以下の通りである。
- 【ピーク管理】
オフィスが混雑しすぎると快適性や生産性が損なわれる。曜日を分散させることで混雑を回避する。 - 【出会いの確率を高める】
チーム単位で出社日をそろえることで、必要な相手に会える期待値をコントロールする。
つまり、偶然ではなく意図した活動が生まれるように企業が出社をコントロールしている。これによりオフィスに来ると、自分の計画・希望通りの活動、すなわち本質的なABWで働くことができる。話したい人と会える、使いたいと思っていた環境が使えるという基本的なニーズが満たされ、出社に対する信頼性が生まれる。そうすることで、オフィスでの従業員体験(エンプロイーエクスペリエンス)を満たし、出社意欲を高めている。「どんな活動をオフィスで行いたいのか」を事前に明確に計画しなければ、この実現は難しいだろう。

日本への問いかけ
日本では、徐々に出社回帰の動きが強まっている。
企業側からは「コミュニケーションを期待して」と語られるものの、期待したコミュニケーションが発生しているだろうか。それをサポートするポリシーや制度まで設計されているだろうか。
同時に従業員からは「会社ではうるさくて集中できない」といった不満の声も上がっている。ABWの観点で言えば「その集中作業はオフィスでする必要はあるのか」という問いかけが必要になるだろう。オフィスと家の使い分けはできているだろうか。
こうしたミスマッチが積み上がっていくと出社への信頼性は下がり、出社の意欲の低下につながる。これらは「出社に何を期待するのか」が具体化していない、あるいはサポートされていないからこそ起きる課題である。
今こそ必要なのは、出社という行動の裏にある“活動”に目を向けることではないか。次回は、ABWの核となる活動(Activity)の視点から、働き方を見直していく。

- 連載「ABW再考」のその他の記事はこちら