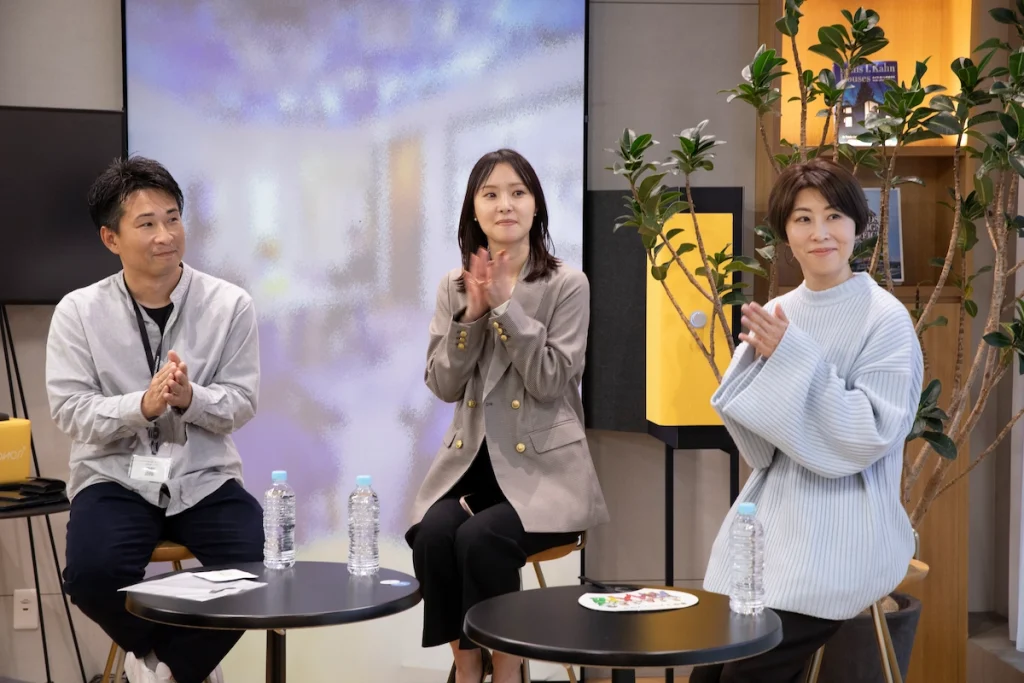理想の組織マネジメントは小学校から学ぶべき!? 映画監督・山崎エマさんが見た日本の教育と仕事力

「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている」。こう話すのは、ドキュメンタリー映画監督の山崎エマさん。山崎さんが手掛けた『小学校〜それは小さな社会〜』は2024年末から半年以上にわたってロングラン上映され、派生短編作が第97回アカデミー賞の短編ドキュメンタリー部門にノミネートされるなど、世界的な注目を集めています。
イギリスと日本にルーツを持ち、国際感覚に長けた山崎さん。日本の公教育に関心を寄せたきっかけは、映像編集者として暮らしたアメリカでの経験にありました。小学校での体験や学びが、日本人の働き方にどのような影響をもたらしているのか。山崎さんが感じた日米の働き方の違いや、教育と仕事観の関係についてお話を伺いました。
Culture, Style, Research Community
-

山崎 エマ/やまざき えま
ドキュメンタリー映画監督。神戸生まれ。19歳で渡米し、ニューヨーク大学映画制作学部を卒業。以降、映像編集に携わる傍ら、自らも監督として長編作品を製作。代表作に『モンキービジネス:おさるのジョージ著者の大冒険』、『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』などがある。日本人の心を持ちながら外国人の視点が理解できる立場を活かし、人間の葛藤や成功の姿を親密な距離で捉えるドキュメンタリー製作を目指す。
日々の生活や行事が生きた教材に。経験から学ぶ日本独自の教育の仕組み
――監督を務められた、映画『小学校~それは小さな社会~』(以下『小学校』)が、昨年の公開以降、話題となっています。
山崎 『小学校』は、世田谷区の公立小学校の1年間に密着したドキュメンタリー作品です。構想から公開までに10年を要し、撮影は150日間、約700時間に及びました。映画では1年生と6年生に焦点を当て、子どもたちの“日本人らしさ”が育まれていく学校での日々のやりとりや、教員の試行錯誤や葛藤を描いています。
私は日本人とイギリス人の両親を持ち、中学校でインターナショナルスクールに通うまで、大阪の公立小学校で6年間を過ごしました。大学ではニューヨークで映画製作を学び、卒業後も10年ほど映像編集の仕事に携わりました。アメリカで暮らしていた頃、時間を守ることや、仕事で困っている人を手伝うことなど、当たり前過ぎて意識すらしていないことを「エマはすごいね!」と何度も褒められたことがありました。
日本では当たり前の行動が、どうやらよその国では当たり前ではないらしい。私の習性はどこで身についたのかと過去を遡ると、どうも小学校での学びが関係しているのではないか。それも算数や国語といった教科学習ではなく、給食や掃除などの生活指導、学級活動や委員会、行事などの特別活動といった、日本式教育の影響が大きいのではないかと考えるようになり、『小学校』の製作に至りました。

――日本の小学校における生活指導や特別活動には、どのような特徴がありますか?
山崎 一番は、経験から学ぶことだと思います。学習指導要領で定められてはいるものの、教科書があるわけではないし、単元が確立されているわけでもない。校内で起こることすべてが、生きた教材なのです。
たとえば、自分の行動の結果やクラスメイトや先生の指摘などから気づきを得て、望ましい関係を築いていく。あるいは行事や係活動を通じて、体験したことのないものに挑戦し、時に壁にぶつかり、周りの励ましや応援を得ながら最後までやり切る。さらに、集団での活動を通じて、学校やクラスなど所属する社会の中での役割を認識し、貢献の喜びや自分の強みを見つけていく。このようなトライ&エラーの繰り返しが、生きていくうえで必要な力を育むだけでなく、自己を相対化する機会にもなっています。
こうした教育は日本独自のものであり、世界の教育現場でも類を見ないといいます。実際に映画を観た諸外国の方々は、「生活までが学校教育の範囲なのか」「6歳の子どもにまで役割を与え、責任を果たすことを教えるのか」といった驚きの反応を示しました。また、映画を撮る過程で、日本式教育を取り入れようとするエジプトの取り組みを取材する機会にも恵まれました。
日本にいると公教育の問題点ばかり指摘されますが、海外では良い意味で注目されているのです。私たちも、もっとフラットに物事を見ていくべきだと感じています。
任される範囲がまるで違う。アメリカと日本の仕事の進め方

――実際にアメリカや日本で働く中で、どのような違いを感じましたか?
山崎 私の経験で言うと、映像編集という職業に対する考え方も、仕事のアサインのされ方も、日米で大きく異なっていました。日本の映像編集職は、編集スタジオの機材を前に、すぐ隣にいる監督やプロデューサーの指示に従って映像を切ったり順番を並べ替えたりする、いわばオペレーターに近い役割が多いです。
一方アメリカでは、企画の説明と素材の受け渡しの後は、編集の裁量に任されることも多々あります。番組全体の構成をどうするか、どの場面をどれだけ使うかの判断は編集者の腕の見せ所。編集した映像を監督らに見せながら意図を説明し、「この人にフォーカスした画を撮って来てほしい」など、撮影の注文をつけることもあります。監督と編集の関係は、非常にフラットです。
働き方自体も大きく異なりました。たとえば、ニューヨークで90分のドキュメンタリー番組を編集した際は、半年ほどの製作期間がありました。そして1〜2週間ごとに行われる監督との打ち合わせに向けて、作業を進めます。その間の出退勤のサイクルや休みの取り方なども、編集者が自分で決めることができました。
しかし日本では、同規模の番組で与えられる期間は2〜3週間ほど。今でこそ働き方改革で改善されているでしょうが、当時は徹夜作業やスタジオでの寝泊まりが当たり前。何より監督やプロデューサーの都合に振り回され、自分の予定すら組むことができません。映像だけでなく、時間の使い方にもまったく裁量が与えられていないのが苦しかったですね。
――予算の差もあるかもしれませんが、かなり対照的ですね。
山崎 で、ここで考えるべきは、私が日本で受けた教育です。アメリカ流の働き方は、自由だけれども自律が問われます。この“律する”という部分で、自分は救われた気がするのです。
当時私は編集の仕事と並行して、個人のドキュメンタリー映画も製作していました。友人と3年間かけて製作した作品で、資料集めから撮影、編集まで、膨大な時間が必要でしたが、柔軟な働き方ができたおかげで「19時退勤・21時就寝・朝4時起きで自分の製作に集中」というリズムを確立し、仕事とやりたいことを両立できました。
加えて製作が佳境に入ると、土日に編集の仕事をする代わり、平日に連休を確保して撮影に臨むなどしていました。映画を撮っていることを知っている上司が、私に休暇を提案してくれたからできたことです。その上司はドキュメンタリー界隈では有名な方で、製作中にはプロジェクトの信頼性を上げるためにエグゼクティブプロデューサーに就いてくれました。
とはいえ上司も、部下なら誰彼構わず応援してくれるわけではありません。私が日々の業務で約束を守り仕事をやり抜いたり、相手の様子を伺いながら役に立てると思ったら手を挙げたりと、小さな成果と信頼を積み重ねてきたから機会に恵まれたのです。当時「エマはよく頑張るね」と周りに言われましたが、頑張りの基準が日本とアメリカでは違うのかなと感じました。
きっとアメリカの若者は、社会に出てから通用しないことを学び、そこから努力を重ねて成長していくケースも多いでしょう。一方で日本では、コツコツと努力することや困難を乗り越える経験、いわゆる勤勉さを学校生活を通じて自然と身につけているのではないかと思います。
組織力や人間力で勝負するなら、人との関わりから学ぶ必要がある

――もし日本に居続けていたら、今のようなご活躍はあったと思いますか?
山崎 そこなんですよね。日本での映像編集という職業は、クリエイティビティも働く時間も自由度の低い環境にあります。アメリカだと自身で編集した映像が評価され、ディレクターやプロデューサーへの道が開けるパターンが多いですが、日本だと操作が的確で早いなど、オペレーション面の評価にとどまってしまう懸念があります。そもそも日本でも働きながら自分の作品を撮ることを試みたこともありましたが、時間がないうえ心身も疲弊して「これは無理だ」と判断しました。
14歳で映像製作を始め、「この世界で生きていきたい」と思って渡米できたのは、中学以降、日本の公教育とは異なる環境で学んだからだと思います。もちろん、日本の教育が育む「規律・責任感・協調性・配慮」が、清潔で正確で細やかな日本の社会を築き上げているのでしょう。しかしその一方で、ムラ社会的な息苦しさや、将来に対して希望が持てず保守的になる若者が多い現状は、日本式教育の負の側面とも言えるかもしれません。
――『小学校』では、先生方の生徒への指導にも焦点を当てていました。あえて厳しく接して子どもが涙する場面や、宿題を提出しない生徒が複数人いるクラスへの指導も印象的でした。
山崎 先に断っておくと、撮影に協力してくれた小学校では主体性に重きを置き、子どもが自ら手を挙げて役割を担う姿勢を、とても大切にしていました。たとえば新2年生が入学式で新入生を迎える際、「喜びの歌」を演奏するのに大型楽器の奏者をオーディションで決めることなどです。そのうえで、子どもが朝や昼休みの自主練習に参加せず、楽譜を覚えてこないなど、代表としての自覚と行動が足りないと判断した生徒には、先生は厳しく注意していました。
ただし、厳しい指導のあとには必ず何かしらのフォローがありました。先生の間で学級や学年の垣根を越えて子どもの状況を都度共有し、叱った先生とは別の先生が励ますなど、役割分担を図っていました。また先生がクラス全体を注意した後は、生徒が問題をどう解決するか議論するなど、映画では泣く泣くカットしましたが、先生方は失敗を成長の機会に変える働きかけをしていたのです。

――その姿勢は、会社組織における部下の指導や育成の参考になりそうです。
山崎 この20年ほど、日本の教育現場では子どもの自己肯定感の低さが問題視されてきました。Z世代は「ありのままを認め、褒める」方針で育ってきましたが、上の世代には生ぬるく映る場面もあるでしょう。私自身も時に発破をかけられて奮起した世代なだけに、撮影中、歯がゆく感じる場面も目にしました。しかしそれは、誰が悪いということではありません。受けてきた教育が違うのだから、ギャップを感じて当然なのです。
そのうえで相手の性質を見極めて、褒めて伸ばすのか、厳しさでひと皮むける体験を課すのかが大事なのだと思います。そして上司は育成を一人で抱えず、周りの管理職や経験値の高い社員と情報をシェアし、協力し合いながら進めていく必要があるのでしょう。
日本はもともと資源に乏しいうえに、人口減少時代を迎えています。組織力や人間力で勝負するしかなく、他の国と同じやり方をなぞっても相対的な競争力は低下するばかりではないでしょうか。特にデジタル化が進む昨今、人と人との関わりの中で、人と共にいることでしか学べないことの価値は高まっていくに違いありません。
そうしたとき、これまで日本の公教育が大切にしてきた“教科外での学び”が評価されるのであれば、10年かけて映画をつくり上げてきた甲斐があるというものです。
本記事はリサーチコミュニティ会員限定記事です。
リサーチコミュニティとは、総務などオフィス運用やマネジメントに携わる人のみの会員制サービスです。
限定記事の閲覧のほか、各種特典もご用意しております。