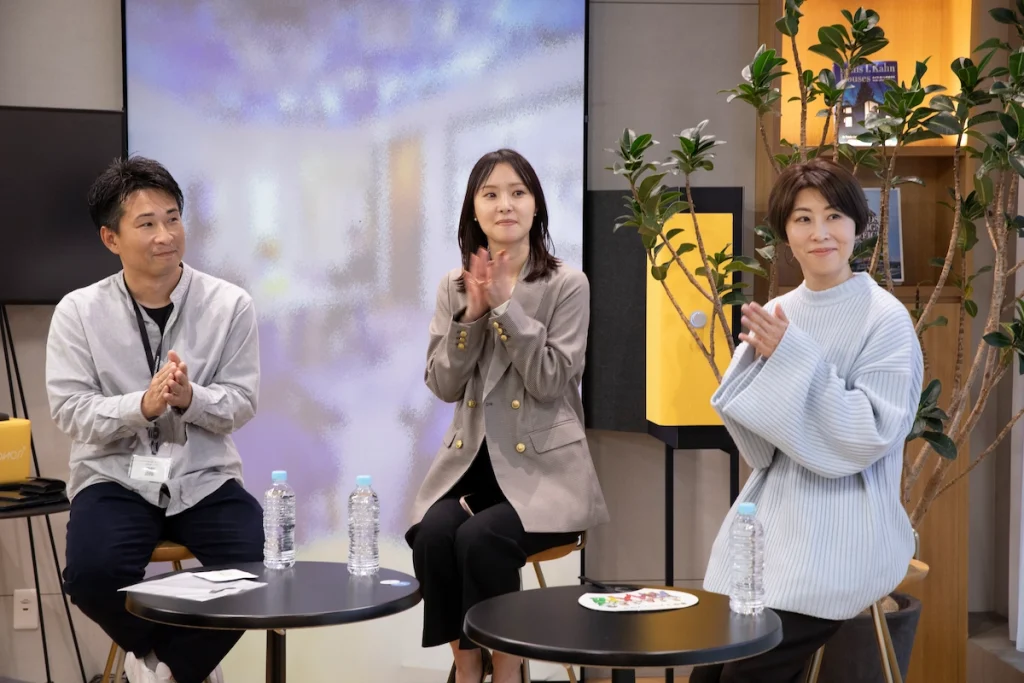【ブレインテック】脳とテクノロジーがつながる世界でどう働くのか? SF思考で問うブレインテック時代の最適解

私たちの思考や行動を司る“脳”がテクノロジーとつながる「ブレインテック」。この技術の発展によって、私たちの働き方は大きく変わる可能性があるといいます。ブレインテックの研究開発をリードする株式会社アラヤで、科学と社会の対話をデザインするサイエンスコミュニケーター・宮田龍さんのお話から、未来の働き方とオフィス、コミュニケーションのヒントを探ります。
Technology, Culture, Style
-

宮田 龍/みやた りゅう
株式会社アラヤ 研究開発部 サイエンスコミュニケーションチーム サイエンスコミュニケーター
九州大学大学院総合理工学府修了。日本科学未来館での科学コミュニケーター等の経験を経て現職。ブレイン・テックの社会実装に向け、科学と社会の対話から未来を共創するコミュニケーション活動を展開。内閣府ムーンショット目標1Internet of Brains におけるコミュニケーションプロジェクト「Neu World」のプロデューサーも務める。日本SF作家クラブ会員。
脳とテクノロジーを接続する「ブレインテック」の現在
──まずは、宮田さんが研究されている「ブレインテック」について教えてください。
宮田 ブレインテックとは、脳の活動を計測してさまざまな応用を目指す技術です。中核的な技術は「ブレイン・マシン・インターフェース(Brain Machine Interface/以下、BMI)」と呼ばれ、人間の脳とテクノロジーをつなぐ技術を幅広く指します。脳の活動や状態を計測し、そこから人間の意図を推定して、たとえば手を使わずにPCやロボットアームを操作するような応用が考えられます。

技術的には大きく「侵襲型」と「非侵襲型」に分けられ、侵襲型は手術で脳に直接電極などを取り付けて脳の活動を測るものです。非侵襲型は、頭皮の上から電極を貼り付けて測るもので、どちらも研究開発が進められています。
──活用のハードルは、非侵襲型のほうが低そうですね。
宮田 そうですね。ただ一方で、非侵襲型には、侵襲型に比べて精度が低くなるという課題があります。たとえば、私が今こうして話しているときにも顔の筋肉が動いているのがわかりますよね。そのときに出る電気信号と脳からの信号が混ざってしまうのです。
ただ、最近の研究によって、たくさんの人の脳の活動データを何百時間と大量に蓄積していくことで、非侵襲型でも精度が向上することがわかってきました。生成AIなどの分野で知られているスケーリング則(データを集めれば集めるほどAIの性能が上がること)が、ブレインテックの分野にもいえるということです。つまり、脳の活動データを測る人が増えるほど、できることも格段に増える可能性があります。
──デバイスの進歩だけでなく、データ解析技術の発展も追い風になっているのですね。現状、ブレインテックが実際に社会に応用されている例はあるのでしょうか?
宮田 応用が始まっているプロダクトという点では、医療分野と一般向けで状況が大きく異なります。医療分野では、たとえば、脳に磁気刺激を与える経頭蓋磁気刺激法(Transcranial Magnetic Stimulation/以下、TMS)という方法がうつ病などの治療に使われるようになっています。適用条件を満たせば保険適用の対象にもなり、社会実装が進んでいる例といえるでしょう。
一般向けの領域では、簡易的な脳波計をはじめとした商品化が始まっています。ただ、現状一般向けに流通しているブレインテックのなかには、できること以上の期待を持ってしまうようなマーケティングや、一部、科学的な効果検証が十分でないものが流通しているという課題もあります。その事実が一般の方に伝わらないまま製品が出回ってしまうことは、この分野の大きな課題のひとつだと考えています。また、プロダクトだけでなく、測定されたデータをどの範囲まで共有するのか、プライバシーは守られるのかといった、法律や倫理の問題も検討すべき課題ですね。
身体の制約から解放された、より自由な働き方へ

──応用への期待と、社会実装上の課題の両面があることがわかりました。こうした技術は、私たちの働き方をどのように変えていく可能性があるのでしょうか?
宮田 ひとつは、働いている人の状態のモニタリングとフィードバックです。「集中力が上がり、クリエイティブな仕事に最適なタイミングです」「集中力が下がり、眠くなってきています」といったフィードバックが得られるようになると、仕事の効率を高めたり、ドライバーや作業員の事故を未然に防いだりすることにつなげることができます。
──個人のそのときどきの状態に合わせて、仕事のやり方を最適化できそうですね。
宮田 そうですね。もうひとつ、大きな社会的インパクトをもたらすと期待されているのが、マイノリティとされている方々の社会参加を促進することです。たとえば、身体を動かすことが困難な方でも、脳の活動をもとに機械を操作できるようになれば、仕事の幅は大きく広がります。
私たちアラヤも参画している国が進める「ムーンショット型研究開発事業」では、BMIなどの技術を活用することで、身体や脳の制約から解放され、多様な形で労働や社会活動に参画できる社会を目指した研究開発も進められています。
──個人のパフォーマンス向上だけでなく、よりインクルーシブな働き方の実現にもつながるのですね。ムーンショット型研究開発事業で、すでに見えている研究成果はあるのでしょうか?
宮田 実際に、他の人には聞こえないくらいの声量でささやくだけでメール返信ができる方法が開発されています。生成AIが提案した返信文案のなかから、ささやきで選択するステップを経てメール返信ができるというもので、手が動かせない人や発話が困難な人にとって新たなコミュニケーションの選択肢になりえるでしょう。
──オフィスという場についてはどうでしょうか?
宮田 働く人の「快・不快」といった感情を脳の活動から測定できれば、その人の状態に合わせてオフィスの環境を調節できるのではないでしょうか。たとえば、脳の活動データに合わせて香りや照明、机の高さなどを変えるといったことが将来的に実現できる可能性があります。

また、アラヤの社内ラボ「Visionary Lab」では、脳の活動データに合わせて照明の色が変わるシステムを応用して、トランプゲームの「ババ抜き」を、相手の生理的情報をもとに戦う新しい“遊び”へと拡張させました。
相手の脳波の状態と連動して環境が変わるため、自分やメンバーの状態に気づきやすくなる環境の好例としてイメージしやすいと思います。どこまで可視化されるべきかの議論は必要ですが、こちらもコミュニケーションや働き方の改善に応用できる可能性がありますよね。
その技術は自社に必要か? SFが実現する対話の場づくり

──新しい働き方の提案にブレインテックの可能性がうかがえる一方で、先ほどの科学的な信憑性やデータ共有の話のように、技術の導入には慎重な議論が必要になりそうです。企業は今後、こうした新技術とどう向き合っていくべきだと考えますか?
宮田 「自分たちの会社にとって本当に必要なのか」という視点で見極めることが大切です。これは、日々社会実装が進む先端テクノロジーの多くで重なる話だと思います。まずは、安全性や倫理的な配慮はもちろんのこと、「その技術は本当に必要ですか?」「その技術を使って何を実現したいのですか?」が問われるべきです。新しい技術を導入せずとも、もっと簡単に低コストで課題解決できることもありえます。会社の文化や業態に照らして考える必要があり、そのために、組織内での対話が重要になるでしょう。
──とはいえ、新しい技術について意見を交わすのは難しいという側面もあるかと思います。
宮田 科学技術は、専門性がないと発言しにくいという風潮がありますから、その気持ちはわかります。また、コミュニケーション全般において自分の意見を述べるハードルは高く感じるものです。とはいえ、議論ができなければ何も進みません。最終的に自分たちの働き方や生活に関わってくることを、「知らなかった」「考えていなかった」では済みませんよね。
ではどうしたらよいのか? コミュニケーションの場を設計し、対話のコストを下げることが非常に大切です。そこで今、私が特に可能性を感じて取り組んでいるのが、「SF(サイエンスフィクション)」の力を借りるというものです。
──場の設計はまさにサイエンスコミュニケーターの力が必要とされる場面ですね。ぜひ具体的な事例を教えてください。
宮田 先ほど話したムーンショット型研究開発事業の一環で、「Neu World」というプロジェクトを推進しています。Webで公開するマンガや小説などのSF作品を通じて、ブレインテックの研究開発内容やビジョンを伝えつつ、社会でどのように活用していきたいかを多くの人々と対話しながら見出していくことを目指しています。

──なぜ、SFなのでしょうか?
宮田 SFのいいところは、未来の話をするときに、課題に焦点を当てやすくなるところです。現実の世界を踏まえながら話すと、実際の社会情勢や科学的な信憑性などに引っ張られて、想像の枷(かせ)になることがあります。その点、SFだと「人類は絶滅したが、ある条件に当てはまる人々だけは生き残った」といった極端な設定から始められるので、想像の幅が広がり、その先の問いや課題に焦点を当てて話しやすくなります。
技術と社会の関わりについて考えるときには、「自分はどうしたいか」と「他の人はどう感じるか」の両方を考えるのが大切になってきます。でも、他の人の気持ちや立場を正しく理解することは難しいですよね。SFであれば、登場人物の視点から世界を見やすいため、自分以外の状況を想像しやすくなります。登場人物の体験を通して、「この状況に置かれた人はこう選択した」「この立場の人は嫌だと感じた」などと考えることができます。
これは一種のロールプレイであり、多様な視点を持つための非常によい訓練になります。技術と社会の未来についてだけでなく、自分たちの組織や働き方について、想像や理解を深めることにも応用できるのではないでしょうか。
バックオフィスが秘める社内コミュニケーターの可能性

──未来についての対話の場をデザインすることは、ブレインテックなど先端技術の領域に限らず、たとえば組織の働き方について新しい制度や施策を導入するときの是非を検討する場面などでも重要になると思います。こうした対話の場をデザインする役割は、どのような人が担えると考えますか?
宮田 まず、利害関係者になる人たちのことをよく知っていて、コミュニケーションが取れることが大前提だと思っています。サイエンスコミュニケーターとしての私の場合、これまで研究者の方とたくさんお話する機会がありました。さらに、科学館の来場者やときには居酒屋で隣になった人など、科学の専門家ではない方々の考えもたくさん聞けてきたことも大きいですね。両方の立場をわかって、はじめて対話の場をつくれるわけですから。
そのような立場は、企業のバックオフィス、特に総務や人事の方々の立場に近いのではないかと思います。バックオフィスは、社内のさまざまな部署の方と関わる機会も多く、なおかつ情報が集まってくる場所ですよね。サイエンスコミュニケーションの仕事をしていても、0から1が生まれることはほとんどなくて、別の場所にあった何かと何かをつなぎ合わせたところに新しい価値が生まれると感じることが多くあります。そう考えると、コミュニケーションと情報が集まる場にこそクリエイティブなポテンシャルが秘められていて、実はバックオフィスにその可能性があふれているのではないでしょうか。
──情報が集まるハブになりえるバックオフィスの方々が、社内の対話をデザインする、いわばコミュニケーターの役割を担えるといえそうですね。
宮田 そうですね。加えて、私はよく「最先端の技術が全ての人の最適解ではない」と言うのですが、その技術とどう関わるかや、技術に対する価値観が違う人とどう接していくかについては、人それぞれに最適な距離感があるはずです。この「距離感の最適化」も、コミュニケーションに関わる立場として非常に重要な視点だと考えています。組織においても、そんな視点を持って対話を重ねていければいいですよね。