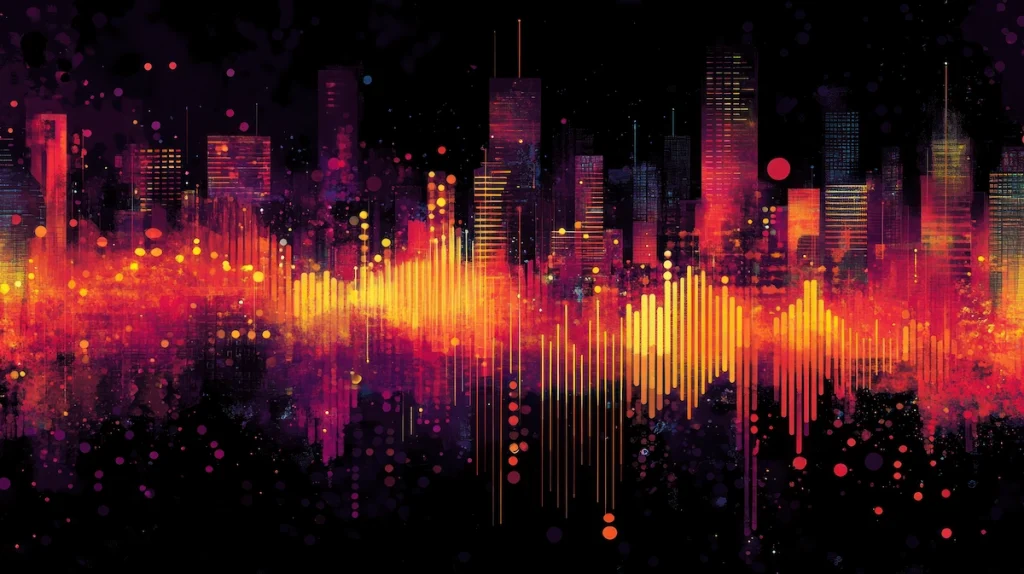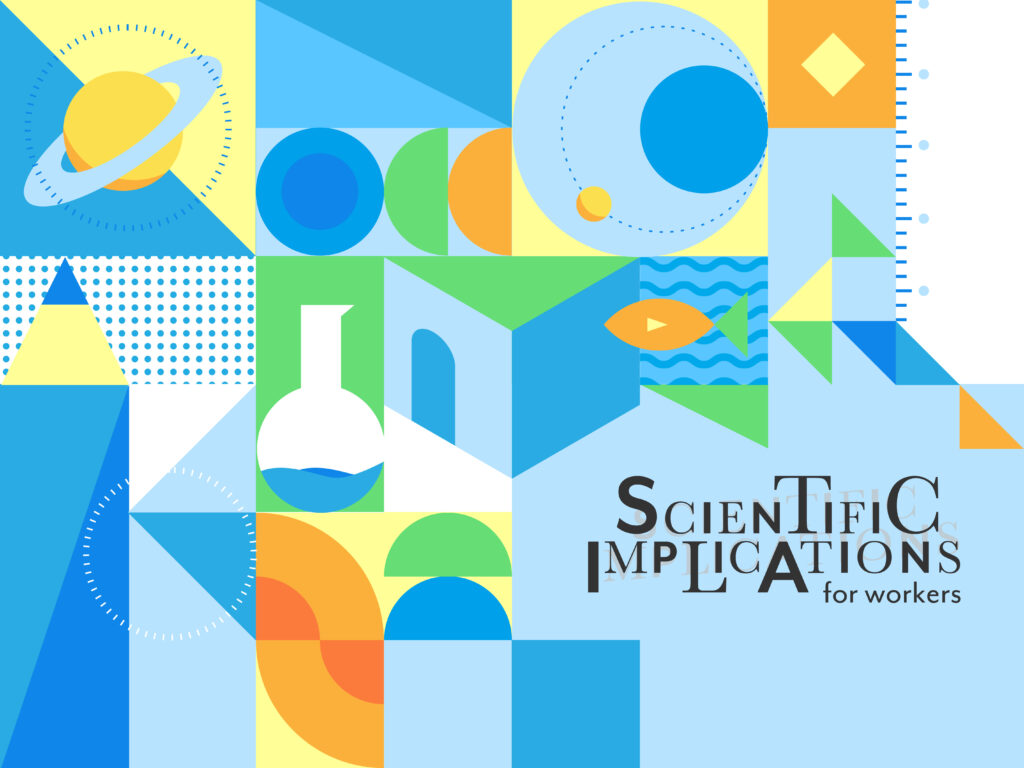働き方を“言語化”する。個と組織の活動を最大化する決め手

ABW(Activity Based Working)とは何か──。コロナ禍でリモートワークが加速度的に普及するなどし、ABWという言葉を耳にする機会が増えた。実際に導入に踏み切った企業も少なくない。ただ、ABWでワーカーの働き方はアップデートされたのか。あるいは、企業の生産性は上がったのか。そもそも、ABWの理念や本質はしっかり理解されているのか。
本連載では、ABWの創始者である、オランダ発のグローバルな働き方コンサルティングファーム・Veldhoen + Company社の岸田祥子氏、生駒一将氏に、ABWの理念から実践、展望まで、国内外で最もホットな話題を全6回にわたって提供してもらう。第3回のテーマは「ABWを機能させるカギ」。
Facility, Culture, Research Community
-

岸田 祥子/きしだ しょうこ
株式会社ヴェルデホーエンカンパニー カントリーマネージャー/シニアコンサルタント
奈良県出身。京都工芸繊維大学大学院にてオフィス環境と知識創造に関する研究に取り組む。卒業後、オフィス家具メーカーに勤務。2019年にVeldhoen+Companyへ入社し、日本初のABWプロジェクトに参画。以降、製造業を中心にABW導入を支援するプロジェクトに多数関与。ABWという新しい働き方を、組織の働き方や文化を尊重したうえで定着させるための導入プロセス設計やチェンジマネジメントが専門。
-

生駒 一将/いこま かずまさ
株式会社ヴェルデホーエンカンパニー コンテンツマネージャー
サンフランシスコでのオフィスマネージャー経験を経て、日本国内でオフィス・働き方領域のコンサルティングに従事。現在は、欧州の先進企業への視察や最新トレンドを取り上げたセミナー・イベントの企画も行いながら、国内外の知見をもとに実践的なアプローチを発信している。同時にABWやハイブリッドワークの導入支援、チェンジマネジメントに関するトレーニングなどのサポートも担う。企業の働き方変革において「空間」「制度」「文化」をつなぐ視点を大切にし、理想論にとどまらない実行可能な変革を支援している。
ABWの根幹にあるのは、個人が自分にとって必要な活動を選択し、その活動に集中するという働き方だ。これにより、それぞれの活動の質を向上させ、効率性や生産性を向上させていく。このように書くと、ABWは個人が自身の働き方を見直す、つまり仕事の活動を進化させていくという個人任せの働き方ではないかと感じるかもしれない。しかし、そうではない。一人ひとりが活動に集中できるようになるには、“組織”としての取り組みが必要となる。
そのカギは、「働き方の言語化」だ。
言語化①:業務の“共通言語”をつくる
「昨日ご自身がした仕事あるいはタスクを箇条書きで書き出してみてください」
これは私たちがワークショップやプレゼンの際によく投げかける最初の問いだ。「メール返信」「見積作成」「定例会議」など、さまざまなタスクが挙げられるでしょう。これは業種、職種あるいは役職によって多種多様で、一人ひとり異なる。ABWではこうしたタスクを「活動」に分類していく。

「次の定例会議はアイデア出しをしたいから、ブレストブースを使おう」「この見積作成は時間がかかるし、集中したいから午前中に在宅でまとめてやってしまおう」・・・・・・。
例えば、定例会議も日によって求められるアウトプットは異なるだろう。「見積作成」というタスクでも、人によっては集中作業かもしれないし、2人で作成することもあるかもしれない。同じタスクでも活動は異なる可能性がある。ABWではタスクの内容だけでなく、それを「どのように実施するか」を含めて活動に分類していく。
タスクを活動として捉えることの1つ目の意義は、個人の活動を内省する習慣を身につけられることだ。最適な場所と時間を選択して働こうとすることで、自ずと自分の日々の仕事を見直すことにつながる。タスクを活動として捉えることは慣れてしまえば難しくないのだが、定着には訓練が必要になる。しかしこれは個人の生産性向上につながる重要なステップだ。
2つ目の意義は、部署や職種を超えた“共通言語”をつくるためだ。この共通言語は、ABWという柔軟性の高い働き方で、オフィス空間とスケジュールを共有しながら組織として働くために欠かせない。
「次の会議のアジェンダはアイデア出しだ」という共通言語があれば、ホワイトボードやポストイットがあるような会議室を予約しておき、会議の前にマインドセットを準備しておくこともできる。

空間を用意するだけでは不十分
あなたのオフィスには集中のためのエリアやブースがあり、そこで集中して作業をしようとしているとしよう。こうした問題は起きていないだろうか。
- ◯大声での会話や電話の声で周囲の人が集中できない
◯同じ席を同じ従業員が毎日利用している
◯デスクの上に荷物だけが長時間放置されていて、席が使えない
フリーアドレスの一部に集中席を設けるなど、これらは席のみで対策した場合に起きがちな問題だ。その結果、「席が足りない」「集中できない」といった不満となり、結果的にオフィスの満足度が低下する。これらはオフィス環境の品質に起因するものではなく、うまく運用できていないことが原因である。この原因を見誤ると必要のないオフィスの改善を繰り返すことになってしまう。
言語化②:オフィスの“使い方”を明文化する
ABWで働く際に重要なのは、オフィスのルールやマナーの明文化だ。ABWは活動ごとにさまざまな空間があり、部署や世代を超えてより多くの従業員と共有して使うことになる。それぞれの空間は各活動をサポートするために意図をもって設計されていても、その意図が共有されなければ、組織として適切に運用することは難しい。異なるワーキングカルチャーを持つ人材が活動に集中して仕事をするためには、各空間の使い方を明文化する必要がある。
「2時間以上離席する際はクリーンデスクをすること」「集中スペースでは私語・通話禁止」「カフェスペースではオンライン会議可」など、空間ごとの使い方やマナーを明文化することで、どこでどんな活動をするべきなのか、あるいは期待されているのかがわかる。暗黙的なルールではさまざまな活動をサポートするオフィス空間の運用は困難だ。
空間や場の使い方を明文化することで、社員は自分に最適な場所を選びやすくなり、組織として活動を基盤に働くことが可能となる。

個人とチームの活動を両立させるには
空間ごとに明文化したマナーやルールを設定し集中できる環境は整った。その次に起こる課題は、以下のようなものだ。
- ◯作業に集中したいのにチャットの返信に追われる
◯作業が進み始めたと思ったら、会議の予定で作業を中断せざるを得ない
◯自分の作業をしようとすると、疲れていて集中できる状態ではない
ともすると、こうした課題は日常的に発生し、中にはそれが当たり前になっている人もいるかもしれない。こうした個人作業の非効率性の積み重ねが労働時間にも大きく影響を及ぼすという認識を持つことが必要だ。人は集中するまで20分程度の時間を要するというデータがある。一度作業が中断されてしまうと、都度20分のロスが発生する。これが1日何度発生しているだろうか。
こうした個人の活動の効率性とチームの活動の調和を図るために必要なのが、チームの働き方の明文化、すなわち「チームの合意(Team Agreement)」である。
言語化③:チームの働き方を明文化する(Team Agreement)
チームの合意は、日常的に一緒に働くメンバー間での業務上の約束事である。例えば、「データの共有方法」「コミュニケーションの優先事項」「会議に関する決めごと」などが含まれる。一般的には、プロジェクトのキックオフなどの際に作成されることが多い。
ABWではこのチームの合意を、より活動に根差した観点で構築していく。例えば「予定に『集中作業』と入力されている場合はそれを尊重し、メールやチャットを控える」「週に2~3時間の集中時間の枠をスケジューラーに入力しておく」「◯曜日の午前中はチームで集まってコワークをする」「定時以降のメールやチャットは翌稼働日でよい」といった解像度で、自分たちにとって最善な働き方として明文化していく。
ポイントは構築のプロセスにある。チームのリーダーが一方的に設定するのではなく、チーム全体で議論しながら各項目を合意していく。チーム内であらかじめ話し合い、働き方の期待値をそろえておくことが重要だ。こうしたチームの合意を設けることで、個人の活動の効率化と組織の活動が両立され、柔軟で生産性の高い働き方が実現できる。 
「空気を読む」ではなく、働き方の言語化を
ABWは、個人が最適な活動を選択する働き方である一方、個人主体の働き方と組織としての働き方を調和させることが求められる。そのために必要なのが、ここまで記載してきた「働き方の言語化」だ。
こと日本は個人よりも組織が重んじられることが多く、「ハイコンテクスト文化」に分類される。ハイコンテクスト文化とは、文脈を重視し、その場で言語化された言葉だけでなく、暗黙的な背景や非言語的な要素を重視する傾向にあることを指す。いわゆる「空気を読む」といった表現が端的にこれを表している。翻って、ABWが発祥したオランダは、シンプルで明快なコミュニケーションを好む「ローコンテクスト文化」に分類される。こうした文化的な背景も、ABWがオランダで生まれた一因と言えそうだ。
多様な働き方の多様な人が混じり合うABWでは、それぞれが空気を読んで仕事をしていては不利益の方が大きい。全員の空気の読み方は常に同じにはならないため、それぞれの場所や時間で期待する活動の再現率は低くなる。これでは生産性は上がらない。柔軟な個人の働き方と組織としての規律や一貫性を維持するには、「働き方の言語化」が必須なのだ。
仕事の活動を見直し、それを言語化することによって、自分たちにとって最善なABWを実現することができる。次回はこうしたABWをサポートするデータやテクノロジーについて見ていく。

- 連載「ABW再考」のその他の記事はこちら
本記事はリサーチコミュニティ会員限定記事です。
リサーチコミュニティとは、総務などオフィス運用やマネジメントに携わる人のみの会員制サービスです。
限定記事の閲覧のほか、各種特典もご用意しております。