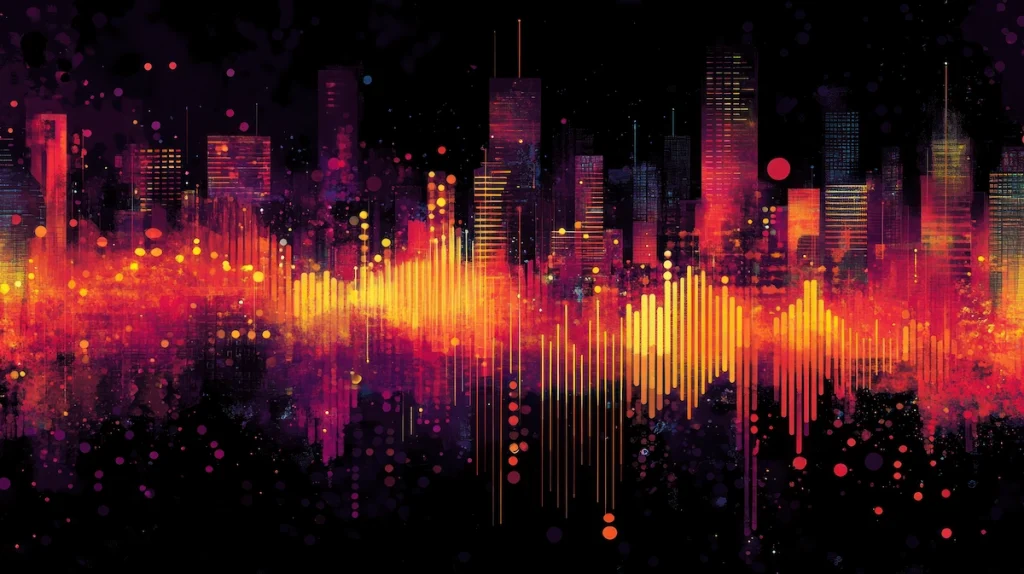「無駄なスペース」の削減が企業のパフォーマンスを落とす? ハイブリッドワークに対応する「乱流型オフィス」とは

最近のオフィス戦略の特徴に、「もっと業務を効率化できるのでは?」という不安から、無駄なスペースの削減などに執着しすぎる傾向がある。人々がチャンスを逃してしまう恐怖、「Fear Of Missing Out(逸する恐怖)」に駆られてしまうことが一因だ。しかし、無駄なスペースを削ったからといって、必ずしもチームのパフォーマンスが上がるわけではない。その解決策となりうるのが、予測不能な事態に柔軟に対応できる「乱流型オフィス」である。
Facility, Design, Culture
「オフィスを十分に活用できていない」という不安
精神分析医のアダム・フィリップス氏は、著書『Missing Out: In Praise of the Unlived Life』で、私たちが思い描く人生と実際に歩む人生の乖離について考察している。「Fear Of Missing Out(以下、FOMO)」として、人々を最も悩ませているのが、この生きられなかった人生、つまり「なりえたかもしれない自分」だ。
同様に、FOMOはオフィス戦略の策定にも影響を及ぼすことがある。例えば、「オフィスを十分に活用できていないのではないか」、あるいは「コスト削減やパフォーマンス向上の機会を逸しているのではないか」といった不安がその類である。
総合不動産サービス会社のJLL(ジョーンズ・ラング・ラサール)の調査によれば、企業の73%がオフィスのポートフォリオ最適化を主要目標として掲げている。
しかし、実際にはこのFOMOによって矛盾する要素が生じ、事態がややこしくなってしまうことが多いという。では、オフィスをより効率的に稼働させ、企業側のコストを抑えながら、高いパフォーマンスと従業員満足度を引き出すにはどうすれば良いのだろうか。
「無駄なスペース」の削減は本当に有効なのか?
ここ数年、オフィスワークとリモートワークをめぐる議論が活発化したことで、ハイブリッドワークが私たちの働き方の一つとして認識されるようになり、単なるスペース削減のための手段以上の意味を持つようになった。
一方、今では多くの企業がオフィス活用のジレンマを抱えており、社内の利用可能なスペースと実際の利用状況との乖離に悩んでいる。つまり、時間帯によってオフィスで働く人の数が変化するため、必要なスペースのバランスを見極めることが困難になっている。
一見すると、ハイブリッドワークなら出社する社員数を減らすことができるので、業務に必要なスペースを最小限に抑えることができ、無駄なスペースの削減につながりそうである。しかし、現実はそんなに単純ではない。社内の利用可能なスペースが縮小されると、チームの対面での顔合わせや社員同士のコラボレーションなどが難しくなるのだ。
この矛盾は想像以上に大きな影響をもたらしている。より効率的なオフィス設計をしようとすればするほど、対面での社員同士のつながりやコラボレーションの価値を、意図せず損なってしまう可能性があるからだ。

出社する社員が増えない理由
今では多くの企業が、日によってオフィスの利用者数が大きく変動せず、週を通して一定の稼働率を維持できるように努めている。具体的には、いくつか決められた出社日を定めたり、チーム単位で出社のローテーションを組んだり、出社する人が少ない日にはイベントを企画したりと、オフィスに人を呼び込むためのさまざまな施策が行われている。
しかし、このような社員に対する「アメ」と「ムチ」の施策は、いずれも大きな成果を上げていないようだ。ロンドン交通局のデータによると、2022年から2024年にかけて出社ラッシュのピークはほとんど変化していない。つまり、アメとムチを使い分けても、オフィス利用者に与える影響は、非常に限定的であることがうかがえる。
現実はそう簡単にはいかない。実際、社員たちが同じ日に同じオフィスで働いていても、やり取りの大半は対面ではなくオンラインで行われているらしい。これは在宅やリモートで仕事をするメンバーがいる限り、オフィスに出社している社員たちも、必然的にウェブ会議に参加しないといけないからだ。
結果として、オフィス自体が「リモートワーク対応」でなければならず、対面とオンラインの両方に対応できるオフィス設計が求められてしまう。
また、オフィスのスペース削減は、社員の出社意欲にも悪影響を与える恐れがある。会議室を事前に予約する必要性や、会社からオンライン会議に参加する手間、メンバーの出社率や空いている会議室の不確実性など、わずらわしい作業や予測できない要素が社内で摩擦を生み出し、人々は出社をためらうようになる。
そして、わざわざオフィスに出社する価値があるかどうか確信が持てず、次第にチームの日常業務は予測不能なものになってしまう。そうなると、一定の出社率を想定してオフィスを設計しても、日によって変わる社員の不安定な勤務形態に対処せざるを得なくなるのだ。
オフィスは「層流」から「乱流」の時代へ
こうした企業の想定と現実とのギャップは、流体力学の視点から説明することができる。
通常、オフィスの設計はいわゆる「層流」の原理を前提としており、予測可能で円滑かつ均一な利用形態を想定している。例えば、換気や避難経路などのビルの付帯設備は、この原理にもとづいて設計されていることが多い。
しかし、ハイブリッドワークの普及は、「乱流型」の職場環境を生み出した。「乱流型」の大きな特徴は、混沌としていて予測不能、そして突発的な急増があることだ。
ある時は、チーム全員がそろい、部署間で人々が行き交い、イベントも開催される。一方で、日によっては、天候、ストライキ、休暇、または明確な理由なしに、オフィスがほぼ無人状態になることもある。この「人流の変化」は、実際に起きてしまうことなので、ほぼ不可避的に生じると言っていい。
こうした環境下において、オフィスは高い変動性に対応すべく、状況に応じて融通が利く設計にしなくてはならない。そしてこの「乱流型」に対応できるオフィスは、これからさらに一般的なものになっていくだろう。

乱流型オフィスに求められるものとは?
この現象が意味することは何か。
まずは、変化に柔軟に対応できるスペースが必要ということだ。オンラインでのやり取りには、区画化された小規模なエリアの方が適しており、リモートでの打ち合わせには、優れた音響システムが不可欠になってくる。また、デスクとオンライン会議用のブースは近い場所に設置し、スムーズに行き来できるようにしなければならない。
次に、ただデスクの配置などに重きを置くのではなく、チーム全体の働き方を深く理解することも重要になる。一緒に作業をするなら大きいテーブル、長時間に及ぶ会議をするなら個室のように、チームの活動によってコラボレーションの形は異なる。しかし、どんな形態であれ大切なことは、働く人々が一体感を感じられるかどうかだ。
企業と社員双方のニーズに応えるデザイン
もちろん、企業、チーム、個人によってそれぞれ業務内容が異なるので、なかにはソファやコラボレーションエリアを設置する代わりに、オフィスのデスク数を増やすという考え方もある。「業務にはデスクが必要であり、ソファはオフィスに向かない」と考える人々にとっては、「デスク=生産性」なのだ。
しかし、そういう人々はもっと広い視点を持つ必要があるだろう。オフィスが混雑して騒がしくなれば、出社しようとする社員は自然と減っていく。つまり、デスクの密度を高めすぎると、逆効果を生み出しかねないということだ。
企業がオフィスに必要だと感じるものと、実際に社員たちが必要としているものには乖離があり、企業の目的と社員たちの働きやすさの間で妥協点を探さないといけない。
私は以前、あるプロジェクトで、広告・メディア企業向けのオフィス戦略を策定した。提案内容は、機動力を上げるために無駄なスペースを削減するというもので、理論上は機能するはずだった。しかし、最高財務責任者(CFO)にレイアウトプランを提出すると、核心を突く質問が返ってきた。
「このレイアウト変更で、実質どれだけの経費削減になるの? それはチームのパフォーマンスにどんな影響を与えるの?」
私は、企業側のコスト削減にこだわるあまり、働くチームの快適性や生産性を損なうリスクを考えていなかった。時々、費用対効果のバランスを取れていないものがあるが、このケースがまさにそうだった。

オフィスは「静的な入れ物」ではなく「動的な環境」
繰り返しになるが、FOMOはオフィス設計を歪めてしまうことがある。
なので、もしスペースを削減したいのであれば、デスクの数や占有率のデータだけでなく、人々が実際にどんな働き方をしているのか、それぞれのチームがどうやって連携しているのか、そしてどんなオフィス文化が全体のパフォーマンスを上げるのかも考慮すべきだ。
すでに一部の企業では流体力学を用いた実証実験が行われている。例えば、オフィスに人が少ない日(金曜日や休日、オフィス需要が低い時期)には一部のフロアを閉鎖し、チームを特定エリアやフロアに集約することで、エネルギー利用と施設管理の両面で効率性を高めている。
その結果、持続可能性目標の達成に寄与するだけでなく、社員同士のクリエイティブな接触を生み出し、部署間のコラボレーションを促す効果があったという。
こうしたアプローチは、オフィスがもはや業務を行うためだけの静的な「入れ物」ではなく、人々の働き方と相互に影響し合う動的な「環境」である、という認識の変化を意味している。
働く人に寄り添うこれからのオフィス設計
私たちは「機会を逸したくない」という考えに拘泥せず、人々の働き方や生活スタイルに合ったオフィスづくりをしていくべきだ。
それは単に社員数だけを見てオフィスを設計するのではなく、社員に寄り添いながらチームとして働くことの難しさを深く理解し、変化に柔軟に対応できるシステムを構築することによって、予測不能な事態に耐えうる環境を醸成していくことを意味する。
オフィス戦略は、ただ完璧を追求すれば良いというものではない。現実に即した空間づくりが重要だ。「どのくらいスペースが必要か」だけでなく、「そのスペースをどう最大限に活用していくか」まで、ぞれぞれのケースに合わせて独創的なデザインを提案していかないといけない。
働く人たちに少しでも貢献できるよう、不確実性を受け入れながら、これからもより良いものを想像し続けていこう。
- ミュリエル・アルトゥナガ氏は、常に変化し続けるビジネスの世界において、人、場所、目的の調和を図るコンサルティング会社「The Flow(ザ・フロー)」の創業者。デザイナー兼オフィス戦略家として、人間と空間の関わり方を具体的な形にしてきた経験を活かし、ビジネス戦略、サステナビリティ、不動産パフォーマンス、変革などをテーマにした人間中心設計のプロジェクトを数多く手がけてきた。これまでに、デザイン事務所、クライアント企業、CBREなどのグローバル不動産会社のプロジェクトで上級職を歴任している。
※本記事は、Worker’s Resortが提携しているWORKTECH Academyの記事「Turbulent flow: why firms need to overcome the fear of missing out」を翻訳したものです。