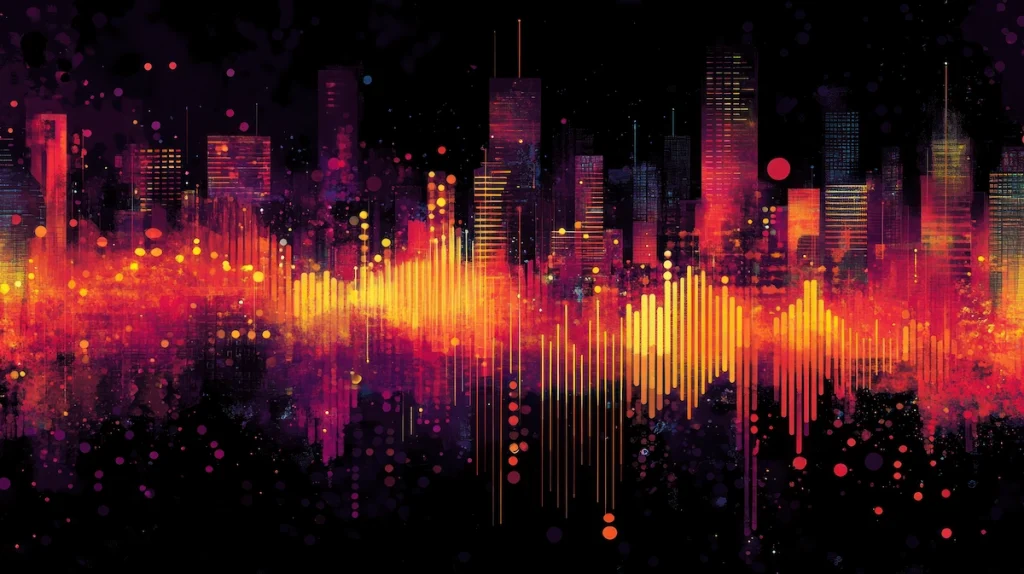【リースマン報告書】「通勤・出社・業務」は変わった。時代にフィットしたオフィスにするには?

英リサーチ会社リースマン(Leesman)による最新のワークプレイス調査報告書は、ハイブリッドワークで働く従業員をサポートするために、通勤、出社、業務の“リズム”に一貫性をもたせる、新たな方策の必要性を示唆している。
Facility, Design, Culture, Style
ハイブリッドワークで変わった仕事の“リズム”
ハイブリッドワークは今、知識集約型のワークプレイス運用モデルで主流となっている。とはいえ、広く浸透した共通の働き方のパターンはまだ確立されていない。ハイブリッドワークは、かつて均一だった仕事のリズムを、個別で流動的なものに変容させた。通勤、出社、業務は以前、大半の従業員が連続して行っていたが、今やそれぞれ独立した3つの行動として機能するようになった。
こうした潮流が現在の働き方を根底から変えつつあることを示したのが、リースマンが2025年10月に発表した報告書「Rhythms」だ。世界122カ国で働く150万人以上の人々の体験に基づく回答を収集・分析したこの報告書は、ワークプレイスの変化だけでなく、企業が多様な働き方への対応に苦慮している理由も明らかにした。
ハイブリッドワークでは管理体制と同様、運用の論理の「一貫性」が重要になる。通勤、出社、業務のリズムが機能して相互に補完し合うとき、組織は「より円滑な協働」「より強固な文化」「より安定したパフォーマンス」を発揮する。一方で、相互補完がみられない職場では、軋轢(あつれき)が増え、運用コストもかさむ。
出社を左右する通勤の満足度
通勤はかつて日々の労働に欠かせない要素だったが、ハイブリッドワークが導入されて以来、選択肢のひとつになった。リースマンのデータによれば、調査に回答した従業員の62%が、自らの通勤状況に満足しているという。
しかし、その裏には複雑な実態が潜む。通勤はリフレッシュや生産性の向上に役立つと感じている人がいる一方で、38%は「時間の無駄」と捉え、32%は「金銭的浪費」、30%は「ストレス要因」と感じている。通勤時間の長さは、通勤満足度を決定づける最大の要因だ。15分未満の通勤では満足度が92%に達するが、1時間前後では54%に低下し、2時間を超えるとわずか35%にまで落ち込む。
満足度は、移動手段によっても差が出る。自転車や徒歩で通勤する従業員の満足度はそれぞれ89%、88%だったのに対し、公共交通機関や自動車に依存する従業員の満足度は57%にとどまった(ちなみに、自転車や徒歩など自力で移動する「アクティブモード」は、世界で利用されている通勤手段のわずか14%に過ぎない)。
言い換えれば、通勤距離が長ければ長い人ほど、あるいは通勤のストレスが高ければ高い人ほど、在宅勤務の利便性を魅力に感じるということだ。また、都心のオフィスから遠く離れた場所に住む人々は、自宅に質の高い作業環境を整えるための投資を惜しまない傾向にある。そのため、企業が彼らにオフィス出勤を求めるなら、在宅勤務に匹敵する快適な環境を提供しなければならないだろう。
通勤はオフィス体験の根幹をなす要素だ。交通の便が悪い、あるいはストレスの多いアクセスしかないオフィスは、従業員に継続的な出社を促す際の阻害要因となる。一方で、充実した移動インフラや交通網にアクセス可能で、通勤後に利用する施設が整い、柔軟な始業時間を取り入れたオフィスであれば、自発的な出社パターンが形成される可能性が著しく高くなる。

若年層ほど出社する
全世界の企業を対象とした今回のリースマンの調査データによると、最も一般的な勤務パターンは週2〜3日出社で、回答企業の29%が採用していた。しかし、企業間でかなりばらつきがあり、34%は週2〜3日以上だったのに対し、37%は同2〜3日以下の出社だった。そして、週5日出社を義務づけている会社は、ほぼなくなったとみていい。
特に顕著なのが世代間のギャップだ。25歳未満の従業員のほぼ半数(47%)が週3日以上出社していたのに対し、55歳以上の従業員ではわずか28%。若い従業員はオフィスを社会的学習や帰属意識の形成の場、暗黙知の伝達の場として捉えているが、彼らが頼りにする肝心の同僚や先輩は不在の場合が多いことを含意する。
また、通勤の質も出社率に影響する。リースマンのデータによると、通勤の質に満足している従業員では、15%が週5日出社している一方、不満を持つ従業員ではその割合は6%に低下する。通勤に不満を持つ従業員は、満足している従業員に比べ、オフィスに出社する日数が週1日以下になる可能性がほぼ倍なのだ。このことから、通勤は動機づけと阻害要因の両方の役割を果たしているといえる。
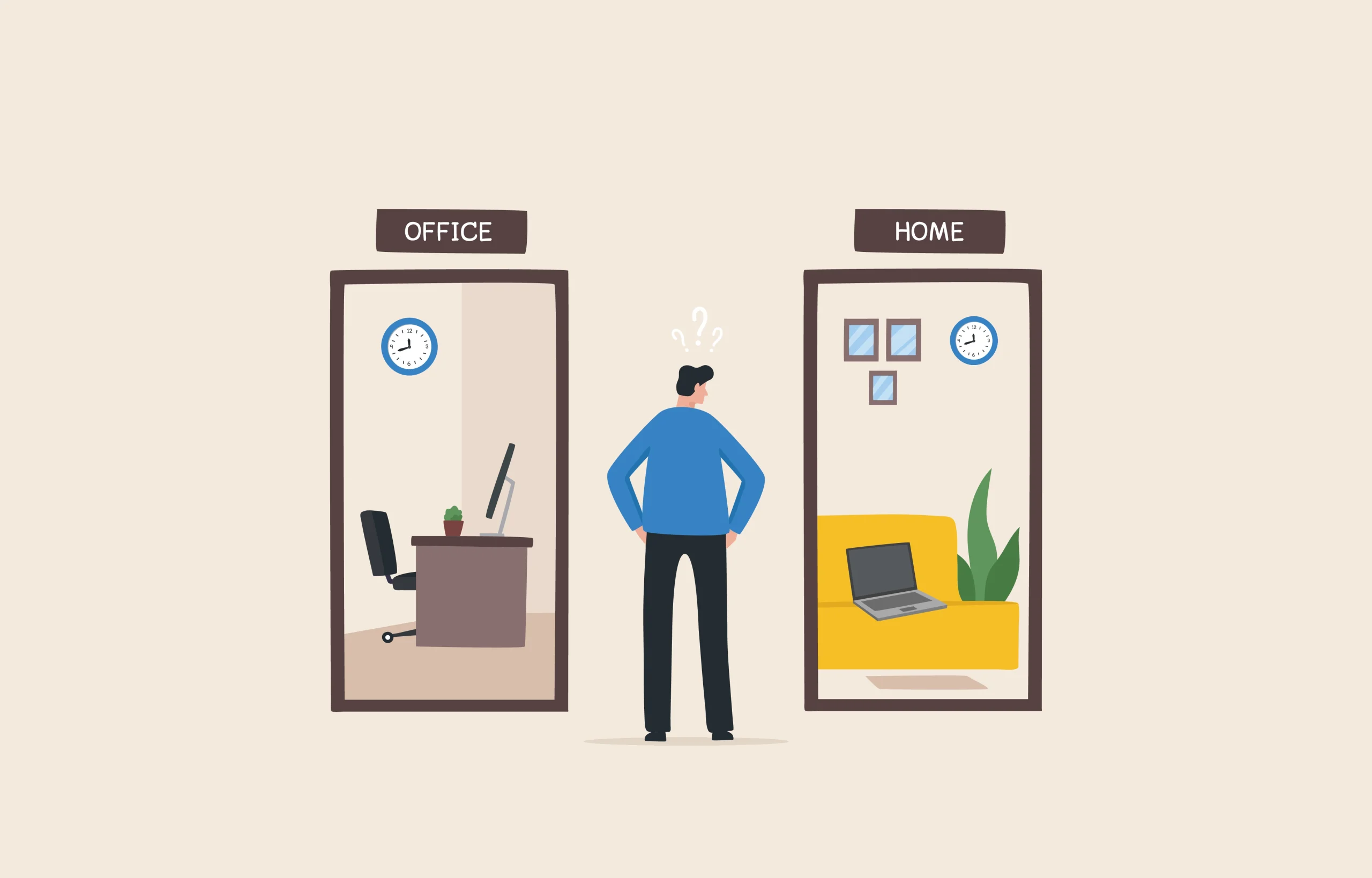
良好なオフィス環境が出社を促す
オフィス戦略も、目立たないながら、人々の行動パターンを左右する要因となっている。固定デスクを割り当てられた従業員の52%が週3日以上出社するが、同水準で出社しているのは、予約制の非固定デスク利用者の場合24%、完全なフリースペースの利用者は28%に過ぎない。
出社率はオフィス体験と相関関係にある。オフィスに不定期に出社する従業員の平均リースマン指標(Lmi:従業員のオフィス体験が優れていることを示す指標)のスコアは100点中約68点だが、週4~5日出社する従業員のLmiスコアは76点近くに達する。これは出社さえすればオフィス体験が向上するという意味ではないが、職場環境が良好であればあるほど、出社率が安定する傾向を示唆している。
企業がオフィス利用の目的を明確化して、出社日をより有意義なものにすれば、従業員は進んで出勤するようになる。例えば、共同作業のスケジュール化、専門家とやりとりできる環境の設定、他者との交流や認識を合わせる機会の提供といった取り組みが効果的だ。逆にいえば、従業員が出社後、オンライン会議にばかり長時間を費やしたり、適切な作業環境を探し回ったりして無駄な時間を過ごすようだと、オフィスは存在意義を失ってしまう。

「マルチモード」に合わないオフィス空間
ワークプレイスにおける最も重要な変革は、リースマンの報告書にあるように「第3のリズム」、すなわち「業務のリズム」で起きている。同報告書によれば、従業員は現在、自身の役職に不可欠な業務として平均9.3種類の活動を挙げているという。
これらには、深い集中を要する作業、例えば、「ハイブリッド型のコラボレーション」「非同期調整」「クリエイティブな課題解決」「プラットフォームをまたいだ継続的なコミュニケーション」などが含まれる。つまり、今日の業務はより多様化・流動化し、認知的要求が高くなっているのだ。
しかし、現実のオフィスは、そういった要求にまだ追いついていない。移動を促す設計を取り入れたオフィスでも、従業員のほぼ半数が「終日ひとつの場所にとどまって働いている」と答えている。また、34%はたまにしか移動せず、複数の環境を定期的に利用する人は16%に過ぎないという。
特筆すべきは、頻繁に移動する人ほどオフィス体験のスコアが低い傾向にある点だ。これは、多様なスペースが利用可能であっても、従業員が遂行しようとする業務ニーズに的確に対応できていない場合が多いと解釈できる。
現代の業務遂行にはマルチモードが避けられず、各モードに応じて複数の空間が求められる。それにもかかわらず、大半のオフィスは依然として、タスクの遂行方法に関してコロナ禍以前を前提としたままだ。そのため、オンラインによるコラボレーションが増加する一方で、従来型の会議室がフロアの大半を占めている。
集中して仕事に取り組める場所の需要が高まっているのに、集中して作業できるエリアの面積は相変わらず狭い。交流・協働のためのスペースは存在するものの、必ずしもワークフローのニーズに合っていないという問題もある。デジタルインフラと空間インフラは、いまだエコシステムとして統合されておらず、「並列」のままのケースが多い。
AIがワークフロー改革をもたらし、業務の認知的複雑性が急速に増すなか、適応力が求められるマルチモードの働き方をサポートする環境の必要性は、ますます高まっていく。それゆえオフィスは、従来の受動的な環境から脱却する必要がある。関係者のニーズを予測しながら、軋轢(あつれき)を減らし、日々の業務プロセスを全面的に支える、新たな環境へと進化しなければならないのだ。

理にかなったワークプレイスの構築を
通勤、出社、業務という3つのリズムを軸に考えれば、受動的な方針や単純な出社率管理中心の考え方では、ハイブリッドワークの課題に対処できないだろう。3つのリズムが調和すれば、オフィスは従業員が実力を発揮できるプラットフォームになる。しかし、それらのリズムが崩れれば、組織に摩擦が生じ、生産性、文化、ウェルビーイングに悪影響をもたらす。
今の時代に成功を収める企業の多くは、旧来の勤務体制を復活させたり、出社を義務づけたりはしないはずだ。そうした企業は、通勤のストレスを減らし、出社して働く意義を高め、複雑な業務ニーズに応じた職場づくりをするなど、一貫して理にかなったワークプレイスを構築することのできる組織だろう。
※本記事は、Worker’s Resortが提携しているWORKTECH Academyの記事「How purpose-led workplaces can help navigate today’s office challenges」を翻訳したものです。