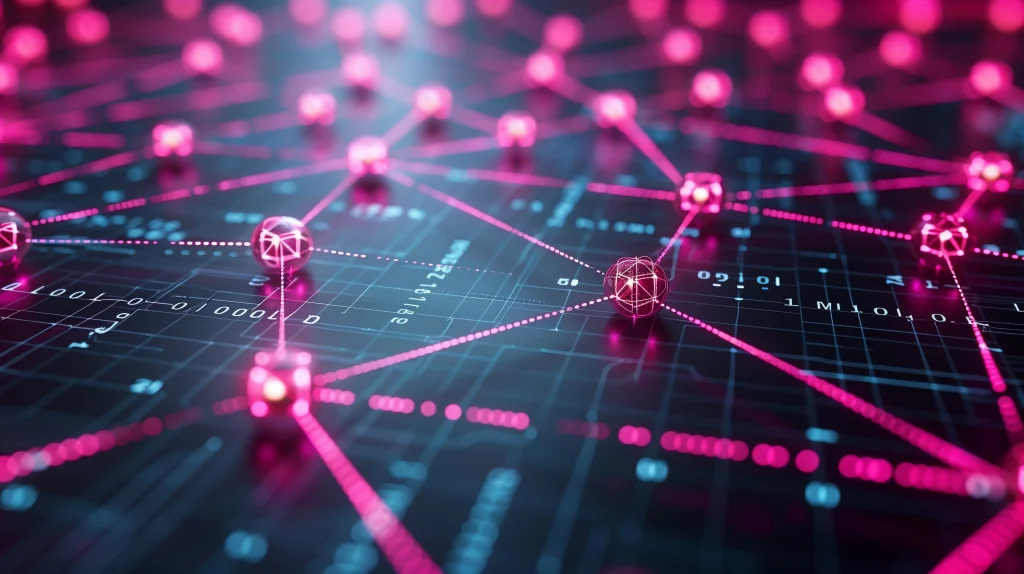テレワークで地方移住は加速する? 移住支援を行う国内企業と自治体の取り組み

テレワークの普及に伴い、地方移住への関心が高まっている。ここでは地方移住のメリットとデメリットを整理し、地方移住を推進する国内企業の事例や自治体の支援策を紹介する。
Culture
テレワークの普及が地方移住のきっかけに
コロナ禍で、テレワークが急速に普及した。内閣府の「第3回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によると、2021年4月~5月の東京23区のテレワーク実施率は53.5%、つまりおよそ2人に1人がテレワークで働いていることになる。
テレワークを緊急で導入するためにICT環境を整備し、結果として在宅勤務を含む多様な働き方が可能となった企業も少なくない。「働くこと」と「出社すること」がイコールではなくなってきているのだ。出社の頻度によっては必ずしも通勤圏内に住む必要はなく、生活の質(QOL)やウェルビーイングの向上を求めて、「地方移住」への関心が今後さらに高まることが予想される。
地方創生を掲げ、かねてより地方への移住支援に力を入れてきた政府は、この流れを受けて地方へ移住する世帯に最大100万円を支給する「移住支援金」の対象を拡大した。従来、移住支援金を受け取るためには、地方自治体が定めた企業に新規就業するか、その土地で起業することが条件だった。それが緩和され、テレワークで仕事を続けながら移住するケースも対象となっている。
本記事では、地方移住のメリットとデメリットを整理したうえで、新しい働き方として従業員の地方移住を支援する企業の事例、そして独自に支援策を展開する自治体について紹介する。
地方移住に関する調査から見えること
転職サイト「doda(デューダ)」が1万5000人の正社員を対象に行った地方移住・転職に関するアンケート調査によると、「新型コロナ感染拡大の影響で、あなたは故郷や地方へ移住して仕事をすることに対してどの程度興味を持っていますか」との問いに、29.2%が「地方移住・転職に興味がある」と回答。20~30代の比較的若い世代ほど、地方移住・転職への関心が高いことがわかっている。
また、同調査では、地方移住・転職に興味がある人の48.9%が「地方に住んで、その地方の企業で働きたい」と回答している一方で、51.1%が「地方に住んで、首都圏の企業にリモートワークなどで働きたい」と回答していた。今回の政府による移住支援金の対象拡大は、そうしたニーズにマッチした施策と言えるだろう。
地方移住のメリットとデメリット
地方移住を検討する際に頭に入れておきたいのが、そのメリットとデメリットだ。移住する側、移住を受け入れる側、企業側、それぞれの立場から見ていきたい。
1. 移住する側
地方に移住する側のメリットに、ワークライフバランスの充実があげられる。前出のdodaのアンケート調査でも、地方移住を希望する理由として、「実家がある」「自然あふれた魅力的な環境がある」「通勤ラッシュから解放されたい」「休日や余暇を充実させたい」「子育てに適した自然環境を求めて」などの声があがっている。家庭の事情や希望に沿う場所が見つかれば、QOLやウェルビーイングの向上も図れるだろう。
一方、デメリットとされるのが収入面だ。同調査でも、地方移住に踏み出せない理由として、「給与水準が低い」「希望する就職先がない」といった課題があげられている。
2. 移住を受け入れる側
受け入れる側にとってのメリットは、地域の活性化だ。移住者が増えると過疎化対策になり、地域産業が活性化すると地域の雇用が創出され、政府の掲げる地方創生にもつながる。
ただし、移住者の地域への定着率を上げるためには、地域のコミュニティに溶け込みやすい環境づくりを行うなどの中長期的な支援が欠かせない。そうした支援には手間や時間が必要となるため、思うような結果につながらない場合は、受け入れ側にとってデメリットともなり得るだろう。
3. 企業側
従業員が地方移住する場合、企業側のメリットとして、BCP(事業継続計画)対策となる点があげられる。また、ワークライフバランスの充実といったメリットを享受することで、従業員エンゲージメントの向上も期待できる。
その一方で、企業側の負担が大きいのも事実だ。従業員が地方に分散すれば労務管理が複雑になるうえ、テレワーク対応が十分ではない企業では、ICT環境の整備や情報漏洩リスクに向けたセキュリティ対策が必要となる。職場においても、「社内での気軽な報告や相談がしづらい」「細かなニュアンスが伝わりにくい」「従業員間のコミュニケーションが希薄になりやすい」といったテレワークならではの課題がある。
国内企業の取り組み事例
地方移住にはメリットとデメリットの両面があるが、テレワークの一歩先を見据えた働き方として、従業員の地方移住を推進する企業も出てきている。ここでは、取り組みのヒントとなる2社の事例を紹介する。
1.富士通株式会社
2021年3月、富士通株式会社は大分県と移住およびワーケーションに関する包括協定を締結。大分県の特色ある地域資源や人材と、同社のICT技術やノウハウを互いに活用することで合意した。
同社は、大分県と連携してサテライトオフィスの設置などの環境整備を進めており、移住を希望し要件を満たした従業員には、大分県での遠隔勤務を可能とした。また、テレワークを活用し、大分県に滞在して仕事をするワーケーションも支援している。同社では、コロナ禍の現況下、従業員の約8割がテレワークを行っているが、東京本社からかなり距離のある大分県での遠隔勤務は、企業としては思い切った施策と言えるだろう。
こうした地方移住への取り組みは、同社が2020年7月より推進している働き方改革「Work Life Shift」の一環であり、社会全体のモデルケースにしたいという狙いがある。大分県側は、移住やワーケーションによって定住人口・関係人口を増やすとともに、同社による新たなビジネスの創出にも期待している。
2.EYジャパングループ
EY新日本有限責任監査法人などを展開するEYジャパングループでは、グループ全社に向けて地方への移住を支援する「EYフレリモ移住プログラム」を試験的に実施している。
この支援制度の狙いは、長期的に働ける環境を用意して多様な人材を確保すること。育児や介護、家族の転勤や海外赴任の帯同といったライフイベントに左右されない、長期的なキャリア形成を支援する。同時に、大都市への人材集中を避けられるため、自然災害発生時のBCP対策にもなっている。同社では、移住に限らずテレワークの課題として、コミュニケーションのあり方、労務管理やメンタルヘルスケアの問題、評価制度、福利厚生の拡充の必要性をあげており、従業員の意見を反映した新たな体制の構築を進めている。

自治体の積極的な働きかけ
移住者の受け入れに積極的な自治体も増えている。コロナ禍でのテレワーカーの増加を受けて、多くの自治体が移住の支援対象を緩和した。政府だけではなく、こうした自治体からの支援もローカルシフトへの追い風となりそうだ。ここでは、都市圏から比較的近い長野県と群馬県の取り組みを紹介する。
1.長野県
長野県は、希望する移住先としてあげられることが多い都道府県の一つだ。長野県企画振興部信州暮らし推進課の「UIJターン就業・創業移住支援事業」は、もともと県内の指定企業へ就職する移住者に向けた支援制度だったが、都市圏の企業に在籍するテレワーク移住者も対象に追加された。長野県では、県内のほか、東京、大阪、名古屋にも移住相談窓口を設置し、都市圏からの移住支援に力を入れている。
また、移住しやすい地域の目安となるよう、積極的に移住者の溶け込み支援を行っている地区を「長野県移住モデル地区」として認定している。さらに、2021年2月には、若年世代やクリエイティブ人材を主なターゲットとして、移住の課題や疑問に向き合うコンテンツを発信する「信州移住ラボ」を始動。土地の魅力や情報発信だけではなく、移住につきものの不安を解消するための支援にも積極的だ。
また、県内の市町村の多くが移住者に向けた独自の支援策を実施。例えば、北陸新幹線の駅がある佐久市では、テレワーカーや住宅購入者を対象に新幹線乗車券代の補助を行っている。このように充実した情報発信や支援制度が、移住したい県としての人気を支えているようだ。
2.群馬県
東京圏から近い北関東周辺も、地方移住先として注目度が高い。その一つである群馬県は、東京有楽町に「ぐんま暮らし支援センター」を設置して移住の相談に応じるなど、東京圏からの移住者誘致に積極的だ。
群馬県移住のポータルサイト「ぐんまな日々。」では、その地域ならではの魅力とともに、県内のお試し移住体験施設の情報を発信。また、オンライン移住相談会を開催したり、テレワーカーやノマドワーカー向けの二拠点居住の体験ツアーを実施したりするなど、移住後のミスマッチを防ぐための取り組みにも力を入れている。
「転職なき移住」でローカルシフトは進む?
コロナ禍でテレワークを導入する企業が増え、多くの人が新しい働き方を経験した。収入面の不安が地方移住の大きな障壁ともされていたが、「従来の仕事をテレワークで続けながら地方に移住する」という可能性が生まれたことで、一気に現実的な選択肢となった。今回紹介したような、政府の移住支援金の対象拡充や自治体の支援策は、ワークライフバランスの観点などから地方移住に関心を寄せていたワーカーの背中を押す要素となり得るだろう。「転職なき移住」により、今後ローカルシフトは加速するのか。その動向に注目したい。