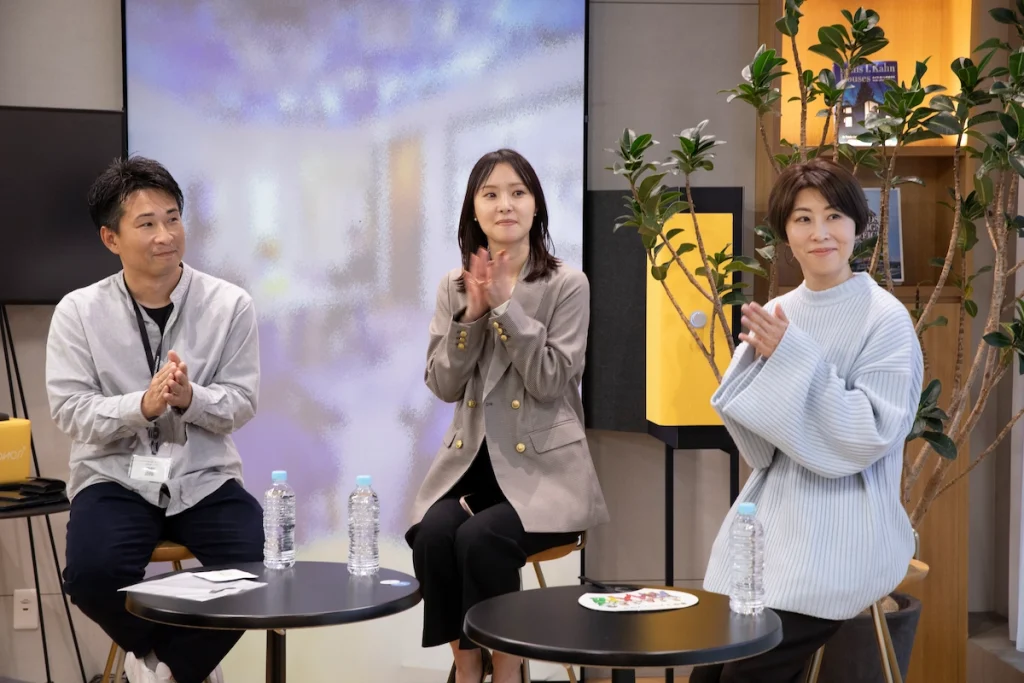“でこぼこ”こそが価値。大阪・関西万博「いのちの遊び場 クラゲ館」プロデューサー・中島さち子さんに学ぶ、組織の創造性を引き出す方法

4月13日に開幕した大阪・関西万博。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに8つのテーマ事業が展開され、それぞれの分野で活躍するトップランナーがプロデューサーを務めています。
そのうち、テーマ事業「いのちを高める」を担うのが、中島さち子さん。数学研究者でジャズピアニストという異色の経歴を持つ彼女は、専門家から芸術家、一般市民まで多様な人たちが入り交じる“ごちゃ混ぜ”の場で、シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」をつくり上げました。中島さんの体験を通じて、未来の働き方、場のつくり方のヒントを探ります。
Design, Culture, Style
-

中島 さち子/なかじま さちこ
株式会社steAm代表取締役社長、一般社団法人steAm BAND代表理事、ジャズピアニスト、数学研究者、STEAM教育家、メディアアーティスト。大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー(テーマ「いのちを高める」、シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」)。多様な文化が協奏するハブとなるKURAGE Band リーダー。1979年、大阪府生まれ。東京大学理学部を卒業後、ニューヨーク大学芸術学部修士課程(メディアアート)を修了。高校2年生で国際数学オリンピック金メダル獲得。東京大学在学中にジャズの魅力に目覚め、卒業後はジャズピアニストとしても活躍。現在はSTEAM教育の普及に注力し、株式会社steAmの代表を務めるとともに、大阪・関西万博テーマ事業「いのちを高める」のプロデューサーとしても活動している。また、内閣府STEM Girls Ambassadorとして、女性の科学技術分野への参加を促進する活動を行う。主な著書に『ヒット曲のすごい秘密』(青春出版社)『知識ゼロからのSTEAM教育』(幻冬舎)『人生を変える「数学」そして「音楽」』『音楽から聴こえる数学』(講談社)絵本『タイショウ星人のふしぎな絵』(絵:くすはらじゅんこ、文研出版)などがある。クラゲ館にまつわる絵本『クララとそうぞうの木』(ひかりのくに株式会社)やコンセプトブック(青春出版社)も発刊予定。資生堂ブランド クレ・ド・ポー ボーテによる、STEM分野での女性支援にて優れた働きをしている人を表彰する Power of Radiance Awards 2025 受賞者(本国初受賞)。
「NY留学」「STEAM教育の普及」「万博準備」の三刀流
――数学研究者にジャズピアニスト、さらにSTEAM教育を広める事業家の一面も持ち合わせる中島さん。その歩みの背景についてお聞かせください。
中島 中学の頃から数学を探究し始め、高校のときに国際数学オリンピックで金メダルを獲得しました。大学でも数学を専攻していたのですが、同時に出会ったのがジャズの世界。就職活動をする代わりにジャズクラブでピアノを弾いて回り、卒業後はしばらく音楽活動に専念していました。数年して数学研究の道にも戻り、さらに音楽と数学の繋がりに気づいてさまざまな講演やワークショップなどの活動をはじめたのは、子どもが生まれ、より社会に貢献できることをしたいと思うようになったからです。2017年にはSTEAM教育の会社(株式会社steAm)を立ち上げ、新しい学びの提案に取り組んでいます。
STEAMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Art/Arts(美術・リベラルアーツ)、Mathematics(数学)の頭文字を組み合わせた造語で、それぞれの領域を横断的・創造的に活かした探究型の学習を指します。2020年からの学習指導要領の改訂を機に、探究という言葉が教育現場でも普及する中、STEAM教育に注目が集まり、学校や企業と協業しながら30ほどのプロジェクトを進めてきました。
並行して、経済産業省や文部科学省の教育関連の委員会や実証事業にも参画していた頃、万博協会からコンタクトを受けたのをきっかけに、大阪・関西万博の「いのちを高める」というテーマ事業のプロデューサーを務めることになりました。任命された2020年7月は、ちょうどニューヨーク大学院での留学から帰国したところでした。

――日本で会社を立ち上げながら、留学ですか⁉
中島 ちょうどフルブライト奨学金の選考を通過したタイミングだったんです。仕事か留学のどちらを選ぶか一瞬迷いましたが、両方やろうと。ニューヨーク大学では、アートとテクノロジーの狭間にあたるメディアアートを専攻し、音楽と数学とテクノロジーと社会にまたがる創作活動に励んでいました。官庁のプロジェクトも、日本にオフィスがあり、たまに帰国してきちんと遂行できるなら問題ないという話でしたので。実際にほとんど不都合を感じることはなかったですね。
当時を振り返ると、実に目まぐるしい毎日でした。昼は大学で学び、家に帰れば深夜に日本の人たちとミーティング。でも、大学にはエンジニアやデザイナー、音楽家など、いろんな経歴の人たちが各国から集まっていて、新しいものを生み出す環境がとても刺激的でした。創造する面白さにあふれる2年間で、諦めずに挑戦して本当によかったと思います。
娘を連れて2人での渡米でした(時に母も渡米して手伝ってくれました)が、娘にとってもすごくよかったですね。日本の学校では、どうしても似た価値観の人たちが集まりがちですから。まるで異なる環境で過ごした時間は、人生において糧になる経験だと思います。
ごちゃ混ぜな八百万の人の手でつくり上げる、いのちの遊び場
――中島さんが大阪・関西万博で手掛けられる「いのちを高める」とは、どのような状態を指すのでしょうか?
中島 まず、今回の万博では「いのち輝く未来社会のデザイン」という全体テーマを掲げています。その象徴として、シグネチャープロジェクトと呼ばれる8つのテーマ事業が設定されました。「いのちを高める」はその1つです。
私はジャズピアニストでもあるので、よく他のミュージシャンとセッションをします。演奏をしていると、その場限りの瞬間的な巡り合わせによって音楽が生まれ、得も言われぬ高揚感に包まれます。このときの感覚が、まさに私にとっては「いのちを高める瞬間」なんですよね。「いのちを高める」の英語表記「Invigorating Lives」には、エネルギーを注入する、元気にするというニュアンスがあります。
いのちを高める瞬間は、音楽だけに限りません。数学のような一見勉強に映るものでも、映画などで数学者が突然、黒板や壁いっぱいに数式を書き出すシーンのように、人間はクリエイティブな状態にあるとき、いきいきと輝くのです。
この事業では、いのちを高める瞬間に立ち会える、創造的な場の創出を目指しました。私はよく「創造性の民主化」という言葉を使いますが、地球上にいる誰もが多様な自分らしいクリエイティビティを発揮することで、プレイフルでインクルーシブな希望に満ちた社会を築きたいという思いから、この事業に参画しています。
――シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」は、どのようにつくられたのでしょうか。

中島 他の事業との大きな違いは、時間をかけ、「八百万(やおよろず)の人たち」の手でつくり上げたことでしょう。コンセプト段階では「闇鍋会議」と称し、設計に携わった建築家の小堀哲夫さんチームをはじめ、芸術家や数学者、教育者などが集まり、「万博とは何か」といった万博の価値や意義の部分から問い直し、骨格をデザインしました。
その後、「クラゲプロジェクト」と称し、子どもから大人まで、障害のある人、海外の人も交え、ごちゃ混ぜなメンバーで分科会やワークショップを繰り返しながら準備を進めてきました。特にクラゲ館のシンボルマークは、「クラゲバンド」による演奏に合わせて、多様なみんながペンキでドロドロになりながら思い思いに体を動かした末に生まれた壁画からクラゲ館らしいところを取り出して生み出したものです。
会期前からさまざまな参加型イベントを用意し、会期中も来場者は展示をただ眺めるだけではなく、いろいろな形でクリエイティブを体験できます。加えて会期後も、クラゲ館の一部は解体され、遊具などに変身して世界各地に飛び立つ仕掛けになっています。
――建物や展示ができて完成ではなく、常に変わり続けるのですね。
中島 その通りです。私たちは万博をゴールではなく、実現したい社会に向けた1つの機会と捉えています。万博というと、多くの方は大きな打ち上げ花火のようなイベントだと捉えているかもしれません。でも万博の本質は、その対極にあるのではないかと感じています。
今の時代、誰もが創造性を発揮できるだけの技術や材料はそろっています。本来なら、「いのちを高める」瞬間にあふれていてもいいはずなのに、現実は残念ながらそうなっていないですよね。社会という場の影響なのか、自己肯定感を得られなかったり、素の自分とは異なる役割を演じ続けていたり。また、障害のある人とそうでない人の間で、生活する環境自体に分断が生じています。
しかし実際に人をごちゃ混ぜにした創造的な活動を体験すると、一人では思いもしないものが生まれる瞬間に立ち会えて、とても楽しいものです。それに価値観や宗教、体格、性格など、自分とは違う人と出会うことで、逆に自分を知ることができます。この感覚を多くの人に味わってもらい、社会を変える力にしたいと考えています。

「全員がその場にいる」という感覚の共有が、恐れや立場を乗り越える
――仕事をするうえでも「いのちを高める」感覚は大切ですね。
中島 今回、テーマ事業「いのちを高める」に協賛いただいた企業のみなさんにも、プロジェクトの当事者として参画いただきました。月に1、2回の全体会に加え、週10本以上の分科会が並行して行われていて、協賛企業の社員も参加しています。組織の枠を超えて一緒につくり上げる体験は、特に若手社員にとって大きな刺激となったようです。
企業のみなさんと取り組む中で、組織と個の関係性ってなかなか深いなと感じましたね。学術系の人やアーティストは「個を立たせてなんぼ」なところがあるけれど、組織人ってまた違うじゃないですか。組織だからこそ、個人では難しいスケールの大きなことに取り組めるのだけど、個を切り捨てたら機械がやるのと変わらなくなってしまう。その組織ならではのユニークネスの源泉は、やはり一人ひとりの個性が発揮され、いのちが高まる瞬間にあるのです。
――多様な人々が集まるほど、コンフリクトマネジメントが重要になってきますね。
中島 いろんな人がいますから、当然ながら意見の相違や揉めることもありますし、万人が満足する解など、そう得られないものです。私が思うのは、どこかで恐れがあったり、立場を脅かされたりしたときに、おかしな流れになるんじゃないかって。相手の考えを受け入れられないのは、何か守りたいものがあるときなんですよね。
そこで大事なのが、思想なんです。万博だったら何万人を動員するといった話ではなく、創造性の民主化の実現といった上位の概念。実現したい世界が面白いと、自然と面白い人が集まってくるんです。その上でプロジェクトのお題を具体的にします。例えばどんなパビリオンがいいか考えようとか、シンボルをつくろうとか。
あとは個々の存在を認めることも大切ですよね。今回、障害を持つ方たちと一緒に準備し、社会はマジョリティ思考でつくられていると改めて気づかされました。多数決で平らに均すやり方は一見公平で整って見えるけど、少数派の声を抑え込んでいるわけですよね。でも、プロジェクトで対等に議論したり一緒にご飯を食べたり、創作したりすると、“でこぼこ”なんだけど、全員がその場にいる。それが不安や恐れから、私たちを救ってくれます。

創造性は、遊びの中から生まれる。“クラゲ”のような自由を体感して
――個にフォーカスしながらも、広く捉えるのが大事なのかもしれません。
中島 クラゲプロジェクトでは、「身体性」も大きなキーワードです。例えば、クラゲチームたちは、韓国のチャンゴ奏者のチェジェチョルさんやセネガルの太鼓奏者のアブライ ンジャイ ローズなどクラゲバンドのメンバーと一緒になって、いろんなイベントで道行く人を巻き込みながら共に歩いてみたり手を叩いたり、タンバリンを叩いたり、踊ったりしてきました。それを「くらげJAM」と呼んでいます。「くらげJAM」をすると、子どもはもちろん、さっきまで無表情だったおじさんも、年配の方も、だんだんと柔和になっていくんです。背景にある思いは人それぞれ違うかもしれないけれど、通じ合うものが生まれるんですね。そもそも人間って、いや生きものって、“生きている”という大きなところで共通しているんですよ。
チェさんとは、共に同様のクラゲ研修・ワークショップを企業に対しても行っており、やっぱり企業の経営幹部候補の中堅の方々が、どんどん表情や動きが変わってくること、それがチーム力・深い意味でのリーダー力(聴く力・感じる力)につながっていく!という声を頂いています。
共に“生きている”にも関わらず、普段私たちは、人種や宗教、政治、ビジネスなら職場の立場に目を奪われると、いのちが高まる感覚が削ぎ落されてしまう。実は多様性も、いろんな人が集まって一緒に何かをすることで得られる“知”に豊かさがあるのに、「こういう人を採るべき」とか、「多様性を進めるべき」とか、手段の目的化に走ってしまう。それでは本来の目的を達成できないでしょう。
私たちは優秀さや正しさという評価軸を気にしがちです。そこにとらわれるとどんどん固く縮こまって、立場や恐れが生まれてしまう。NYに留学中、授業で自分の創作物について説明するときに「ものづくりはヘタだけど」と前置きをすると「そういう前置きはいらない」、「下手とか言うな」っていつも言われていました。これは、日本人の悪い癖だなと。謙遜の一言が、抑圧の要因にもなっているんじゃないかなと。
――抑圧によって、思考に限界が生じてしまいますからね。
中島 創造性は揺らぎのある遊びの中から生まれ、遊びは限りなくシンプルで、心の制約のない場に生まれるんですよね。クラゲプロジェクトでも、自分で考えていい、好きに感じていい、動いていい、思いを言葉にしていいって、自身の心の制約を外して自由になれると、どんどんいきいきしてきます。
それはロジカルには説明しきれないもので、でもものすごく大切な何かが生まれているんですよね。「いのちを高める」事業でもこの感覚を表現したくて、それで出てきたのが、“クラゲ”だったんです。ゆらゆらと逆らわず、しなやかに形を変えながら、幻想的で美しい、あの姿です。
――「いのちの遊び場 クラゲ館」は、私たちの周りにある囚われを取り払って、共創を試みる実験の場です。ぜひ、こどもはもちろんなのですが、実は大人こそ足を運んで、未来の学び、遊びを体感してほしいと思います。きっと働く場をデザインするためのヒントを、たくさん持ち帰ることができるはずです。