【多国籍チーム】翻訳を超えて価値を生む「ブリッジ人材」の役割とワークプレイスの意義
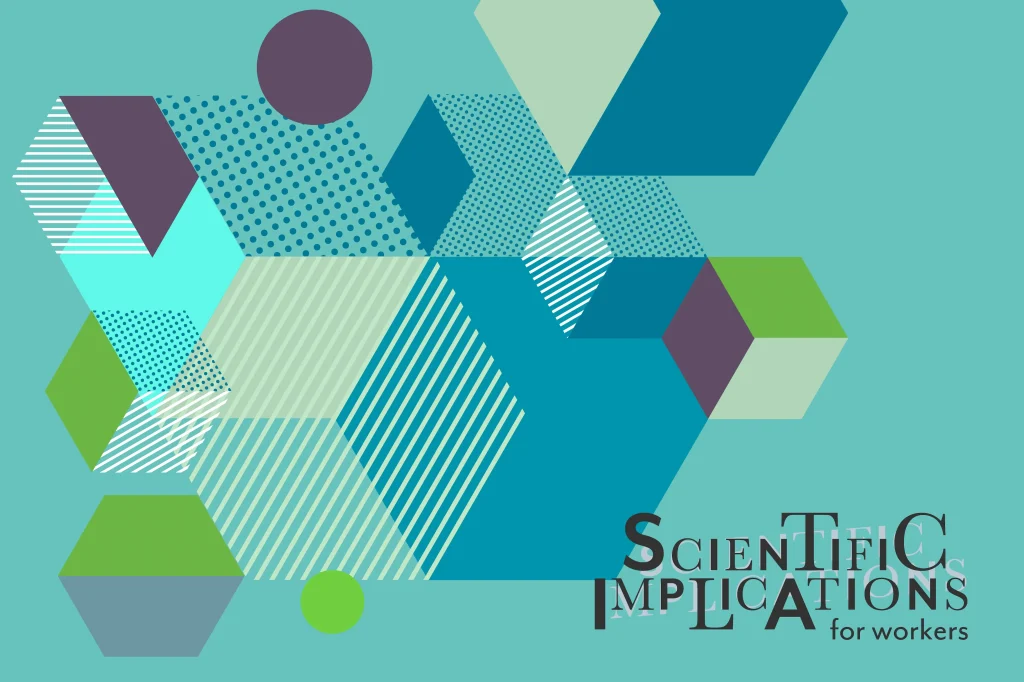
機械翻訳などのツールが発達し、言語の壁がかつてなく低い現在でもなお、多国籍チームのプロジェクトではコミュニケーションにまつわる課題が尽きない。「さまざまな国や文化の出身者で構成されるチームのメンバーが、円滑に協働しつつ一緒に働ける状態の実現につなげたいです」と研究のビジョンを語る法政大学准教授の戎谷梓氏のお話から、すれ違いの根本原因と乗り越えるためのヒントを探る。
Culture, Style
-

戎谷 梓/えびすや あずさ
法政大学経営学部准教授
大阪大学大学院にて言語文化学の博士号を取得。大阪大学大学院経済学研究科助教、米ラトガースビジネススクール客員研究員などを経て、2021年より現職。専門分野は国際人的資源管理。 多国籍・多文化出身者で構成されるチームの相互作用やコミュニケーションに関する研究を推進する。
言語翻訳だけでは解決しない多国籍コミュニケーション

グローバル化とリモートワークの普及に伴い、多国籍チームでの連携は特別なことではなくなった。近年では、AIを活用した翻訳ツールの性能向上も目覚ましく、言語そのものの障壁はかつてなく低い。しかし、現状ではいまだに多くの企業がコミュニケーションの課題に直面している。
互いにプロフェッショナルとしてのスキルや姿勢を持って仕事に臨んでいるにもかかわらず、なぜかすれ違いが生まれることはないだろうか。情報提供を待っていたら「積極性がない」と誤解されたり、逆によかれと思って積極的に連絡したら「無駄な情報ばかり送ってくる」と受け取られてしまったりする。些細な認識のズレはメンバー同士の不信感を強め、チーム全体の生産性をむしばんでいく。
こうしたすれ違いの原因は、個々の能力や意欲の問題よりも、「常識」のズレにあることが多い。たとえば、ある文化圏の出身者は、要件定義から設計、実装へと進む直線的なプロセスを当然と考える。一方で別の文化圏の出身者は、試作品を作りながら顧客と対話し、改良を繰り返す開発スタイルに慣れ親しんでいるかもしれない。
このような仕事の進め方や目標に対するチーム内の暗黙的な共通認識は、「チームメンタルモデル」と呼ばれる。「暗黙的であるがゆえに、どこにズレがあるかを突き止めるには時間がかかります。一方で、短期間で終わらせないといけないプロジェクト形式の業務では、共通認識や相互理解を醸成する十分な猶予がないのが悩ましいところです」と、多国籍メンバーのコミュニケーションを研究する戎谷氏は指摘する。
事業や情報伝達の加速が進むこれからのビジネス環境では、ますます対応が迫られる課題となっていくだろう。
考え方を橋渡しする「ブリッジ人材」

暗黙的で文化的な背景も色濃く反映されたチームメンタルモデル。背景の異なるメンバー間でこれを共有するにはどうすればよいのだろうか。戎谷氏の研究からキーとして見えてきたのは「ブリッジ人材」の存在だ*1。
ブリッジ人材とは、単に言語の翻訳や通訳を行う人のことではない。戎谷氏によれば、その本質は言語の意味が伝わるようにするだけでなく、その背景にある考え方について共通認識を成り立たせるところにある。言語を超えた、考え方のレベルでの橋渡しをする存在ともいえるだろう。文化的背景が異なるメンバー同士の間に立ち、双方の考えを汲み取ったうえで、互いの理解が深まるようコミュニケーションを進める役割だ。
この役割は、プロジェクトマネージャーやファシリテーターなど、さまざまな立場のメンバーが担うことができる。通訳者として働く中で、言語の翻訳だけでは不十分だと気づき、考え方や価値観の橋渡しを自発的に行うようになった人もいるという。
考え方の橋渡しにあたって求められる資質は多岐にわたる。前提となる異文化理解への積極的な姿勢と言語能力に加え、双方にわかりやすくものごとを伝えるプレゼン力や、メンバー間の問題を察知し、解決に導く調整力も必要となる。ここでの「プレゼン力」には、考え方の異なるそれぞれのステークホルダーに耳を傾けてもらうための信頼構築力も含まれてくる。
「エンジニアのような専門職がブリッジ人材を単なる通訳者としか見ていない場合、どうせ技術のことはわかっていないだろうという意識が働き、聞く耳を持ってもらえないことがあります」と戎谷氏。ただ言葉を翻訳するだけでなく、「あなたの専門分野について理解しています」という姿勢を示すことがブリッジの起点となる。新機能が必要とされる目的を丁寧に説明したり、技術的な観点からの懸念を先に問いかけたりすることで、「この人は我々の立場を理解したうえで話している」という信頼感が生まれ、円滑な対話の土台が築かれるのだ。
日常業務には翻訳や通訳といった作業も含まれるが、ブリッジ人材の働きの中でより重要なのは、チーム内で生じているあつれきの兆候や些細な問題を察知し、対応することだ。各メンバーの状況を把握し、両者の認識が一致しているかを確認する。齟齬があれば解決や調整に動く。
期間の限られたプロジェクトでチームメンタルモデルを速やかに成り立たせるうえで、各メンバーが信頼を寄せるブリッジ人材が果たす機能は、極めて大きいといえるだろう。
バーチャル環境でこそ重要さを増すブリッジの力

チームの共通認識を育むうえで、ブリッジ人材が担う繊細なコミュニケーションの重要性が見えてきた。しかし、近年普及が急速に進むバーチャル環境において、その機能は十分に発揮されるのだろうか。
対面であれば、表情や身振り手振り、声のトーン、話す速さといった非言語的な情報を豊富に得られる。一方、特にカメラオフのWeb会議やテキストベースのやりとりでは、こうした非言語情報がごっそりと抜け落ちてしまう。ブリッジ人材が各メンバーの状況を把握したり、認識合わせを行ったりするときの難度は格段に上がることになる。
この困難な状況で重要性を増す要素が「感情知能」であると戎谷氏は言う。感情知能は、自分自身と他者の感情の認識を行い、それらを踏まえたうえで、その場にふさわしい形で自らの感情を表出・制御する一連の能力を指す*2。バーチャル環境で信頼関係を構築し、精緻な相互理解を目指すには、対面時以上にこの能力を駆使する必要があると戎谷氏は指摘する。
たとえば、わずかなミスでも厳しく非難されるチーム環境では、不安や恐れから意見の発信や状況の共有をためらってしまうメンバーもいるだろう。その結果、仕事の進め方や考え方のズレが察知されにくくなり、気づかないところで重大な認識違いが起きていた、という事態も想定される。チームメンタルモデルの形成に向けて考え方のズレを調整する土台を整えるためにも、感情面への配慮は重要なものとなるだろう。
人間同士の連携における感情の重要性と、昨今のAIツールの発展を踏まえると、ブリッジ人材が担う役割の比重が今後変わってくると予想される。従来の仕事のうち言語面の翻訳に関しては、ツールの活用でより効率的に行うことができるようになるだろう。その分、より本質的な役割である考え方や価値観の橋渡しや、安心してコミュニケーションを取れる環境構築に注力できるようになると期待される。
ワークプレイスが担う橋渡しの可能性

ブリッジ人材の根幹となる考え方の橋渡し機能を強化し、チームメンタルモデルの形成を促すために、これからの組織ができることは何だろうか。その答えのひとつは、物理的なオフィス空間とバーチャル環境の両面において、ワークプレイスの機能を見直すことにあるのかもしれない。
まずは物理的なオフィスから考えてみよう。オフィスには、会社の文化や価値観を伝達したり、共有したりする機能があることが指摘される。
たとえば、役員と社員が同じ空間で働くフリーアドレスのオフィスはフラットな風通しのよさを感じさせるし、活動的な色合いが目立つ空間から積極的なチャレンジを推奨する方針を読み取るメンバーもいるだろう。オフィス空間に暗黙的な文化や価値観を伝える機能があることを考えると、チームメンタルモデルの形成を促す効果も期待できる。ブリッジ機能の一部を、オフィス空間が担うことができるのだ。
Web会議やチャットを軸としたバーチャルなワークプレイスにも、このブリッジ機能を持たせることはできないだろうか。たとえば、物理的なオフィスでみんなが見えるところに掲示物を張るのと同じイメージで、バーチャル空間でも同様の体験は作り出せるかもしれない。メンバー全員が日常的にアクセスするポータルサイトやチャットツールの目立つところに、プロジェクトの目標やチームとして大切にする考え方を表示しておく。こうした工夫は、バーチャルな空間における共通体験として、チームメンタルモデルの形成を助けるだろう。
ワークプレイスがブリッジ機能を持つという発想は、ブリッジ人材の働きを後押しするだけでなく、働く環境づくりを担う人事や総務の担当者、オフィスマネージャーらにも新たな可能性を提示するだろう。「組織の文化や価値観を共有できる場をどう作るか」「メンバー同士の一体感を強めるのはどのような職場か」といったオフィスづくりの知見は、これからの組織で重要性を増すチームメンタルモデルを育む知見として捉え直すことができる。それは物理的なオフィス空間に限らず、バーチャルなコラボレーション環境にも応用可能なはずだ。
「ブリッジ機能」をキーワードに、働く場とコミュニケーションのデザインを担う人材の重要性と活躍の場は、今後さらに広がっていくだろう。
- *¹ Ebisuya, A., Sekiguchi, T., & Hettiarachchi, G. P. (2021). Narrowing the communication gap in internationally distributed teams: The case of software-development teams in Sri Lanka and Japan. Asian Business & Management, 1-25.
- *² Ebisuya, A., & Hettiarachchi, G. P. (2023). A Step Forward Towards Understanding Emotional Intelligence for Effective Virtual Teams. 経営志林, 60(1).












