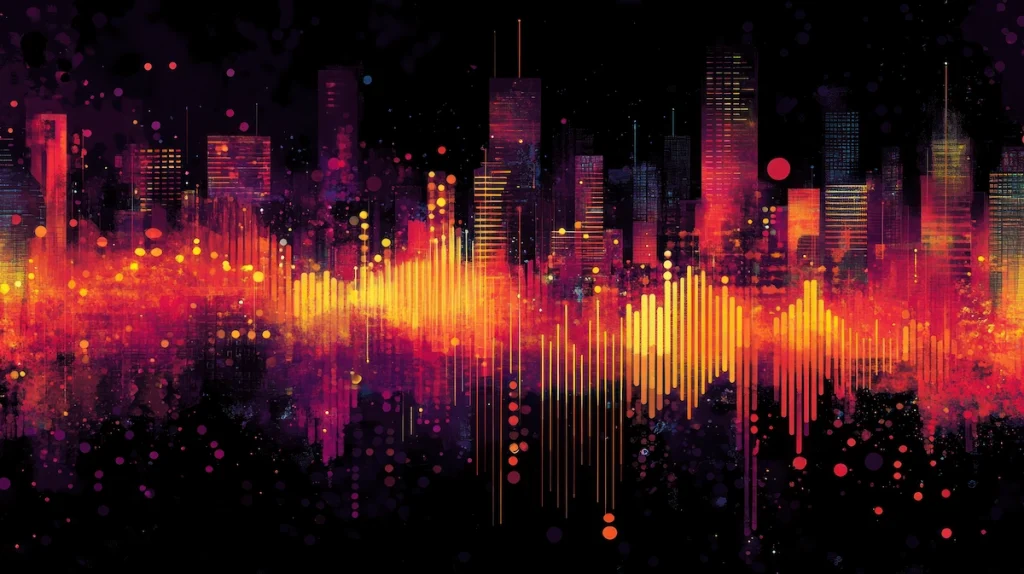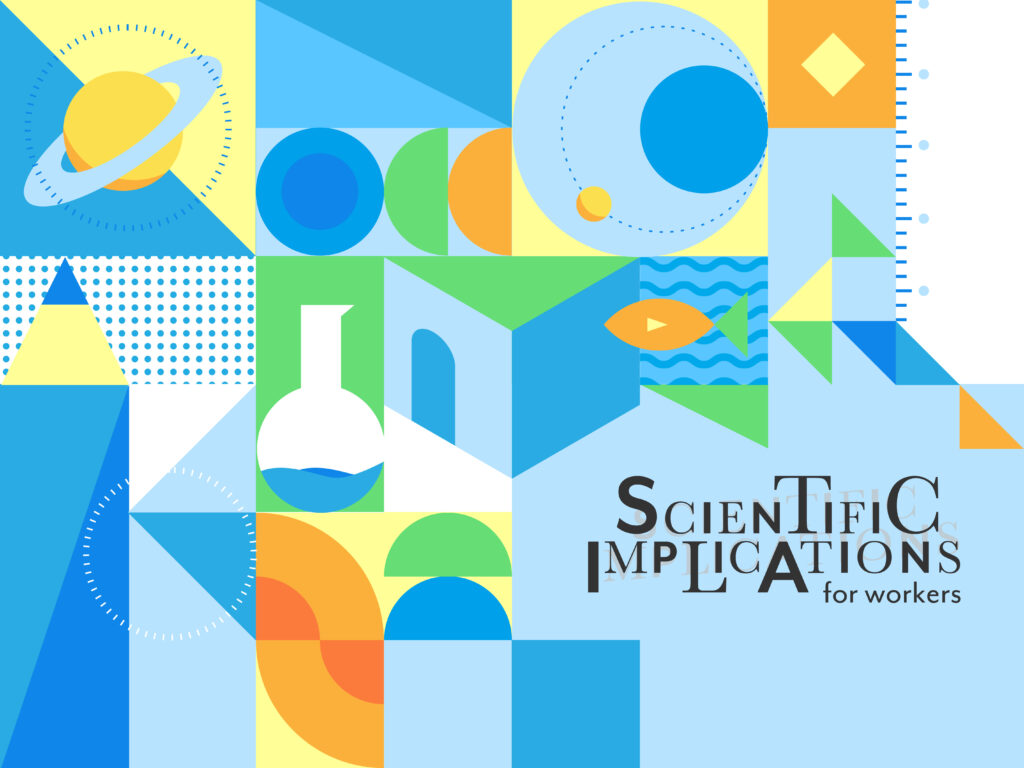【三宅香帆さんインタビュー】ベストセラー作家が語る、これからの組織に必要な「半身で働く」仕組み

忙しくて本が読めない。空いた時間にはスマホばかり見てしまう……。それは、自分自身のせいではなく、社会の仕組みの問題かもしれません。
文芸評論家・三宅香帆さんは、就職をきっかけに読書から遠ざかった自身の経験から、全身全霊で働く価値観を問い直します。三宅さんの提唱する「半身で働く」社会とは。新書大賞2025を受賞した話題作『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者・三宅さんに、これからの働き方の可能性とその効用について伺いました。
Culture, Style, Research Community
気づけば本を読めていない! ノイズを遠ざける全身全霊の働き方
――2024年に出版された『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)は、年間ベストセラー1位を獲得し、「新書大賞2025」も受賞。大きな話題を呼びました。あらためて、本書の内容について教えてください。
三宅 この本は、「労働と読書の近代史」をまとめたものです。課題意識の出発点には、会社員時代の私自身の経験がありました。私は子どもの頃から本が大好きで、学生時代まで息をするかのように活字に触れるのが当たり前の毎日を過ごしてきました。ところが就職した途端、読書が思うようにできなくなってしまったんです。
仕事は楽しかったですし、毎日が充実していました。でも、仕事が生活の主軸を握ると、どんどん“余白”が埋められていく感覚があって。わずかに空いた時間も、気づけばSNSや動画を眺めていて……しばらく本を手にしていない自分に気づいたとき、愕然としました。
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」というタイトルの連載をネットで始めると、とても大きな反響がありました。この本も、タイトルに共感して手に取る方が多いようです。つまり、「本が読めない」のは単なる個人の問題ではなく、社会の仕組みがそうさせているのではないか。本書では、働き方や社会のあり方が読書にどのような影響を与えているのか、その背景をひもとくことを試みました。
-

三宅香帆/みやけかほ
文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。1994年高知県生まれ。京都大学人間・環境学研究科博士後期課程中退。リクルート社を経て2022年に独立。主に文芸評論、社会批評などの分野で幅広く活動。“働きながら本が読める社会をつくる”をミッションに、読書や物語の魅力、働き方や生き方などについて発信、講演を続ける。著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書)など。

――本書では、新自由主義や情報社会の加速が、私たちを読書から遠ざけたのではないかと指摘していますね。
三宅 2000年代以降、インターネットの発達によって、欲しい情報にすぐにアクセスできるようになりました。一方で、「仕事を通じて自己実現を目指す」という価値観も広がっていきます。
膨大な情報が飛び交う中で、「仕事に役立つ情報だけを効率よく得たい」と考えるようになると、読書はどうしても後回しになってしまいます。なぜなら本は、そのときの自分に必要な情報以外の智識や感情体験、すなわち“ノイズ”を含んでいるからです。
けれども私たちは、本来、他者の文脈に触れながら生きていく社会的な存在です。見聞きするものからノイズを排除して、情報だけで生きることはできません。むしろ、そうしたノイズを受け入れるための余白が、人には必要なのだと思います。そう考えると、私たちの働き方そのものも、そろそろ見直すべき時期に来ているのかな、と感じているところです。
「半身で働く」とは? “余白”を確保する、新しい働き方のスタンダード

――そこで「半身(はんみ)で働く」という提案につながるのですね。
三宅 「半身」とは、正社員として週5日フルタイムで残業もいとわないような“全身全霊”の働き方ではなく、自身の体や時間の半分を会社の仕事に、もう半分を家庭や個人の活動に充てるという考え方です。
社会学者の上野千鶴子さんがあるときテレビ番組で、高度経済成長期以降の男性の働き方に対し、女性の働き方は家庭との両立から「半身」にならざるを得ない、と語っていました。
それを聞いて、私は「むしろ半身が社会のスタンダードになるべきでは?」と思ったんです。男女を問わず、誰もが全身全霊の働き方から脱却すべきだと。もちろん一生の間に、昼夜も忘れて夢中になって働く時期はあってもいいし、必要なときもあるでしょう。けれども人生の終盤まで、時間の大半を仕事に身を捧げるような生き方ってどうなのだろうと。
今は働き方の選択肢も増えていますが、会社のルールは全身全霊の働き方を前提に設計されていますよね。評価や報酬もフルタイムで働く正社員が基準になっていて、それ以外はイレギュラーな位置づけの会社がほとんどでしょう。その前提自体、疑ってみてもいいのではないでしょうか。たとえば正社員でも週3~4日勤務や兼業を認めるなど、柔軟性の高い働き方を、もっと基本の選択肢として捉えていけるといいと思います。
「全力じゃない働き方」が、企業にもたらす3つの追い風
――もし企業が「半身で働く」ことを受け入れた場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?
三宅 一番は、人材の確保がしやすくなることだと思います。若い人たちを中心に、全身全霊の働き方に疑問を持つ人は増えています。「半身で働ける会社のほうがいい」と感じるのは自然な流れでしょう。労働人口がどんどん減っていく中で、こうした姿勢は採用面での追い風になると考えられます。
次に、半身で働くことには、仕事とは別の側面も含まれていることです。それによって組織の多様性が広がり、創造性の高い環境が生まれるのではないでしょうか。子育てや介護だけでなく、副業、起業、趣味などを通じて多様な経験を持つ人が集まると、異なる価値観や合理性を理解し合える土壌も育ちます。
そしてもうひとつ、メンタル不調のリスク軽減にもつながると考えています。仕事のストレスによって、うつや適応障害を起こしてしまう人は少なくありません。どんなに優秀な人でも一度調子を崩してしまうと、復帰までに時間がかかってしまったり、以前と同じ働き方には戻れなかったりしがちです。それは会社と本人の双方にとって、大きな損失といえます。
休職や離職に至らなかったとしても、精神的な疲れがハラスメントの引き金になるケースもあるでしょう。であれば、「常に仕事に全力」を求めるのではなく、70〜80%でいいから安定して力を発揮してもらうほうが、健全な働き方な気がします。
「面倒くささ」の先にある、持続可能な働き方

――半身で働く人材を受け入れると、働き方や意思疎通を一律にできない分、企業側にある種の負担が生じそうです。
三宅 たしかに、人事制度を整えるだけでなく、日々のオペレーションなども含め、一時的に大変になるのは理解できます。けれども、この「面倒くささ」を乗り越えない限りは、日本の働く環境そのものがどんどん縮小していくのではないかと感じています。結局、社会や経済、産業など世の中の構造が大きく変化している中で、依然として「正社員でかつ全身全霊で働ける人」を求め続けた結果が、今の少子化や労働力不足といった状況を招いているようにも思えるんです。
だからこそ、より長い目で見て、社会全体でウェルビーイングな働き方に近づくための選択が求められているのでしょう。そのひとつのあり方が半身で働くというスタイルで、最終的には安定的で持続可能な状態につながるのではないかと考えます。
補足したいのは、半身といっても、業務量を単純に半分にするのではありません。日本は諸外国と比較して、長時間労働と生産性の低さを指摘されています。つまり改善の余地があるわけですよね。本でも述べましたが、長時間労働の一因に「情意考課」という人事制度があります。資料づくりや社内の根回しなど、過度な丁寧さが職場慣行となり、それが評価の対象になってしまっている現実です。
実際に、メールで済む内容をわざわざ打ち合わせにしたり、オンラインでもよさそうなのに対面での予定を組んだり……といったことって、今も意外と多いですよね。その背景には、簡単に済ませると「あなたに時間を割く価値がない」「失礼だ」と受け取られるのではないか、という無意識の遠慮や恐れが潜んでいることもあるでしょう。でも、日本全体で「もっと簡素でいいよね」という共通認識が持てれば、業務量を担保しながら半身で働くことも十分に可能だと考えています。
まずは気軽に、今の働き方を問い直す

――組織全体の生産性を落とさずに、半身で働く組織を築くにはどのような取り組みが必要でしょうか?
三宅 最も手っ取り早いのは、「半身で働く人」を発言力ある立場に置くことです。つまり、若手の登用ですね。現状、会社の役員層の多くは、全身全霊で働くことで地位を築いてきました。そのため、昨今の若手の就業観の変化や早期離職の問題も、理解はできても納得しきれないのが本音ではないでしょうか。
そうなれば、半身で働く当事者に権力を与えて、組織のあり方や仕事の進め方を根底から変えていくくらいの思いきりが必要な気がします。会社が旧態依然のままで若手の失望を招き、早期離職が相次ぐよりもずっといいようにも思います。極論ではありますけどね。
そのうえで、働く場と時間の自由度を高める工夫が大事になってきます。本当に出社が必要な仕事のときだけオフィスに出向く、子育て中の人なら夕方早くに一度パソコンから離れて、子どもと夕飯を済ませて寝かしつけた後にもうひと仕事するというように、空間の制約をできるだけ取り除く。さらに仕事の進め方も、無駄を省いてコンパクトにすることが問われるでしょう。
――副業の歓迎や書籍購入の補助など、仕事以外の過ごし方の支援も有効でしょうか?
三宅 全身全霊から半身に目を向けるという意味で有効だと思います。ただし、そうしたことを受け入れる文化が前提にないと、形骸化してしまうおそれがあります。制度は存在するけど使いにくい、直属の上司や同僚の理解を得られないというようでは、なかなか広まらないでしょう。
まずは、「働き方を考える場をつくること」が大事だと思います。今回の書籍をきっかけに、企業内読書会に呼ばれることが増えたのですが、毎回とても良い場だと感じています。読書会では、部署や役職に関係なく、気軽に話し合える空気がありますし、ふと「自分たちの働き方ってどうなんだろう」と、普段当たり前に受け入れていたことを見直すきっかけにもなります。「我が社の働き方を語ろう」といったテーマでは構えてしまいがちですが、読書会ならフラットに意見交換しやすいですよね。
そこから発展して、「本当は何時に退社したいか」といった理想の働き方を自由に語り合うのも面白いと思います。きっと世代や役職、部署、ライフステージによっても認識は変わってくるでしょう。ギャップを顕在化することで、次の一手が見えてくるかもしれないですね。

――最後に「半身で働く」生き方について、三宅さんの考えをお聞かせください。
三宅 働いていれば、仕事のことで頭がいっぱいになるのはごく自然のことだと思うんです。特に今はスマホがあるから、すぐに連絡もとれますし。むしろ意識的に仕事から離れないと、仕事に呑まれてしまう時代ともいえます。
本を読んだり、いろいろな人と接したりと、仕事の外に自分の身を置くことは、個人の健康面だけでなく仕事にも良い影響を与えると思うんです。仕事から少し自分の頭をずらすことで、新たな視点やアイデアが生まれたり、リフレッシュした状態で仕事に向き合えたりするからです。
それも難しいくらいに余裕がないなら、まずはしっかり体を休めることが大切です。そして、ふと「そういえば、しばらく本を読んでいなかったな」とページをめくる余裕が生まれたら、仕事以外の自分についてぜひ一度、立ち止まって考えてみてほしいですね。
本記事はリサーチコミュニティ会員限定記事です。
リサーチコミュニティとは、総務などオフィス運用やマネジメントに携わる人のみの会員制サービスです。
限定記事の閲覧のほか、各種特典もご用意しております。